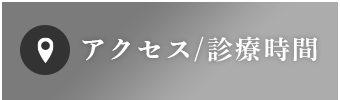インプラントの二次手術とは?目的・内容・流れを徹底解説!
- 2025年4月25日
- インプラント
目次
インプラントの「二次手術」とは?基本をおさらい

・一次手術と二次手術の違いとは?
インプラント治療において「手術」と聞くと一度で完結するイメージを持たれる方が多いかもしれません。しかし、一般的なインプラント治療では「一次手術」と「二次手術」の2段階で行われることが多く、それぞれには明確な役割があります。
一次手術は、インプラント体(人工歯根)を顎の骨に埋め込む処置です。この段階では歯ぐきの下にインプラント体を完全に埋めて、しっかりと骨と結合させるために治癒期間を設けます。そして、骨との結合が確認された後に行われるのが「二次手術」です。二次手術では、歯ぐきを少し切開して埋まっているインプラント体の頭部を露出させ、人工歯を装着するための準備を行います。
このように、一次手術は「骨に固定するため」、二次手術は「人工歯を装着するため」と、それぞれが治療の異なるステップであり、最終的な見た目と機能性を仕上げる重要な工程となっています。
・なぜ二段階で手術を行うのか
「手術は一回で済ませたい」と思う方が多いのは当然ですが、あえて二段階に分けるのは、治療の安全性と確実性を高めるためです。一次手術後に歯ぐきを閉じておくことで、インプラント体が唾液や細菌に触れるリスクを減らし、清潔な状態で治癒を促進できます。これにより、インプラントと骨がしっかりと結合する環境を整えることができるのです。
また、骨の状態や量によっては、初期の安定が得られにくいケースもあります。そういった症例では、無理に一度で処置を進めるよりも、一度インプラントを骨内に埋入し、確実に結合したことを確認した上で次のステップに進むほうが、長期的な成功率が高くなります。
歯ぐきや骨の状態が良好な場合は、一回法(ワンステージ)という選択肢もありますが、多くのケースでは二回法によって段階的に処置を進めたほうが、治療全体の安定性と成功率が高いとされています。
・骨とインプラントが結合する“治癒期間”の意味
一次手術で埋め込まれたインプラント体がすぐに歯として機能するわけではありません。人工歯根がしっかりと顎の骨と結合するまでには、一定の治癒期間が必要です。この期間は「オッセオインテグレーション(骨結合)」と呼ばれ、金属(主にチタン)であるインプラントと生体組織である骨が生理的に結びつく過程を指します。
この結合が不十分なまま次のステップへ進むと、インプラントの脱落や周囲の炎症など、将来的なトラブルを引き起こすリスクが高くなります。したがって、インプラント治療の成功にとって“治癒期間をしっかり設けること”は極めて重要です。通常、この期間は3〜6ヶ月程度が一般的で、患者様ごとの骨の質や量によっても異なります。
この間、患者様はとくに大きな処置は必要ありませんが、感染予防のための口腔ケアや定期チェックが必要になる場合があります。治癒期間を適切に経て、骨との結合が確認できた時点で、インプラント体の一部を歯ぐきの上に出す二次手術へと移行します。
二次手術はどんな内容?実際に行う処置とは

・インプラント体の頭出し(ヒーリングアバットメントの装着)
インプラントの二次手術では、まず一次手術で顎の骨に埋入されたインプラント体の「頭」を歯ぐきの外へ露出させる処置から始まります。これは「頭出し」または「ヒーリングアバットメントの装着」と呼ばれ、人工歯(上部構造)を支える土台を口腔内に見えるように設置する工程です。
具体的には、局所麻酔をしたうえで、インプラント体が埋まっている部分の歯ぐきを少しだけ切開します。インプラント体の頭部が確認できたら、そこに「ヒーリングアバットメント」と呼ばれる小さな金属製のパーツを取り付けます。このパーツは、歯ぐきの形を整えながら、人工歯の装着に向けた準備を進める役割を持っています。
この処置自体は数十分で終わることが多く、出血や痛みも比較的少ないのが特徴です。患者様にとっては大がかりな手術というより、“インプラント治療の最終段階に近づいた”ことを実感できるタイミングとも言えるでしょう。
・歯ぐきを開いて整える「最終準備」
ヒーリングアバットメントを装着するためには、歯ぐきに最小限の切開が必要になります。この工程では、インプラント体の周囲にある歯肉を丁寧に開き、人工歯が自然な形で歯ぐきから生えるように整える処置もあわせて行われます。この“歯ぐきの整形”は、見た目だけでなく清掃性や装着後の安定性にも関わる重要なポイントです。
特に前歯のように審美性が求められる部位では、歯ぐきのラインや厚み、形状を細かく調整することで、まるで天然歯のような見た目に仕上げることが可能になります。この段階での処置が不十分だと、装着後に「不自然に見える」「食べかすが詰まりやすい」といった不具合の原因になりかねません。
歯ぐきの形状は患者様一人ひとり異なるため、二次手術では経験豊富な歯科医師が状態を見極めながら、美しさと機能性を両立させる“最終準備”を進めるのです。この段階で初めて、人工歯の型取りができる口腔内環境が整います。
・人工歯を装着するための土台作り
二次手術で行われるもう一つの重要な目的が、インプラント体に人工歯(上部構造)を取り付けるための「土台」を整えることです。この土台は「アバットメント」と呼ばれ、インプラントと人工歯の橋渡しとなる中間構造です。ヒーリングアバットメントで歯ぐきの治癒が完了した後、本格的なアバットメントへと交換されます。
アバットメントの形状や材質は、最終的に装着する人工歯の種類や位置、噛み合わせの状態によって最適なものが選ばれます。この選定には、歯科技工士との連携も欠かせず、より自然で違和感のない補綴(ほてつ)物を作製するために、細部まで調整が行われます。
また、アバットメントの装着後には、歯科技工所に送るための型取り(印象採得)も行われます。この工程が正確でなければ、人工歯のフィット感や噛み合わせに問題が生じることもあるため、極めて精密な作業が求められる重要なフェーズです。つまり、二次手術は「人工歯をしっかりと機能させるための最後の橋渡し」ともいえるのです。
二次手術は痛い?不安をやわらげるために

・手術は局所麻酔で対応、痛みは最小限
インプラントの二次手術と聞くと、「また手術か…」「痛みがありそう」と不安になる方は多いでしょう。しかし実際には、二次手術は一次手術に比べて体への負担が小さく、局所麻酔で十分に対応できる処置です。処置内容としては、インプラント体が埋まっている歯ぐきを数ミリ切開して、埋入されたインプラント体の頭部を露出し、ヒーリングアバットメントと呼ばれる金属パーツを取り付けるものです。
この処置は患者様によって個人差はありますが、ほとんどの場合で麻酔がしっかり効いており、痛みを感じることはありません。術中の時間も15〜30分程度と比較的短く、入院や全身麻酔を必要とする大がかりな手術とは異なります。施術後の痛みも、一時的な違和感や軽度の鈍痛にとどまることが多く、処方された鎮痛剤を服用すれば日常生活に支障をきたすことはほとんどありません。
不安の大部分は「わからないこと」によって生まれるものです。だからこそ、事前に処置の内容や麻酔の方法、術後の経過についてしっかり説明を受けることが、安心感につながります。過剰な心配をする前に、まずは担当医に相談してみましょう。
・処置時間と当日の流れ
二次手術の当日の流れは非常にシンプルで、患者様の身体的・時間的負担は最小限に抑えられています。まず来院後に簡単な問診と体調確認が行われ、その後に局所麻酔を注射。麻酔が効いていることを確認したうえで、インプラント体が埋まっている歯ぐきの部分に小さな切開を加えます。
インプラント体の頭部を露出させたら、そこにヒーリングアバットメントを取り付けて、周囲の歯ぐきを丁寧に整形。最後に縫合するか、自然に歯ぐきが治癒するように処置をして完了です。全体の所要時間は15分〜30分程度が一般的で、痛みが強く残るような処置ではありません。
術後は、麻酔の影響が残っているため、食事や激しい運動は避けるよう指導がありますが、ほとんどの方が当日中に通常の生活に戻ることが可能です。入院も不要で、通院で完結する処置なので、忙しい方でも予定を調整しやすいのが特徴です。
患者様の不安を軽減するため、歯科医院では当日の注意点や術後の過ごし方について丁寧に説明を行ってくれます。「何が行われるのか」を理解することで、不安はぐっと小さくなるのです。
・術後の腫れ・出血・違和感の程度と対処法
二次手術後の症状として想定されるのは、軽度の腫れや出血、傷口の違和感程度であることがほとんどです。一次手術と異なり、骨に穴を開けるような大きな処置ではないため、体へのダメージは小さく、回復も比較的スムーズに進みます。
腫れについては、術後1〜2日で軽度に出る場合がありますが、保冷剤などで冷やす、処方された抗炎症薬を服用するなどで対処が可能です。また、出血も数時間以内におさまるのが一般的で、ガーゼを軽く噛んで止血することで自然と落ち着いていきます。
違和感についても、ヒーリングアバットメントが装着されることで「何かが当たっている感じ」がすることはありますが、数日で慣れてくる方がほとんどです。歯科医院では、術後のトラブルを防ぐために必要なケア方法や生活上の注意点を説明してくれるほか、必要があれば追加の診察や処置にも迅速に対応します。
万が一、腫れや痛みが数日以上続く、熱が出るなどの異常があれば、早めに連絡し再診を受けることで重篤化を防ぐことができます。何よりも、術後の小さな変化に気づいたときには一人で悩まず、遠慮なく歯科医院に相談することが大切です。
二次手術が必要な理由と役割

・インプラントと骨がしっかり結合するまで待つ意味
インプラント治療では、人工歯根となるチタン製のインプラント体を顎の骨に埋入した後、一定期間をおいて二次手術を行うのが一般的です。その理由は、インプラントと骨がしっかりと結合(オッセオインテグレーション)するまで、治癒期間を確保する必要があるからです。この骨結合の過程は、インプラントの長期的な安定性と機能性に直結する極めて重要なプロセスです。
インプラント体は体内に埋め込まれる異物でありながら、チタンという生体親和性の高い素材を使用することで、骨細胞がインプラント表面に直接結合するようにデザインされています。しかし、この結合には時間がかかるため、一次手術後すぐに人工歯を取り付けてしまうと、インプラントが動いたり、感染のリスクが高まったりする可能性があります。
しっかりと骨との結合が確認できてから二次手術に進むことで、長く安定して噛めるインプラント治療の基盤が完成するのです。そのため、二次手術は単なる「追加の処置」ではなく、治療成功のための必須ステップといえます。
・歯ぐきの形を整えることで自然な見た目へ
インプラント治療において、見た目の自然さは患者様の満足度に直結します。とくに前歯のように審美性が重視される部位では、歯ぐきのラインや厚み、自然なカーブが仕上がりの印象を大きく左右します。二次手術では、インプラント体の頭出しだけでなく、歯ぐきの形を調整する処置が行われます。
この処置を「歯肉形成」と呼び、ヒーリングアバットメントの装着とともに、歯ぐきが人工歯を自然に包み込むような状態へと導いていきます。歯ぐきの形が整っていないと、人工歯の周囲に段差や隙間ができ、見た目が不自然になるだけでなく、清掃不良や炎症のリスクが高まります。
また、歯ぐきが美しく整っていると、隣接する歯との調和が取れ、まるで自分の歯のように仕上がります。これにより、笑ったときや話したときの見た目に自信が持てるようになり、QOL(生活の質)の向上にもつながるのです。歯ぐきを整える二次手術の意義は、見た目だけでなく、機能面・衛生面にも大きなメリットをもたらします。
・長期的に安定したインプラントのために重要なステップ
二次手術は、インプラント治療の「完成」に向けた最終準備であり、将来的なトラブルを防ぐための重要なステップでもあります。たとえば、一次手術後にインプラント体が骨と結合していても、適切に頭出しがされておらず、歯ぐきの形が不自然だった場合、人工歯の装着後に噛み合わせや清掃性に問題が出る可能性があります。
また、ヒーリングアバットメントの装着によって歯ぐきが自然な形に落ち着くことで、その後に取り付ける上部構造(人工歯)がピッタリと適合し、隙間ができにくくなります。これは、インプラント周囲炎といった炎症リスクの低減にもつながるため、長期的な予後を考えるうえで非常に重要です。
さらに、二次手術の段階でしっかりとインプラントの安定性を確認できれば、その後の噛み合わせ調整や補綴物の作製にも高い精度が期待できます。逆にこの工程を省略したり、急ぎすぎたりすると、見た目の違和感だけでなく、数年後にインプラントが緩んだり脱落したりといったリスクが高まります。
つまり、二次手術は治療の「仕上げ」であると同時に、患者様がインプラントを長く快適に使っていただくための“品質保証”ともいえる工程です。ここを丁寧に行うことで、インプラント治療は初めて本当の意味で完成するのです。
二次手術のタイミングと判断基準

・骨の状態や治癒状況に応じた判断
インプラント治療において、二次手術の実施タイミングは非常に重要です。なぜなら、インプラント体が骨としっかりと結合していなければ、上部構造を装着しても長期的な安定が得られないからです。二次手術は、単に「いつやるか」というカレンダー的な話ではなく、顎の骨の治癒状態を見極めた上での判断が必要となる医療的判断です。
骨の質や量は個人差が大きく、たとえば骨密度が高い下顎の場合は治癒が比較的早いことが多い一方で、上顎や骨移植を伴ったケースでは治癒に時間がかかる傾向があります。また、高齢者や糖尿病などの全身疾患がある患者様では、骨の再生力が低下している場合もあるため、より慎重な判断が求められます。
このように、二次手術のタイミングは「○ヶ月経てばOK」といった一律のものではなく、個々の状態に応じたオーダーメイドな判断が不可欠です。歯科医師は、レントゲンやCTでの画像診断、インプラントの初期安定性、患者様の体調など多面的に評価したうえで、最適なタイミングを見極めているのです。
・一般的な目安はいつ?(3〜6ヶ月が多い)
一般的には、一次手術から二次手術までの期間は3〜6ヶ月程度が目安とされています。この期間は、インプラント体と骨との間にしっかりとした骨結合(オッセオインテグレーション)が起こるために必要な時間とされており、これにより治療後の安定性や予後が大きく左右されます。
ただし、前述のように骨の状態や個人の治癒力によってこの期間は前後します。骨造成やサイナスリフトなどの外科的処置を伴ったケースでは、骨の成熟を待つためにさらに数ヶ月の治癒期間を設けることもあります。一方で、骨の質が良好で初期固定が得られている場合には、4〜6週間程度で二次手術を行うケースもあります。
つまり、3〜6ヶ月というのはあくまで「平均的な目安」であり、その期間内に必ず二次手術をしなければならないわけではありません。焦って早めてしまうことで結合が不十分なまま上部構造を装着してしまうと、後々のトラブルにつながるリスクが高まります。大切なのは、「いつやるか」ではなく「いつならやってもいい状態か」を見極めることです。
・医師が慎重にタイミングを見極める理由
インプラントの二次手術は、治療の最終段階へ進むための重要なステップです。だからこそ、歯科医師はそのタイミングを慎重に判断しています。「せっかくここまで進めたのだから、焦らず確実に仕上げたい」というのがプロフェッショナルとしての共通認識です。
たとえば、レントゲンやCT画像で明らかな骨結合が確認できない場合や、術部に感染兆候が見られるような場合には、たとえ予定より日数が経過していても二次手術は延期されます。逆に、骨が良好に回復しており、かつ全身状態も安定しているなら、通常よりもやや早めに二次手術を行うケースもあります。
このように、患者様の安全と治療の成功を最優先に考えているからこそ、歯科医師はタイミングを“慎重に”見極めるのです。また、インプラント体にかかる咬合圧(噛む力)をコントロールするためにも、しっかりと治癒した状態でアバットメントや人工歯を装着することが求められます。
もし患者様自身が「そろそろ次のステップに進みたい」と思っていても、医師が「まだ様子を見ましょう」と判断することがあるのは、あくまでトラブルを未然に防ぎ、長持ちするインプラント治療を提供するための配慮だと捉えていただければと思います。
一次手術と二次手術の間にしておくべきこと

・治癒期間中の口腔ケアのポイント
一次手術から二次手術までの期間中は、インプラント体が顎の骨としっかりと結合するための重要な治癒期間です。この間のセルフケアが、その後のインプラント治療の成功を大きく左右します。特に注意すべきは、手術部位の感染を防ぐことと、周囲の歯ぐきや天然歯を健康に保つことです。
術後しばらくは、インプラント体が完全に歯ぐきの中に埋まっているため、表面からは見えません。しかし、手術直後の数日は傷口の保護と清潔維持が重要です。歯科医院から処方されるうがい薬や抗生物質を正しく使用し、ブラッシングの際には傷を避けるように優しく行いましょう。硬い食べ物や刺激の強いものも避けることで、出血や痛みのリスクを減らせます。
また、インプラント周囲の歯肉環境を清潔に保つために、歯ブラシだけでなくデンタルフロスや歯間ブラシも活用し、プラークコントロールを徹底することが大切です。特に、天然歯に歯周病がある場合、そこから細菌がインプラント周囲に移行する可能性があるため、徹底した予防管理が求められます。定期的なメンテナンスやプロによるクリーニングも忘れずに行いましょう。
・仮歯や周囲の歯をどう扱う?
一次手術後、インプラント部分にはまだ人工歯が装着されていないため、噛む機能や見た目のバランスを保つ目的で「仮歯(テンポラリークラウン)」を入れることがあります。これはあくまで一時的なものですが、日常生活において違和感なく過ごすためのサポートとして有効です。
仮歯は歯ぐきの治癒に悪影響を及ぼさないように作られており、強く噛まない、ねじらない、必要以上に清掃器具でこすらないなど、取り扱いには一定の注意が必要です。過度な力が加わると、仮歯が外れたり、インプラント体に過剰な負担がかかることがあります。また、仮歯が壊れたりフィット感が悪くなった場合は、すぐに歯科医院へ連絡し調整してもらうようにしましょう。
さらに、インプラント部位の両隣の歯や、対合する歯(かみ合う歯)への意識も重要です。咬み合わせのバランスが崩れないように、周囲の歯の清掃と管理を徹底し、かつ無意識にその部位ばかりで噛まないようにするといった日常の配慮も、治療全体の成功率を高めるポイントになります。
・喫煙や食生活への注意点
治癒期間中に特に意識していただきたいのが、喫煙の影響と食習慣の見直しです。喫煙はインプラントの治癒を妨げる最大のリスク因子の一つです。ニコチンや一酸化炭素は血管を収縮させ、酸素や栄養の供給を阻害するため、インプラントと骨の結合がうまくいかず、失敗リスクが大幅に高まります。
インプラント手術の前後で禁煙を勧められるのはこのためで、少なくとも手術の前後2週間は禁煙することが望ましいとされています。できれば、この治療を機に禁煙に取り組むことが、口腔内だけでなく全身の健康にも良い影響をもたらします。
また、食生活にも注意が必要です。特に一次手術後の数週間は、硬いもの・熱いもの・刺激物(スパイスやアルコールなど)を控えることが推奨されます。インプラント部位に無理な負荷をかけないためにも、軟らかく栄養価の高い食事を意識し、バランスの取れた栄養摂取で治癒をサポートすることが理想的です。
糖分の多い食事や間食も、インプラント周囲のプラーク蓄積を促し、細菌感染やインプラント周囲炎の原因になりやすいので注意が必要です。生活習慣全体を見直し、良好な治癒環境を整えることが、次のステップにスムーズに進むための鍵となります。
二次手術後に気をつけるべき生活上の注意点

・食事・運動・睡眠時の注意事項
二次手術後はインプラント体の頭が口腔内に露出し、ヒーリングアバットメントが装着された状態になります。この段階では大がかりな処置は終了していますが、歯ぐきの治癒を促し、インプラント周囲に清潔で安定した環境を保つことが非常に大切です。日常生活における小さな行動の積み重ねが、最終的な治療結果に大きく影響を与えます。
まず、食事に関しては、術後数日は柔らかく刺激の少ない食事を選ぶことが望ましいです。硬いものや熱すぎる・冷たすぎる飲食物は、傷口の刺激や出血の原因になることがあります。アバットメント周辺は歯ぐきがまだ安定していないため、無理な咀嚼圧がかからないよう、反対側で咬むように心がけましょう。
また、激しい運動や長時間の入浴、アルコールの摂取も術後2〜3日は避けるべきです。これらは血行を促進して出血や腫れを助長する可能性があります。睡眠時は頭の位置を少し高くして寝ると腫れを抑えるのに有効です。無意識の歯ぎしりがある方は、ナイトガードの使用について歯科医師に相談しておくと安心です。
・傷口のケアと再感染予防
インプラントの二次手術は比較的小さな処置とはいえ、歯ぐきを切開した部位は一時的に外界とつながる「開放創」となります。そのため、細菌感染を防ぐための傷口ケアが非常に重要です。特に歯磨きやうがいの方法は、通常よりも慎重さが求められます。
まず、術後24時間は強いうがいを避け、処方された消毒薬で軽く口をすすぐ程度にとどめましょう。翌日以降は、歯ブラシの毛先が傷口に直接当たらないように注意しながら、周囲をやさしく清掃することでプラークの付着を防ぎます。ヒーリングアバットメントの周囲に汚れが溜まると、炎症を起こして歯ぐきの治癒が遅れたり、最悪の場合インプラント周囲炎に進行するリスクもあります。
再感染を予防するためには、喫煙の継続・糖尿病などの基礎疾患・口呼吸の癖などもリスク因子として考慮する必要があります。術後の経過観察時には、医師に気になる症状(出血が続く、腫れがひかない、異臭がするなど)を遠慮なく伝えることが大切です。早期に対応することで、問題を大きくせずに済むケースがほとんどです。
・必要な通院頻度と観察ポイント
二次手術後は、いよいよ人工歯の装着に向けたステップが始まります。ですが、この段階でもインプラント周囲の歯ぐきやアバットメントの状態を正しく評価するための通院が不可欠です。多くの歯科医院では術後1週間程度で傷の確認と抜糸(縫合した場合)を行い、歯ぐきの治癒状態を観察します。
このとき歯科医師は、ヒーリングアバットメントの装着状態や歯ぐきの腫れ、炎症、出血の有無を細かくチェックし、人工歯の型取り(印象採得)に進むかどうかを判断します。ここで問題があれば治癒をもう少し待つ場合もありますし、必要に応じてアバットメントの交換や形状調整を行うこともあります。
また、ヒーリングアバットメント装着後に数週間放置すると、プラークの蓄積や歯ぐきの不安定化が進む恐れがあるため、最低でも2〜3週間ごとの通院が推奨されます。通院のたびに、日々の清掃状況や生活習慣についての指導も行われるため、患者様自身の意識向上にもつながります。
特に二次手術後のこの期間は、インプラントとお口全体の環境が最終調整に入る大切なフェーズです。見た目・機能・長期的な安定性のいずれをとっても、この段階の丁寧な経過観察が今後何年にもわたるインプラントの快適さを支える土台になるといえるでしょう。
一次手術と二次手術をまとめて行うケースとは?

・一回法(ワンステージ)の概要と適応条件
インプラント治療には「二回法(二段階手術)」が主流ですが、患者様の状態によっては「一回法(ワンステージ)」という方法を選択できる場合があります。一回法では、インプラント体を埋入する一次手術の際に、同時にヒーリングアバットメントも取り付けるため、二次手術が不要となるのが特徴です。
この術式は、骨の質や量が十分にあり、インプラント体が初期の段階でしっかりと安定する場合に適応されることが多いです。特に下顎の臼歯部など、骨密度が高く治癒が早い部位では、患者様の負担を軽減する選択肢として効果的です。加えて、二次手術を省略できることで、治療期間の短縮にもつながります。
ただし、一回法はすべての症例に適しているわけではありません。骨造成を行った部位や、骨質が軟らかい場合、治癒に時間がかかるケースでは、二回法のほうが確実性が高くなります。また、ヒーリングアバットメントが早期に露出することで感染リスクが高まるという懸念もあるため、術式の選定には細心の注意が必要です。
・二回法との違いとそれぞれのメリット・デメリット
一回法と二回法の最大の違いは、「インプラント体の埋入後、歯ぐきを完全に閉じるかどうか」にあります。二回法ではインプラント体を歯ぐきの中に完全に埋め、治癒期間を確保したのち、必要に応じて二次手術で頭出しを行うというステップを踏みます。一方、一回法ではインプラント体とアバットメントを同時に露出させたまま治癒させるため、術後の管理が大きく異なります。
二回法のメリットは、感染リスクが少なく、骨とインプラントの結合に集中できること。また、歯ぐきを閉じることでインプラント部位を外部からの刺激から守れるため、骨造成や全身疾患を持つ患者様にも適応しやすいです。一方で、二回法では治療期間が長くなり、手術が2回必要になるため、精神的・身体的な負担が増えるというデメリットもあります。
一回法のメリットは、治療期間の短縮と、手術回数が1回で済むことです。手術に対する不安が強い方や、通院回数を減らしたいという希望がある患者様にとって魅力的な選択肢です。しかし、アバットメントが口腔内に露出している状態で数ヶ月を過ごすため、日常のセルフケアが極めて重要であり、リスク管理も必要になります。
・どちらが合うかは個人差あり
インプラント治療において、どちらの術式を選ぶべきかは、「患者様の状態に最も適した方法を選択する」ことが原則です。医師が骨の状態や全身疾患の有無、口腔内の清掃状況、さらには患者様の生活スタイルまで考慮し、最善の治療計画を立てていきます。
たとえば、日頃から口腔ケアに自信があり、喫煙などのリスク因子が少ない方であれば、一回法での治療が適応されるケースも十分にあります。逆に、慢性的な歯周病の既往がある方や、骨造成を行った方、全身疾患(糖尿病、骨粗鬆症など)がある方の場合は、より確実な治癒を重視して二回法が選ばれることが多くなります。
また、審美性が求められる前歯部では、歯ぐきのラインや見た目を細かく調整できる二回法の方が好まれる傾向にあります。一方で、臼歯部など機能性が重視されるエリアでは、早期に咀嚼機能を回復できる一回法が適している場合もあります。
最も大切なのは、患者様自身が治療の内容と目的をしっかり理解し、納得の上で術式を選ぶことです。「手術が一度で済むかどうか」だけにとらわれず、長い目で見てインプラントを快適に使い続けられるかを考えることが、成功への鍵となります。
二次手術を経て人工歯を装着するまでの流れ

・印象採得(型取り)から上部構造の作製へ
インプラントの二次手術が終わると、いよいよ「歯」となる上部構造を作るための工程に入ります。その最初のステップが「印象採得(いんしょうさいとく)」、いわゆる型取りです。これは、口腔内のインプラントの位置や歯ぐきの形態、隣接する歯との関係などを正確に再現するための非常に重要な工程です。
型取りの方法には、従来のシリコン印象材を用いる方法と、口腔内スキャナーによるデジタル印象があります。いずれにしても、1本の歯だけでなく周囲の歯列全体との調和を図るため、数ミリ単位の精密さが求められます。この型に基づいて、歯科技工士が患者様専用の上部構造(クラウン)を製作します。
クラウンの素材には、見た目を重視する場合はセラミック、強度を重視する場合はジルコニアやメタルボンドなどが選ばれることが多いです。これらは色や形もオーダーメイドで作られるため、自然な見た目と機能性を両立した“自分だけの人工歯”が完成します。
・噛み合わせ調整と色・形の確認
上部構造の製作が終わった後、いよいよ口腔内への試適(してき)となります。この段階では、単に人工歯を“はめる”だけではなく、見た目・噛み合わせ・周囲の歯との調和など、あらゆる角度からの微調整が行われます。特に噛み合わせの調整は非常に重要で、わずかなズレが全体のバランスに影響を及ぼす可能性があるため、慎重な作業が求められます。
まずチェックされるのが、「咬合(こうごう)」です。上下の歯がきちんと接触しているか、力のかかり具合に偏りがないかを、咬合紙などを使って確認します。その後、患者様に「噛んだ感覚」や「口を閉じたときの違和感」がないかを直接伺いながら、必要に応じて人工歯の高さや接触面を細かく調整していきます。
また、セラミックやジルコニアなどの素材では、周囲の歯の色味に合わせた自然なグラデーションや透明感を持たせるため、色調の確認も行われます。とくに前歯部では光の反射まで考慮し、笑ったときの印象や対人コミュニケーションに影響しないよう、細部までこだわった仕上げが可能です。こうした丁寧な工程を経ることで、まるで天然歯のような自然な見た目と噛み心地を実現できるのです。
・最終的な装着とメンテナンスの重要性
すべての調整が終わると、いよいよインプラントの上部構造(人工歯)の「最終装着」が行われます。装着の方法は主に2種類あり、「スクリュー固定」と「セメント固定」に分かれます。スクリュー固定は取り外しが可能で、メンテナンス性に優れるのが特徴。一方で、セメント固定は見た目が自然で、審美性を重視する部位に適している場合があります。
装着後は、患者様に咬み心地や見た目に問題がないかを再確認し、治療は一通りの流れを終えます。しかし、インプラント治療の“本当の始まり”はここからといっても過言ではありません。なぜなら、インプラントは天然歯と異なり、自己修復能力や歯根膜がないため、炎症や力の偏りにとても敏感なのです。
そのため、治療終了後には、3〜6ヶ月ごとの定期検診(メンテナンス)が必須となります。ここでは、噛み合わせのチェックやプラークの除去、インプラント周囲炎の早期発見などが行われ、インプラントを長く快適に使い続けるための“予防管理”が徹底されます。
メンテナンスを怠ると、せっかく装着した人工歯も数年で脱落してしまうリスクがあるため、患者様自身が「自分の歯のように責任を持ってケアする」意識を持つことが何より大切です。最終装着はゴールであると同時に、インプラントライフのスタート地点でもあるのです。
二次手術が不安な方へ|安心して受けるためのポイント

・医師との十分なカウンセリングで不安を解消
インプラントの二次手術に不安を抱えている方の多くは、「どんな処置が行われるのか分からない」「痛みや腫れが心配」といった漠然とした不安を感じているものです。こうした不安は、医師との丁寧なカウンセリングによって具体的な情報を得ることで、大きく軽減することができます。
二次手術では、局所麻酔下で歯ぐきをわずかに切開し、インプラント体の頭部(プラットフォーム)を露出させて、ヒーリングアバットメントというパーツを装着します。時間にして15〜30分程度の処置であり、痛みも麻酔によって最小限に抑えられます。このような処置内容を、患者様ご自身が事前に理解しておくことが、精神的な安心につながります。
また、医師との会話の中で「どのタイミングで何をするのか」「術後はどんな経過が予想されるのか」「自分の場合はどうなのか」といった、パーソナライズされた説明を受けることが、信頼関係の構築と不安の軽減に直結します。質問しにくいと感じるような小さなことでも、遠慮せず伝えてみることで、より安心して治療に臨むことができるでしょう。
・施設の衛生・設備・症例実績の確認
安心して治療を受けるためには、実際に治療を行うクリニックの環境や体制が整っているかどうかも非常に重要なポイントです。インプラント治療は精密な手術を伴う医療行為であり、衛生管理や機器の充実度がそのまま治療の安全性や成功率に影響を与えるからです。
たとえば、手術専用の個室オペ室があるかどうか、感染対策としての滅菌システムや空調環境が整っているか、使用するインプラントメーカーは信頼性が高いものかなど、医院の設備や取り扱う製品に対するこだわりをチェックすることが安心材料になります。また、歯科用CTによる精密な診断が可能かどうかも、安全な二次手術には欠かせない要素です。
加えて、その医院がこれまでにどれだけのインプラント治療の症例を持っているか、どのような患者層に対応しているかといった「実績」も参考になります。公式サイトやカウンセリング時に確認できる範囲で構いませんので、自分の症例に近いケースの経験があるかどうかを確認するだけでも、安心して任せられるかの判断材料になるでしょう。
・セカンドオピニオンや相談だけでもOK
「二次手術に進むべきかどうか迷っている」「今通っている歯科医院の説明だけでは不安がある」――そう感じた場合、セカンドオピニオンを活用するのも、安心して治療に進むための有効な手段です。セカンドオピニオンとは、現在の治療計画に対して別の医師の見解を聞くことで、治療方針の妥当性や他の選択肢を比較・検討できる仕組みです。
特に、インプラントのように外科的な処置を伴う治療では、患者様が100%納得したうえで進めることがとても大切です。「他の先生の意見を聞きたい」と思ったときにそれを躊躇する必要はなく、むしろ納得感のある選択をするために当然の権利といえます。
また、最近では「相談だけでも歓迎」というスタンスの歯科医院も増えています。初回相談であれば無料のところもあり、無理に治療を勧められる心配もありません。治療の進め方だけでなく、「費用感」や「通院期間」「生活への影響」など、治療以外の心配事についても話せる環境が整っているクリニックは、患者様に寄り添う姿勢があると言えるでしょう。
結果として相談したうえで現在の主治医に戻って治療を続けるケースもありますし、新たな医院に移る判断をすることもあります。どちらを選んでも、「自分で納得して選択した」というプロセスが、治療への信頼感と安心感につながります。
埼玉県大宮の再治療0%を追求した
審美インプラント治療ガイド
監修:関口デンタルオフィス大宮
電話番号:048-652-1182
*監修者
関口デンタルオフィス大宮
*経歴
・2008年 日本大学歯学部卒業
日本大学歯学部臨床研修部入局
・2009年 日本大学歯学部補綴学第一講座入局
専修医
顎関節症科兼任
・2014年 同医局退局
関口デンタルオフィス開院
*所属学会
*スタディークラブ
・CIDアクティブメンバー(Center of Implant Dentistry)