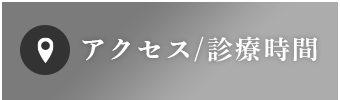喫煙していてもインプラントはできる?成功率を高めるための対策
- 2025年8月22日
- インプラント
目次
喫煙者のインプラント治療、なぜこんなに不安になるのか?

・「喫煙している自分は無理かも…」という不安の正体
インプラント治療は、歯を失った部分に人工歯根(インプラント体)を埋入し、あごの骨としっかり結合させることで、天然歯に近い噛み心地と審美性を取り戻す治療法です。しかし、成功の鍵を握るのが「骨との結合」や「治癒の過程」であるため、喫煙による血流障害や免疫力の低下が不利に働くとされており、治療を検討する喫煙者の方は「自分には無理かもしれない」と不安を抱きやすくなります。
とくにインプラントに興味を持ち始めた段階では、喫煙習慣を理由に「治療の選択肢がなくなるのでは」といった思い込みが先行しがちです。また、禁煙が難しい現実を自覚しているほど、「どうせ続かない」「怒られるかも」といった自己否定的な心理が働き、積極的に相談する気持ちになれないこともあるでしょう。
・医師に相談しにくい、否定されるかもしれないという心理
喫煙が健康に悪影響を及ぼすことは広く知られていますが、その一方で、タバコは強い依存性を持つため簡単にやめられるものではありません。だからこそ、「喫煙しています」と医師に伝えることで、否定的な反応をされるのではないかと身構えてしまう患者さんも多くいます。とくに過去に別の治療で禁煙を強く促され、罪悪感を抱いた経験がある方は、「また怒られるかもしれない」と感じ、正直に相談すること自体を避けてしまいがちです。
しかし、歯科医師は「患者さんの生活背景も含めて治療を支える専門家」です。無理に禁煙を迫るのではなく、喫煙による影響を正確に評価した上で、現実的な対策や治療法を一緒に検討することが本来の医療の在り方です。必要なのは、否定を恐れずに事実を共有する勇気と、患者側の事情を尊重してくれる専門医との信頼関係なのです。
・ネット情報で余計に不安になる人が多い理由
「インプラント 喫煙 影響」と検索すると、「失敗率が高い」「インプラントがすぐダメになる」「喫煙者は治療できない」といった強い言葉を目にすることがあります。こうした断定的で刺激的な表現は、読者の不安を煽りやすく、医学的な根拠や前提条件が示されていないまま拡散されているケースも少なくありません。
本来、インプラント治療の可否やリスク評価は、口腔内の状態、全身の健康、喫煙の頻度・年数など、さまざまな要素を総合的に判断して決められるものです。しかし、ネット上には「喫煙=インプラント不可」といった短絡的な情報が氾濫しており、それを鵜呑みにしてしまうと、本来受けられるはずの治療機会を自ら閉ざしてしまうことにもなりかねません。
また、口コミや体験談に依存しすぎることで、「自分も同じようにうまくいかないのでは」というネガティブな思い込みが強くなる傾向もあります。個人の体験は決して医療の普遍的な指標にはならず、むしろ自身の状態を正確に知ることこそが、信頼できる判断材料になります。インターネットは便利な情報源である一方、情報の真偽を見極める力も求められる時代です。
知っておきたい基本情報|インプラントと喫煙の基礎知識

・インプラント治療とは?治療の流れと目的
インプラント治療とは、歯を失った部位に人工歯根(インプラント体)を埋め込み、あごの骨と結合させた上で、人工の歯(上部構造)を装着する治療法です。天然歯のような見た目と噛む力を取り戻せるのが大きな特徴で、見た目の美しさと機能性の両立を図ることができます。治療の流れは、事前の検査・診断に始まり、一次手術(インプラント体の埋入)、必要に応じた二次手術(アバットメントの装着)、そして最終的な人工歯の装着へと進みます。従来のブリッジや入れ歯とは異なり、周囲の健康な歯を削る必要がなく、長期的な口腔の安定性が期待できる点も、選ばれる理由の一つです。
・喫煙によって身体に起こる生理学的変化
喫煙は、全身にさまざまな悪影響を及ぼすことが科学的に証明されています。ニコチンは血管を収縮させる作用があり、組織への血流が低下することで酸素や栄養の供給が妨げられます。また、一酸化炭素の影響で赤血球の酸素運搬能力も低下し、全身の細胞が十分な酸素を受け取れなくなります。さらに、喫煙は白血球の機能低下を引き起こし、免疫力が下がることで炎症や感染のリスクが増大します。インプラント治療においては、これらの生理的変化が「骨とインプラント体の結合不全」や「術後感染」につながるため、治癒の過程に大きな影響を及ぼす可能性があるのです。
・血流・免疫・回復力とタバコの関係
インプラントの成功において重要な要素の一つが「骨結合(オッセオインテグレーション)」です。この過程では、インプラント体とあごの骨が安定的に一体化する必要がありますが、喫煙によって血流が悪化すると、組織の再生や修復に必要な栄養素や酸素の供給が滞り、骨結合が阻害されやすくなります。加えて、ニコチンによる免疫機能の抑制により、細菌感染への抵抗力も低下します。術後の傷口が治りにくくなり、インプラント周囲炎をはじめとする合併症のリスクが高まる点も見逃せません。このように、「インプラント 喫煙 影響」は密接に関連しており、喫煙は治療成績に影響を与える重要な因子であると考えられています。
喫煙がインプラント成功率に影響するメカニズム
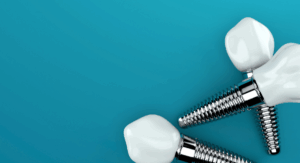
・骨とインプラントの結合を阻害する「血流障害」
インプラント治療の成否を大きく左右するのが、「オッセオインテグレーション」と呼ばれる、インプラント体と顎の骨が直接結合するプロセスです。この骨結合には、十分な血流が必要不可欠です。しかし、喫煙に含まれるニコチンは血管収縮作用をもたらし、局所の血流を悪化させてしまいます。その結果、創傷部位に十分な酸素や栄養が届かず、骨の再生や治癒過程が遅延、あるいは不完全になるリスクが高まります。とくに、インプラントを埋入した直後の数週間は初期固定が求められる重要な期間ですが、この時期に血流が確保されないと、インプラント体が骨に安定して結合できず、早期脱落に至るケースもあります。「インプラント 喫煙 影響」という視点で見たとき、この血流障害は喫煙者特有の明確なリスクとして認識されるべき重要な因子です。
・喫煙者が感染リスクや術後合併症を起こしやすい理由
喫煙は、体の自然治癒力や免疫機能を広範囲に低下させることが知られています。ニコチンや一酸化炭素は白血球の働きを鈍らせ、細菌に対する防御機能を弱体化させます。これはインプラント手術において極めて重要な問題であり、術後の創傷が感染しやすくなるだけでなく、慢性的な炎症が続きやすくなる原因ともなります。また、喫煙によって唾液の分泌量が減少し、その浄化作用も低下するため、口腔内の細菌バランスが崩れやすくなる傾向があります。インプラントは、天然歯と異なり歯根膜が存在しないため、免疫バリアの弱さを補うことができません。そのため、わずかな炎症やプラークの蓄積が、すぐにインプラント周囲の骨にダメージを与える可能性があります。喫煙習慣は、術後合併症を引き起こす「誘因」として、非常に警戒すべきリスクなのです。
・長期的な予後に与える喫煙の影響
たとえインプラント手術が初期的に成功したとしても、喫煙を続けることでその予後が大きく損なわれるケースが少なくありません。特に注意すべきは「インプラント周囲炎」の発症リスクです。これはインプラントを支える歯槽骨が炎症によって徐々に破壊されていく病態で、天然歯における歯周病に類似しています。喫煙者は歯ぐきの炎症反応が出にくいため、異常に気づくのが遅れる傾向があり、気づいたときにはすでにインプラントがぐらついていたという事例もあります。加えて、慢性的な血管収縮や免疫抑制の影響は、メンテナンス時の治癒回復にも悪影響を与えるため、同じケアを行っていても喫煙者は非喫煙者に比べて長期的な安定性が劣ることが分かっています。喫煙が与える影響は、単に「手術がうまくいくかどうか」だけでなく、「どれだけ長く快適にインプラントを使い続けられるか」にも直結しているのです。
喫煙者でもインプラント治療は可能?専門家の見解

・一律に「喫煙=NG」ではない現実
インプラント治療を検討している喫煙者の方の中には、「喫煙しているから無理だろう」と自己判断で諦めてしまう方が少なくありません。しかし、実際には喫煙者すべてが治療不適応というわけではなく、歯科医師の診断によっては十分に治療が可能なケースもあります。確かに「インプラント 喫煙 影響」という観点では、非喫煙者と比較して成功率がやや低くなる傾向は報告されていますが、これは個人の健康状態や治療計画によって変わります。禁煙指導を前提とするケースもありますが、患者さんの意思や背景を尊重し、リスクを管理しながら実施する選択肢も現代の歯科医療では広がっています。重要なのは、思い込みで判断せず、専門医の意見を受けたうえで選択することです。
・成功率を左右するのは「喫煙の有無」だけではない
インプラント治療の成功を左右する要因は、喫煙の有無だけに限られません。たとえば、糖尿病や骨粗鬆症などの全身疾患がある場合、インプラントの治癒や維持に影響を及ぼすことがあります。また、歯周病の有無や顎骨の状態、咬み合わせのバランスなど、口腔内の健康状態も重要な評価項目です。喫煙は確かにリスク因子の一つではありますが、それだけで可否が決まるものではなく、喫煙者でも他の条件が良好であれば治療が可能と判断されることもあります。つまり、「喫煙=治療できない」と決めつけるのではなく、他のリスクとあわせて総合的に評価されるというのが、臨床現場における実情です。
・医師が重視する「全身状態」「口腔環境」「生活習慣」
インプラント治療の適応を判断するうえで、歯科医師は「喫煙しているかどうか」だけでなく、患者さんの全身状態や生活習慣、口腔内の清掃状態なども含めて総合的に評価します。例えば、高血圧や心疾患、糖尿病といった持病が安定していない場合は、手術時のリスクが高まるため慎重な対応が必要です。口腔環境においては、歯周病の進行具合やプラークコントロールの習慣なども治療結果に影響を与える要素となります。また、喫煙だけでなく、食生活や睡眠習慣、ストレス管理といった日常生活の質も、術後の治癒やインプラントの長期安定に関係してきます。こうした観点からも、喫煙の影響を過度に恐れるのではなく、自分の全体的な健康管理と向き合うことが、治療成功の鍵となります。
成功率を高めるには?喫煙者ができる対策とは
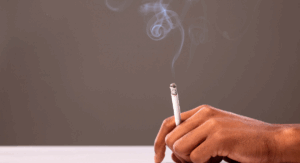
・手術前後の禁煙期間が与える影響
インプラント治療における喫煙の影響は、手術の前後においてとくに顕著です。ニコチンによる血管収縮や免疫機能の低下は、インプラント体と骨の結合を妨げたり、術後の感染リスクを高めたりする要因となります。そのため、できる限り「手術の2週間前から禁煙を始め、術後も少なくとも8週間は継続する」ことが望ましいとされています。この期間に喫煙を控えることで、創傷治癒に必要な血流や酸素供給が正常に保たれ、骨結合の成功率を高める効果が期待できます。禁煙は一時的でも治療結果に大きく寄与するため、「完全にやめられないから無理」と諦めず、一時的な禁煙からでも取り組む価値があります。
・ニコチンパッチ・代替法の活用方法
喫煙の習慣は身体的な依存だけでなく、精神的な習慣にも深く関係しています。そのため、ただ我慢するだけの禁煙では挫折しやすく、成功率も低くなりがちです。そこで有効なのが、ニコチンパッチやニコチンガムといった「代替療法」の活用です。これらは体内のニコチン濃度を安定させつつ、喫煙による有害物質の摂取を回避できるため、無理のない禁煙支援として広く用いられています。とくにインプラント手術を控えている場合、医師と相談のうえ適切な禁煙支援法を選択することで、禁煙のハードルを大きく下げることができます。「インプラント 喫煙 影響」を正しく理解したうえで、計画的に禁煙を支援する体制を整えることが、成功への近道です。
・術後の口腔ケアとメンテナンスの重要性
インプラントは、埋入後の長期的なメンテナンスによって初めて機能を維持できる治療法です。特に喫煙歴のある方は、インプラント周囲炎のリスクが高いため、治療後のセルフケアとプロフェッショナルケアの両立が欠かせません。具体的には、適切なブラッシングや歯間清掃を徹底し、定期的に歯科医院でクリーニングとチェックを受けることが重要です。喫煙を続けている場合でも、プラークの早期除去や炎症のコントロールを徹底することで、インプラントの寿命を延ばすことが可能です。術後の経過観察に加え、喫煙状況や生活習慣も含めた全人的なアプローチが求められるため、治療後も継続的に歯科医と連携をとることが推奨されます。
加熱式・電子タバコなら大丈夫?よくある誤解と真実

・加熱式タバコもリスクゼロではない理由
加熱式タバコや電子タバコは、「紙巻きたばこよりも健康被害が少ない」といったイメージから、インプラント治療への影響も軽いと誤解されることがあります。しかし実際には、加熱式タバコにもニコチンが含まれており、血管収縮作用や免疫機能の低下といった「インプラント治療に不利な作用」は残っています。紙巻きタバコと比較して有害物質の種類や量が異なるだけで、インプラント治癒にとって安全というわけではありません。「インプラント 喫煙 影響」という観点では、加熱式タバコも注意が必要な要因のひとつであり、完全な禁煙と同等の効果を得られるわけではないことを理解しておく必要があります。
・「禁煙できない」人のための現実的アドバイス
「禁煙した方がいいのは分かっているけれど、やめられない」という方も多くいらっしゃいます。とくに長年の習慣となっている場合、禁煙は容易ではなく、強いストレスや不安を伴うこともあります。そんな方には、まず「減煙」や「手術前後の短期的な禁煙」から取り組むことが現実的な対策です。完全な禁煙が難しくても、インプラント埋入前後の重要な期間だけでもニコチンの摂取を控えることで、治癒や感染リスクを軽減できる可能性があります。さらに、歯科医や医科と連携した医師による禁煙をサポートする専門の外来の利用や、ニコチンパッチなどの代替療法を活用することも有効です。「できない」ではなく、「できる範囲で工夫する」ことが治療成功への第一歩となります。
・どこまで対策すれば成功に近づけるのか?
インプラント治療において、喫煙の影響を完全に排除するのは困難かもしれませんが、リスクを最小限に抑えることは可能です。治療前のカウンセリングで喫煙習慣を正直に伝え、術前・術後の一定期間だけでも禁煙することで、血流改善や免疫機能の回復が期待できます。さらに、術後の適切なセルフケアと定期的なメンテナンスを徹底することで、喫煙者であっても良好な治療結果を得ることは可能な場合もあります。どこまで対策するべきか迷ったときは、「無理のない範囲でリスクをコントロールし、医師と連携して進めること」が大切な考え方です。一人で抱え込まず、専門家の支援を受けながら取り組むことで、インプラント治療の成功に近づくことができます。
医院選びのポイント|喫煙者への理解と対応力

・喫煙の影響を熟知した医師と話すべき理由
インプラント治療においては、喫煙が成功率や治癒過程に与える影響を正確に理解し、その上で患者の背景に応じた判断をしてくれる歯科医師との出会いがとても重要です。「インプラント 喫煙 影響」という観点で信頼できるのは、喫煙によるリスクを単に否定的に捉えるのではなく、科学的根拠をもとに適切な対策を講じてくれる医師です。
たとえば、術前の喫煙歴の確認や生活習慣のヒアリングを丁寧に行ったうえで、どの程度の禁煙が治療成功につながるか、患者一人ひとりの状態に応じて説明できる歯科医師は、安心して任せられる医師の目安になります。また、喫煙を完全にやめられない状況であっても、術後のメンテナンスや感染予防の工夫、リスクを最小限に抑えるケアプランを提案できる医院であれば、喫煙者も安心して治療を受けることができます。重要なのは、喫煙というリスク要因を正しく評価し、可能性を閉ざさずにサポートしてくれる姿勢です。
・カウンセリングで聞いておきたい3つのこと
喫煙者がインプラント治療を前向きに受けるためには、初回のカウンセリングが非常に重要です。この時点で不安や疑問を整理し、納得したうえで治療に進むためには、以下の3点をぜひ確認しておくことをおすすめします。
まず1つ目は「喫煙によるインプラントの成功率への影響」について。医師が統計データや臨床経験をもとに説明してくれるかどうかは、信頼性を見極める一つの指標です。2つ目は「術前・術後の禁煙期間とその必要性」です。治療計画において禁煙の期間がどのように影響するかを明確に説明してもらうことで、自分に何が求められているのかを理解できます。そして3つ目は「禁煙が難しい場合の代替策やリスク軽減策の有無」です。代替案を提示してくれるかどうかで、その医院が喫煙者に対してどれだけ柔軟に対応してくれるかを判断できます。こうした質問に対して誠実に、かつ具体的に応えてくれる医師であれば、安心して治療を任せられるでしょう。
・医院の設備・治療方針が安心材料になる
喫煙者にとってインプラント治療を受ける際には、歯科医院の治療方針や設備体制も慎重に確認すべき要素です。たとえば、口腔内の状態や骨量の正確な診断が求められるため、歯科用CTや三次元画像解析が導入されている医院であれば、より安全で確実な治療計画が可能です。術中・術後の感染対策を徹底するために、クリーンなオペ室を完備しているか、滅菌体制が整っているかといった点も評価材料になります。
さらに、治療後のアフターケアまで視野に入れた医院であるかどうかも重要です。喫煙者はインプラント周囲炎のリスクが高いため、メンテナンス体制が充実していることは非常に大切です。定期検診の頻度や、必要に応じた専門的なクリーニング、歯周組織の管理に力を入れているかといった点に注目しましょう。また、「禁煙支援プログラム」や「生活習慣への助言」を組み込んでいる医院であれば、単に治療を提供するだけでなく、長期的に患者の健康を見据えたサポート体制が整っている証拠です。喫煙者の背景を理解し、患者に寄り添った治療を行う医院は、設備面・方針面でもその姿勢が表れています。
喫煙とインプラントに関するよくある質問(FAQ)

・喫煙歴が長いとインプラントは無理?
喫煙歴が長いからといって、必ずしもインプラント治療が不可能になるわけではありません。ただし、「インプラント 喫煙 影響」の観点では、喫煙年数が長い方ほど血管収縮や骨代謝の機能低下が進行している可能性があり、治癒力や骨の再生力が低下していることがあります。そのため、診断においてはより慎重な評価が必要です。重要なのは、喫煙歴だけで判断するのではなく、現在の全身状態・口腔内環境・生活習慣などを総合的に見て治療可能かどうかを判断することです。喫煙歴があっても、現在禁煙している方や、治療に向けた準備を積極的に行っている方は、治療に前向きに取り組めるケースが多くあります。自己判断せず、まずは歯科医師に相談することが大切です。
・喫煙していても骨造成はできる?
喫煙者でも骨造成は可能ですが、リスクや制約が伴う点には注意が必要です。骨造成とは、インプラントを支える骨の量が不足している場合に人工骨や自家骨などを用いて骨を増やす処置であり、術後の治癒力と血流が重要になります。ニコチンによる血流障害や免疫力の低下は、骨造成の成功率にも影響を及ぼすため、非喫煙者と比較すると治癒が遅れる、炎症が起こりやすいといった傾向があります。とはいえ、完全に治療ができないというわけではなく、術前からの禁煙や術後の感染管理、メンテナンスの徹底によって良好な結果を得られることも少なくありません。喫煙しているからといって可能性を否定せず、医師と連携しながら慎重に計画を立てることが成功への鍵です。
・手術後、また吸ってしまったらどうなる?
インプラント手術後の喫煙再開は、治癒の遅延やインプラント周囲炎のリスク増加につながります。手術直後はインプラント体が骨と結合する重要な期間であり、十分な血流と免疫反応が必要です。喫煙を再開すると、血管が収縮し、必要な酸素や栄養素の供給が妨げられることで、骨との結合が不完全になる可能性があります。また、創傷部の治癒が遅れ、細菌感染を引き起こしやすくなるため、インプラントが脱落するリスクもあります。もし術後にうっかり喫煙してしまった場合は、その事実を隠さずに医師へ正直に伝え、必要な処置やケアを受けることが大切です。完璧な禁煙が難しい場合も、再開を最小限に抑える努力が、治療の成功率を左右します。
インプラント治療を「前向きに考える」ためのヒント

・不安をすべて取り除くのではなく「把握」する
インプラント治療を検討する際、喫煙者の多くが「自分には無理なのでは」と強い不安を抱きがちです。しかし、こうした不安は完全に消そうとするよりも、まずは“正しく理解する”ことが大切です。「インプラント 喫煙 影響」に関する科学的な知識を知ることで、自分のリスクを客観的に捉え、治療に向けて現実的な準備ができるようになります。不安の正体が見えれば、いたずらに心配するよりも、具体的な行動につなげられるようになります。完璧を目指す必要はありません。大切なのは、自分の体の状態や生活習慣と向き合い、治療成功のために何ができるかを冷静に考える姿勢です。理解は不安を乗り越える第一歩です。
・「今からできること」が未来を変える第一歩
喫煙の習慣があると、「インプラント治療は無理かもしれない」と感じてしまうかもしれません。しかし、今この瞬間からできる小さな取り組みが、将来の治療結果に大きく影響します。たとえば、手術に向けた一時的な禁煙や、歯磨き・フロスなどの口腔清掃を徹底すること、食生活や睡眠といった生活習慣を見直すことも、すべてがインプラントの成功率を高める行動です。喫煙を完全にやめられなくても、少しでも本数を減らす努力や、禁煙に向けた準備を始めるだけでも意味があります。未来の自分を守るのは、今の自分の選択です。治療を成功させたいと願うその気持ちを、まずは身近な行動につなげていきましょう。
・喫煙の有無にかかわらず、まずは相談するという選択肢
喫煙を理由に、歯科医院への相談そのものをためらってしまう方も少なくありません。しかし、喫煙しているからといって治療の可能性が完全に閉ざされているわけではありません。喫煙歴があること、禁煙が難しいことは、医師にとって治療方針を考えるための重要な情報です。だからこそ、正直に伝えたうえで、喫煙者にも適したアプローチを提案できる歯科医師と出会うことが、治療成功の鍵になります。現在の習慣を責めたり否定されたりすることを恐れず、まずは一歩、専門家に相談すること。それが、インプラント治療を「現実的な選択肢」として前向きに捉えるきっかけとなります。相談することで、可能性は広がります。
まとめ|喫煙歴があっても、治療を諦める必要はありません

・「喫煙=治療不可能」ではないという事実
インプラント治療において、喫煙は確かにリスク因子の一つではありますが、「喫煙しているから絶対に治療できない」というわけではありません。喫煙者でも、治療前後の禁煙や口腔内の衛生管理、定期的なメンテナンスなどを徹底することで、インプラントの成功率を高められる可能性があります。むしろ、「喫煙者だから無理だ」と決めつけて何もしないことのほうが、将来の選択肢を狭めてしまいます。医学の進歩により、喫煙リスクを考慮した治療方針を立てられる歯科医院も増えており、過去の習慣だけで可能性を否定する必要はありません。大切なのは、リスクを理解した上で、自分の状態に合った対処法を見つけることです。
・リスクと対策を正しく理解することが成功への近道
治療の成功には、喫煙がインプラントに与える影響を正確に理解することが不可欠です。ニコチンが血流や免疫機能に与える作用、骨とインプラントの結合を阻害するメカニズムなどを知ることで、自分にとって必要な対策が見えてきます。また、禁煙が難しい方でも、術前後の短期的な禁煙や代替療法、生活習慣の改善によってリスクを軽減する方法があります。インプラントは「喫煙者はできない治療」ではなく、「リスクと向き合いながら成功に導く治療」です。不安や疑問を放置せず、正しい知識を持って主体的に治療に向き合うことが、良好な結果につながります。
・あなたの口腔状態を正しく評価できる専門医に相談を
喫煙歴がある方こそ、まずは信頼できる専門医に相談することが治療の第一歩です。喫煙状況、口腔衛生、全身疾患の有無などを丁寧にヒアリングし、必要な検査を行った上で、リスクと適応可否を判断できる歯科医師は、リスクを減らせる存在です。また、単に治療を行うだけでなく、術後のメンテナンスや禁煙支援、生活習慣のアドバイスまで含めてサポートしてくれる医院であれば、長期的な予後まで見据えた治療計画が可能です。「インプラント 喫煙 影響」に正しく向き合い、あなたの状態に最適な方法を一緒に考えてくれる医師との出会いが、信頼できる選択肢となるでしょう。自分だけで判断せず、専門家と共に進む道を選んでください。
埼玉県大宮の再治療0%を追求した
審美インプラント治療ガイド
監修:関口デンタルオフィス大宮
電話番号:048-652-1182
*監修者
関口デンタルオフィス大宮
*経歴
・2008年 日本大学歯学部卒業
日本大学歯学部臨床研修部入局
・2009年 日本大学歯学部補綴学第一講座入局
専修医
顎関節症科兼任
・2014年 同医局退局
関口デンタルオフィス開院
*所属学会
*スタディークラブ
・CIDアクティブメンバー(Center of Implant Dentistry)