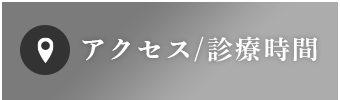歯を抜くしかないと諦める前に。ご自身の歯を残すための最後の砦「精密根管治療」
- 2025年8月15日
- 未分類
目次
見た目の変化に悩むあなたへ ― ブラックマージンの現実

・笑顔に影響する歯茎の黒ずみとは
ブラックマージンとは、被せ物(クラウン)と歯茎の境目が黒く見える状態を指し、特に金属を使用したメタルボンドクラウンや、過去に「歯 神経 除去」を行った歯で起こりやすい現象です。歯茎が加齢や歯周病によって下がると、金属部分や歯の変色した根が露出し、黒ずんだ線のように見えることがあります。これは口元の印象を大きく損ね、特に笑顔のときに目立ちやすいため、審美的なコンプレックスとなります。健康被害が直ちに出ない場合もありますが、見た目に影響を与えるだけでなく、被せ物や歯肉の状態が悪化しているサインである可能性もあります。近年では、金属を使用しないオールセラミッククラウンやジルコニアクラウンが普及しており、こうした黒ずみを予防・改善する方法が選べるようになっています。
・人前で気になる瞬間と心理的負担
ブラックマージンは、特に会話中や笑顔になったときなど、口元が自然に開く場面で他人から見えやすくなります。接客業や営業職、プレゼンテーションなど、人と接する機会が多い方にとっては、強い心理的ストレスになることがあります。また、写真撮影やビデオ会議、食事の際など、相手との距離が近いシーンでは口元を意識しすぎてしまい、自然な笑顔や会話が減ってしまうこともあります。こうした心理的負担は、長期的には自己評価の低下や社交性の減退につながりかねません。特に、口元は第一印象を左右する重要な要素であり、ブラックマージンによって「老けた印象」や「不健康な印象」を与えてしまうこともあります。そのため、見た目だけの問題と思わず、早期の改善を検討することが大切です。
・放置することで起こり得る見た目以外の影響
ブラックマージンは単なる審美的な問題と思われがちですが、その裏には健康面のリスクが潜んでいます。まず、原因が歯肉退縮や補綴物(被せ物)の適合不良である場合、その隙間からプラーク(歯垢)が溜まりやすくなります。これにより、歯周病や二次むし歯(被せ物の下で再び発生する虫歯)のリスクが高まります。また、「歯 神経 除去」を行った歯は感覚が鈍くなっており、痛みなどの異変を感じにくいため、症状が進行しても気づかないケースがあります。さらに、金属を使用したクラウンの場合、唾液中で金属イオンが溶け出し、歯茎に色素沈着を起こして黒ずみを悪化させることがあります。これらの要因は放置すればするほど改善が難しくなり、最終的には被せ物のやり直しや歯周治療が必要になる場合もあります。見た目と健康の両面から、早めの歯科受診と適切な対応が望まれます。
ブラックマージンの基礎知識

・発生のメカニズムと「根管治療(歯の神経を取る処置)」との関係
ブラックマージンは、被せ物と歯茎の境目が黒く見える状態で、特に金属を含む補綴物を使用している場合に発生しやすくなります。その主な原因は、歯茎の退縮や被せ物の適合不良により金属部分が露出することです。また「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行った歯は、血流がなくなるため時間とともに歯質が変色しやすく、その変色が補綴物の縁や歯茎から透けて見えることがあります。さらに、神経を失った歯は変色や脆くなる傾向があり、その結果として補綴物や歯茎に負担がかかる場合があります。こうしたメカニズムを理解することで、単なる見た目の問題だけでなく、歯や歯茎の健康状態にも関係していることが分かります。
・金属による影響とセラミック素材の違い
ブラックマージンの大きな要因の一つが金属の使用です。金属を使用したクラウン(メタルボンドなど)では、歯茎が下がると金属の縁が露出しやすく、さらに唾液中で金属イオンが溶け出して歯茎に色素沈着を起こす「メタルタトゥー」が発生することがあります。一方、オールセラミックやジルコニアなど金属を含まない素材では、こうした黒ずみのリスクが大幅に低減します。また、セラミックは光の透過性が高く、天然歯に近い透明感と色調を再現できるため、審美性の面でも優れています。特に前歯部では、金属レス素材を選択することで長期的な美しさと健康的な歯茎の色を維持しやすくなります。
・黒ずみが進行しやすいケースとそうでないケース
ブラックマージンが進行しやすいケースには、歯周病や加齢による歯肉退縮、過去に「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行っている場合、また金属を使用した補綴物を装着している場合が含まれます。特に神経を失った歯は歯質の変色が進みやすく、歯茎のライン変化によって黒ずみが目立つことがあります。一方、歯周組織が健康で、金属を使用しないオールセラミックを選択している場合は、進行リスクが低く抑えられます。ただし、素材だけでなく日常のケアや定期的な歯科メンテナンスも重要です。適切なブラッシング、歯周病予防、補綴物の適合チェックを継続することで、ブラックマージンの進行を防ぐことが可能です。
原因を深掘り ― 歯と歯茎の関係性

・補綴物の適合と歯茎の健康状態
ブラックマージンの発生には、補綴物(被せ物)の適合精度が大きく影響します。適合が不十分だと、境目に段差や隙間が生じ、プラーク(歯垢)が溜まりやすくなります。これが慢性的な歯肉炎や歯周病を引き起こし、歯茎が下がる原因となります。さらに、補綴物のマージン(縁)が歯茎に強く当たる状態や、歯茎のラインに合っていない場合も炎症を誘発しやすく、結果として金属や変色した歯質が露出してしまいます。適切な適合を得るには、精密な型取りや噛み合わせの調整、歯周組織への配慮が必要です。特に長期的な美しさを保つためには、素材選びだけでなく補綴物の設計精度と歯茎の健康管理が欠かせません。
・歯肉退縮とブラックマージンの関係
歯肉退縮は、ブラックマージンを目立たせる主要な要因です。歯茎が下がると、補綴物の縁や金属部分が露出しやすくなります。原因としては、加齢による自然な退縮、歯周病、強すぎるブラッシング、噛み合わせによる負担などが挙げられます。また、「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行った歯は、神経のない状態で硬さや色調が変化しやすく、さらに歯周組織への栄養供給が減少することで歯肉退縮が進む場合があります。進行を防ぐには、歯周病予防のための定期検診や、正しいブラッシング圧の習得が重要です。歯茎の厚みや形態に配慮した補綴設計も、見た目の変化を最小限に抑える助けとなります。
・根管治療後に起こりやすい見た目の変化
根管治療は、重度の虫歯や感染で「根管治療(歯の神経を取る処置)」が必要になった際に行われますが、その後の歯は血流を失い、時間とともに色が暗く変色しやすくなります。この変色が補綴物の縁や歯茎から透けて見えると、ブラックマージンが強調される原因になります。また、神経を失った歯は脆くなり、噛み合わせや補綴物からの負荷によって歯肉退縮が進む可能性もあります。審美性を維持するためには、変色を抑える素材選びや、必要に応じて歯の内部漂白(ウォーキングブリーチ)を行った上で補綴する方法が有効です。根管治療後は見た目の管理も重要であり、治療計画時から長期的な審美性を考慮することが求められます。
改善のための治療選択肢

・セラミックによるやり直し治療の流れ
ブラックマージンの改善には、既存の補綴物を除去し、新たに適合精度の高いセラミッククラウンやラミネートベニアを装着する方法が有効です。治療の流れとしては、まず既存の被せ物を丁寧に除去し、支台歯の状態や歯茎の健康を確認します。虫歯や歯質の劣化が見られる場合は、その処置を先に行います。特に「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行った歯では変色や脆弱化が進んでいるため、土台強化のためのファイバーコアなどを併用することがあります。型取りはシリコン印象材など精密度の高い方法で行い、歯茎のラインや隣接歯との調和を考慮して設計します。最終的に装着されるセラミックは、金属を含まないオールセラミックやジルコニアを選択することで、長期的な審美性と歯茎の自然な色調を維持しやすくなります。
・歯茎のラインを整える外科的アプローチ
ブラックマージンが歯肉退縮によって生じている場合、歯茎のラインを整える外科的処置が有効です。歯肉移植術(CTG)や歯冠長延長術(クラウンレングスニング)などが代表的な方法で、歯茎の形態を回復させることで、補綴物の縁が自然に隠れるようになります。特にセラミックのやり直しと併用することで、審美性の向上が期待できます。外科的処置では、歯周組織の治癒期間を考慮し、補綴物の装着までに数週間〜数か月を要する場合があります。また、術後は歯周組織の安定を保つため、正しいブラッシング方法や定期的なメンテナンスが欠かせません。外科的アプローチは、単なる見た目の改善にとどまらず、歯周組織の健康維持にもつながります。
・歯の保存と見た目改善を両立する方法
審美性の改善を目指す際、できるだけ天然歯を削らずに保存することも重要です。例えば、「根管治療(歯の神経を取る処置)」を避けるために、歯質の残存量が多い場合はラミネートベニアや部分的なセラミック修復(インレー・アンレー)を選択する方法があります。また、歯肉退縮や変色が軽度であれば、補綴物の全交換ではなく、内部漂白や補綴物の縁だけを修正する部分的なやり直しも可能です。こうした方法は、歯への侵襲を最小限に抑えながら、ブラックマージンの見た目を改善できます。治療法の選択は、歯の健康状態、噛み合わせ、歯周組織の条件を総合的に判断して行われるため、歯科医師との十分な相談が欠かせません。
医院選びと事前準備のポイント

・精密診断とシミュレーションの重要性
ブラックマージンの改善や審美治療の成功には、事前の精密診断が欠かせません。口腔内スキャナーや高解像度のレントゲン、CT撮影を用いることで、歯茎の厚みや骨の状態、補綴物の適合度を詳細に把握できます。特に「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行った歯では、歯質の強度や変色リスクも考慮する必要があります。また、治療後の見た目を事前にイメージできるシミュレーションは、患者様の希望と歯科医師の計画を一致させるために有効です。写真やデジタルモックアップを用いることで、仕上がりの形や色調を具体的に確認でき、治療方針のミスマッチを防ぎます。精密な診断と可視化されたシミュレーションは、安心して治療を進めるための土台となります。
・素材選びで失敗しないための基準
治療結果の美しさと長期的な安定性を左右する大きな要因が、補綴物の素材選びです。オールセラミックやジルコニアは金属を使用しないため、歯茎との境目が黒ずみにくく、自然な透明感を再現できます。一方、金属を含むメタルボンドは強度に優れるものの、経年的な歯茎退縮でブラックマージンが現れやすくなります。素材選びでは、見た目の美しさだけでなく、噛み合わせの強さや歯茎の健康状態、予算も考慮が必要です。また、「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行った歯は変色リスクが高いため、遮蔽力のある素材を選ぶことで、長期的に安定した色調を維持できます。信頼できる歯科医師と相談し、症例に合った素材を選ぶことが重要です。
・治療前に確認すべき費用・期間・通院回数
審美治療は保険適用外となることが多く、費用は医院や素材、治療方法によって大きく異なります。事前に見積もりを提示してもらい、追加費用の有無や保証内容も確認しておきましょう。また、治療期間は歯茎や歯周組織の状態、外科的処置の有無によって変わります。セラミックのやり直しのみであれば数週間〜1か月程度ですが、歯茎の外科処置を伴う場合は数か月かかることもあります。通院回数も事前に把握し、スケジュールに無理がないか確認することが大切です。「根管治療(歯の神経を取る処置)」が必要な場合は、根管治療に数回通院が追加される可能性もあります。これらを明確にしておくことで、計画的かつ安心して治療に臨むことができます。
よくある疑問とその答え

・ブラックマージンは削らずに改善できる?
ブラックマージンの原因が補綴物と歯茎の境目の金属露出であれば、削らずに改善できるケースは限られます。例えば、歯茎の軽度な退縮や変色であれば、歯茎の色を補正するコンポジットレジンでの充填や、歯茎の着色をレーザーで除去する方法が検討されることがあります。ただし、これらは根本的な解決にはならず、時間の経過とともに再度黒ずみが目立つ可能性があります。審美性を長期的に保つためには、金属を含まないオールセラミックやジルコニアなどへの補綴物の置き換えが効果的です。また、「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行った歯では、内部の変色も影響するため、補綴物のやり直しと併せて内部漂白や遮蔽性の高い素材選びが必要になることがあります。
・治療後に再発する可能性は?
ブラックマージンは、一度改善しても将来的に再発する可能性があります。その主な要因は、加齢や歯周病などによる歯肉退縮、噛み合わせの変化、または補綴物の劣化です。特に金属を使用している場合、歯茎が下がると金属の縁が露出しやすくなります。「根管治療(歯の神経を取る処置)」をした歯は脆くなりやすく、補綴物の適合が時間とともに変化することもあり、結果として再び境目が目立つことがあります。再発リスクを最小限にするためには、治療時に歯茎の厚みや形態を整え、金属を使わない素材を選択することが有効です。さらに、定期的なメンテナンスと歯周組織の健康管理が、見た目の美しさを長期的に維持する鍵となります。
・保険適用での改善は可能か?
ブラックマージンの改善は、多くの場合保険適用外となります。保険診療では、機能回復を目的とした最低限の材料や方法が採用されるため、金属を含むクラウンやブリッジが主流で、審美性を重視したオールセラミックやジルコニアは適用外です。ただし、前歯など審美性が特に求められる部位で、かつ一定の条件を満たす場合には、硬質レジン前装冠などの保険診療で対応できることもあります。しかし、この場合でも長期的な変色や摩耗、ブラックマージンの再発リスクは高くなります。見た目と耐久性の両立を望む場合は、自費診療での治療を検討することが望ましく、特に「根管治療(歯の神経を取る処置)」後の色調安定や透明感再現には、自費での高品質素材の選択が推奨されます。
治療後の見た目と機能を守るために

・定期検診とメンテナンスのスケジュール
ブラックマージンの再発や補綴物の劣化を防ぎ、治療後の美しい見た目と噛む機能を長く維持するためには、定期的な歯科検診が欠かせません。特に「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行った歯は神経がないため痛みやしみる感覚が失われ、異常があっても自覚しにくい傾向があります。こうした歯では小さな不具合が進行してから発見されるケースも少なくありません。そのため、治療後は一般的に3〜6か月ごとの定期検診が推奨されます。
検診では、歯茎の健康状態や補綴物と歯の境目の適合、咬み合わせの変化などを詳細にチェックします。特にブラックマージンは歯茎の位置変化によって再発する可能性があるため、歯周組織の状態を早期に把握することが重要です。また、歯石除去やポリッシングによる着色汚れの除去、咬み合わせの微調整など、日常のセルフケアだけでは補えない部分も定期的にメンテナンスしていくことが、長期的な審美性と機能維持につながります。
・歯茎に優しい日常ケアのコツ
治療後の歯茎を健康に保つためには、日々の正しいブラッシングと歯間清掃が非常に重要です。間違ったケア方法、例えば硬すぎる歯ブラシの使用や強い力でのブラッシングは、歯肉退縮を招きブラックマージンを再び目立たせる原因となります。適切なのは、やわらかめの歯ブラシを使用し、毛先を歯と歯茎の境目に45度の角度で当てて優しく小刻みに磨く方法です。
さらに、デンタルフロスや歯間ブラシを使い、補綴物の周囲や歯と歯の間に残ったプラークを除去することも欠かせません。特に「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行った歯は、歯茎の炎症や骨の吸収に対して感覚が鈍くなるため、異変を感じた時にはすでに症状が進んでいる場合があります。出血や腫れ、色の変化に気づいた際は、自己判断せずに早めに歯科医院を受診することが大切です。
・食生活・生活習慣が与える影響
食生活や生活習慣も、治療後の見た目や機能の維持に大きく関わっています。砂糖を多く含むお菓子や清涼飲料水、また酸性度の高い柑橘類や炭酸飲料を頻繁に摂取すると、補綴物周囲のプラークが増加し、歯茎の炎症や着色の原因となります。特に金属を含む補綴物では、酸性環境が長く続くことで金属成分の溶出や変色のリスクが高まります。
さらに、喫煙は歯茎の血流を悪化させて歯肉退縮を促進し、補綴物と歯茎の境目が目立ちやすくなります。また、歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合、補綴物や歯根に過度な力が加わり、摩耗や亀裂の原因となるだけでなく、「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行った歯の寿命を縮める可能性があります。
これらを防ぐためには、バランスの取れた食事を心がけ、喫煙習慣がある場合は禁煙を検討することが望ましいでしょう。また、就寝時にはマウスピース(ナイトガード)を装着することで、無意識下の歯ぎしりによる負担を軽減できます。日常生活でのこうした配慮が、美しい口元を長期的に守る大きな鍵となります。
自分でできる予防アプローチ

・補綴物周囲のプラークコントロール方法
補綴物(クラウンやブリッジなど)の周囲は、天然歯に比べて形態が複雑でプラーク(歯垢)が付着しやすく、除去が難しい部位です。特に「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行った歯は感覚が鈍くなり、違和感やしみる感覚がなくなるため、汚れが蓄積しても自覚しにくい傾向があります。その結果、歯茎の炎症やブラックマージンの進行、二次虫歯のリスクが高まります。
効果的な予防のためには、歯ブラシだけでなくデンタルフロスや歯間ブラシなどの補助清掃用具を併用することが欠かせません。歯間ブラシは補綴物と歯茎の間に軽く挿入し、前後に小さく動かして汚れを落とします。サイズや硬さが合っていないと歯茎を傷つける恐れがあるため、歯科医師や歯科衛生士の指導のもと選ぶことが大切です。さらに、殺菌作用のある洗口液を補助的に用いることで、細菌の増殖を抑制し、口腔内環境を安定させることができます。
このような日々のプラークコントロールは、補綴物の寿命を延ばし、治療後の見た目や歯茎の健康を長期間維持するための基盤となります。
・歯茎の健康を守るブラッシング習慣
歯茎の健康維持には、力まかせの磨き方ではなく、歯肉に優しい正しいブラッシング方法が不可欠です。特に補綴物と歯茎の境目や歯肉溝は汚れがたまりやすいため、毛先を歯と歯茎の境目に45度の角度で当てて小刻みに動かす「バス法」が効果的です。強く磨きすぎると歯肉退縮を招き、ブラックマージンがさらに目立つ原因となります。
「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行った歯は知覚過敏が起こりにくくなりますが、痛みがないために力を入れすぎてしまう人も少なくありません。これはかえって歯茎のダメージや歯の摩耗を引き起こすため、力加減には十分注意しましょう。
また、電動歯ブラシを使う場合は振動や回転の力で十分に汚れを落とせるため、過度な押し付けは不要です。1日2回以上、特に就寝前は丁寧に磨く習慣をつけることで、歯茎の健康と補綴物の美しさを長く保てます。
・金属を使わない治療法を選ぶメリット
補綴物に金属を使用すると、金属の成分が歯茎に沈着して黒く見える現象(メタルタトゥー)やブラックマージンが目立ちやすくなります。これに対し、ジルコニアやオールセラミックなどのメタルフリー素材は、天然歯に近い色調や透明感を再現でき、長期的に審美性を維持しやすいという利点があります。
さらに、金属アレルギーのリスクがなく、生体親和性が高いため、歯茎の炎症や変色が起こりにくい点も魅力です。特に「根管治療(歯の神経を取る処置)」を行った歯は、歯質がもろくなりやすく、補綴物の適合精度がそのまま耐久性や見た目に直結します。精密に作製されたメタルフリー補綴物を選べば、機能性と審美性の両方を高いレベルで維持することが可能です。
また、金属を使用しないことで光の透過性が向上し、隣接歯との色の調和も自然になります。見た目の改善と同時に、長期的な歯茎の健康維持にもつながるため、審美面と予防面の両方からメリットの大きい選択肢と言えるでしょう。
まとめ

・笑顔の印象が変わる心理的効果
ブラックマージンや補綴物の変色が改善されると、笑顔の印象は大きく変わります。特に前歯は会話や表情の中で目立つため、色や形が自然になることで清潔感や若々しさが感じられやすくなります。根管治療(歯の神経を取る処置)を行った歯でも、適切な色調や形態の補綴物を装着すれば、周囲の歯と自然に調和し、見た目の違和感を軽減できます。
見た目の改善は単なる審美的効果にとどまらず、心理的な自信にもつながります。笑顔や会話に積極的になり、人前での振る舞いにも良い影響を与えることが多く報告されています。また、自信を持って口を開けられることで、仕事やプライベートにおけるコミュニケーションも円滑になり、生活全体の質が向上する可能性があります。
・長期的な口腔健康へのメリット
ブラックマージン改善や精密な補綴治療は、見た目だけでなく歯や歯茎の健康維持にも大きな役割を果たします。補綴物の適合性が高まれば、歯と補綴物の間に汚れが入り込みにくくなり、二次虫歯や歯周病のリスクが低減します。根管治療(歯の神経を取る処置)を行った歯は脆くなりやすいため、適切な形態と咬合調整で保護することが重要です。
また、歯茎に適切な圧力がかかることで血流が保たれ、歯周組織の健康も維持されます。定期的なメンテナンスと併せて治療を行えば、長期的に安定した口腔環境を保ちやすくなります。これは単なる見た目の改善にとどまらず、口腔機能の維持や全身の健康にもつながる重要なポイントです。
・将来の再治療リスク低減
精密な補綴治療や審美的改善を行うことで、将来的な再治療の可能性を大幅に減らせます。例えば、適合精度の低い被せ物は隙間から細菌が侵入し、二次虫歯や歯周病を引き起こす原因となりますが、適切な治療によりこのリスクは最小限に抑えられます。
特に根管治療(歯の神経を取る処置)を行った歯は、内部の防御機能が低下しているため、破折や感染が再発しやすい状態です。高精度な補綴物でしっかり保護すれば、咬合力による負担を分散し、歯の寿命を延ばすことができます。さらに、適切な素材選び(ジルコニアやセラミックなど)により、経年的な劣化や変色の影響を受けにくく、長期的な安定性を確保できます。これにより、治療のやり直しや抜歯のリスクを減らし、結果的に時間的・経済的負担の軽減にもつながります。
専門医への相談で安心を手に入れる

・初診カウンセリングで伝えるべき情報
初診時のカウンセリングでは、症状や見た目の悩みだけでなく、治療の経緯や既往歴、アレルギー、生活習慣なども正確に伝えることが重要です。特に、過去に根管治療(歯の神経を取る処置)を受けた歯の状態や、その後の不調の有無は治療方針に直結します。また、現在服用している薬や持病の有無も共有することで、安全性の高い治療計画が立てられます。
さらに、「どのような見た目にしたいか」「治療期間や費用の希望」「通院頻度の制限」など、生活や希望に関わる条件も事前に明確にしておくと良いでしょう。
・治療計画の理解と納得の重要性
治療は、患者と歯科医師の相互理解があってこそ成功します。治療計画の説明では、使用する材料の特徴、治療ステップ、予想される経過、メリット・デメリットなどをしっかり確認しましょう。特に、根管治療(歯の神経を取る処置)を行った歯の補綴治療では、強度や耐久性を考慮した設計が不可欠です。
疑問点や不安があれば、その場で質問し、理解したうえで同意することが大切です。説明を受けた際には、専門用語だけでなく日常的な言葉で理解できるまで説明してもらいましょう。納得感のある治療計画は、安心感を高めるだけでなく、治療後の満足度にも直結します。
・信頼できる歯科医師との長期的なパートナーシップ
治療後の健康維持には、信頼できる歯科医師との継続的な関係が欠かせません。補綴物や歯茎の状態は年月とともに変化するため、定期的な検診やメンテナンスを受けることで、早期のトラブル発見・対応が可能になります。
根管治療(歯の神経を取る処置)を行った歯は特に脆くなりやすいため、咬合や補綴物の適合を長期的に見守る必要があります。信頼できる歯科医師は、患者の生活背景やこれまでの治療履歴を把握しており、必要に応じて柔軟に対応できます。このようなパートナーシップを築くことで、口腔の健康と見た目の美しさを長期的に守ることが可能になります。
再治療0%を追求した歯科治療専門クリニック
埼玉県さいたま市の歯医者・歯科
監修:関口デンタルオフィス大宮
電話番号:048-652-1182
*監修者
関口デンタルオフィス大宮
*経歴
・2008年 日本大学歯学部卒業
日本大学歯学部臨床研修部入局
・2009年 日本大学歯学部補綴学第一講座入局
専修医
顎関節症科兼任
・2014年 同医局退局
関口デンタルオフィス開院
*所属学会
*スタディークラブ
・CIDアクティブメンバー(Center of Implant Dentistry)