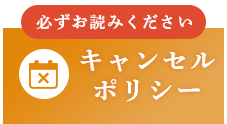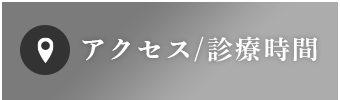セラミックで前歯のすきっ歯改善Q&A|治療期間・耐久性・メンテナンスの疑問
- 2025年5月22日
- 審美歯科
目次
セラミックで前歯のすきっ歯は本当に改善できる?

セラミック治療の仕組みと適応範囲
セラミック治療は、審美性と機能性を兼ね備えた補綴処置として、前歯のすきっ歯改善に非常に有効な方法です。人工歯を使用して歯の形態や大きさを調整することで、隙間を自然に埋めることができます。特に、ラミネートベニアやセラミッククラウンといった方法では、既存の歯の表面に高精度のセラミック素材を貼り付けたり、被せたりすることで、隙間を閉じると同時に形や色調も美しく整えることが可能です。すきっ歯の幅や本数、噛み合わせの状況によって最適な治療法は異なりますが、軽度から中等度のすきっ歯であれば、セラミックによって短期間で高い審美的改善が期待できます。また、セラミックは変色しにくく、天然歯に近い透明感を持つため、見た目にこだわる方にも適した選択肢です。
すきっ歯の原因に応じた治療の選択肢
すきっ歯の原因は多岐にわたります。たとえば、歯のサイズが小さい、歯と顎のバランスが合っていない、舌の癖(舌突出癖)、歯周病による歯の移動などが挙げられます。それぞれの原因に対して最適なアプローチを取ることが、治療の成功と長期的な安定に直結します。セラミック治療は、主に歯のサイズや形態に起因するすきっ歯に適しています。対して、歯列全体のバランスや顎の骨格の問題が関係している場合は、矯正治療が必要になることもあります。歯周病によって歯が動いて隙間ができている場合には、まず歯周治療で歯ぐきの健康を取り戻すことが先決です。見た目だけでなく、原因を正しく診断し、再発を防ぐ視点から治療法を選ぶことが重要です。
ラミネートベニア・クラウンの違いと選び方
セラミックによるすきっ歯改善では、ラミネートベニアとクラウンの2つが主な選択肢となります。ラミネートベニアは、歯の表面を0.3~0.7mm程度だけ削り、薄いセラミックシェルを貼り付ける方法です。歯の削除量が少なく、神経を残せることから、低侵襲かつ自然な見た目を実現できます。一方、セラミッククラウンは、歯全体を削ってセラミック製の被せ物を装着する方法で、すき間が大きいケースや、歯の向き・色・形の修正が必要な場合に適しています。どちらが適しているかは、すきっ歯の幅、歯の状態、患者様の審美的要求によって異なります。カウンセリング時にシミュレーションを通じて確認し、自分にとって負担が少なく、かつ満足度の高い選択肢を選ぶことがポイントです。
治療はどれくらいの期間で終わる?

初診〜最終装着までのスケジュール例
セラミックによる前歯のすきっ歯治療は、症例にもよりますが、初診から最終装着まで約2〜4週間程度で完了することが一般的です。まず、初診ではカウンセリングと精密な診査・診断を行い、治療方針を確定します。その後、治療が決定すれば必要に応じて仮歯を作製し、歯の形成と型取り(印象採得)を行います。セラミックの補綴物(被せ物やベニア)は、通常1〜2週間ほどで技工所から仕上がってきますので、その後に最終的な装着となります。審美性や噛み合わせにこだわる場合は微調整が必要なケースもあり、その際は装着までさらに1回程度の通院が追加されることもあります。大きな手術や矯正治療とは異なり、比較的短期間かつ少ない回数で理想的な見た目を実現できるのが、セラミック治療の大きな魅力です。
仮歯の有無と日常生活への影響
前歯のセラミック治療では、歯を削った当日から装着までの期間、仮歯(テンポラリークラウンや仮ベニア)を使用するのが一般的です。仮歯の目的は、見た目を保つだけでなく、歯の移動や咬み合わせの乱れを防ぎ、歯の神経を保護する役割も果たします。近年は仮歯も審美性が高く、周囲に治療中であることが気付かれにくいレベルに仕上げられるケースがほとんどです。ただし、セラミックほどの強度はないため、硬い食べ物や粘着質のあるもの(キャラメル・ガムなど)は避ける必要があります。また、仮歯はあくまでも一時的なものなので、丁寧にケアすることが求められます。治療中でも仕事や外出、会話など日常生活に支障が出ないよう、見た目と機能を両立した仮歯を準備することで、快適な治療期間を過ごせます。
矯正との比較で見る期間の差
すきっ歯の改善方法として、矯正治療とセラミック治療はしばしば比較されます。矯正治療は歯を動かして隙間を閉じる根本的なアプローチであり、歯を削らずに済むというメリットがある一方で、治療期間は6ヶ月〜2年程度と長期に及ぶのが一般的です。また、見た目や発音への影響、通院頻度も高くなる傾向があります。一方、セラミック治療は歯の形を整えることで隙間を埋めるため、数週間という短期間で審美的な改善が可能です。ただし、歯を削る処置が伴う点は慎重に判断すべきポイントとなります。すきっ歯の原因や幅、患者様のご希望に応じて、治療法の選択が変わります。長期的な咬合の安定や歯の保存を重視するか、見た目を優先して早く仕上げたいかによって、ベストな選択肢は異なるため、専門的なカウンセリングが重要です。
セラミックの耐久性は?どのくらいもつの?

材質ごとの耐用年数と保証の目安
セラミック治療に使用される素材には、主に「ジルコニア」「e.max(イーマックス)」「メタルボンド」などがあり、それぞれに特徴と耐久性があります。一般的に、ジルコニアは10〜15年以上の高い耐久性を誇り、奥歯にも使用できる強度を持っています。一方、e.maxは見た目が非常に自然で前歯に適しており、5〜10年の使用に耐えうる素材とされています。メタルボンドは金属を芯にしているため強度に優れていますが、長期使用で歯ぐきとの境目に黒ずみが出ることもあります。クリニックによっては、セラミック補綴物に5〜10年の保証を付けているところもあり、破損や脱落があった場合の再治療が含まれるケースもあります。耐用年数は使用状況やメンテナンス次第で大きく変わるため、適切なケアと定期的な検診が長持ちの鍵となります。
欠け・割れを防ぐ生活上のポイント
セラミックは天然歯に近い強度と美しさを兼ね備えていますが、「陶材」であることから、過度な力が加わると欠けや割れを起こすことがあります。そのため、セラミックを長く使うためには、咬む力を分散させる生活習慣が重要です。例えば、硬いもの(氷・煎餅・ピスタチオの殻など)を前歯で噛まない、爪を噛む癖やペンを咥える癖がある方は意識的にやめるようにしましょう。また、歯ぎしりや食いしばりの癖がある方には、就寝時にナイトガード(マウスピース)の使用が推奨されます。歯ぎしりは無意識下で強い力が加わるため、セラミック破損の大きな要因になります。普段の生活の中で少し意識を変えるだけでも、セラミックの寿命は大きく延びます。せっかくの治療を長く快適に保つために、使用者自身の協力が欠かせません。
定期的な調整で寿命を延ばすコツ
どれほど精密に作られたセラミックでも、長年の使用によってわずかなズレや摩耗が生じてきます。これを放置すると、かみ合わせのバランスが崩れたり、他の歯に負担がかかったりして、セラミックの破損リスクが高まります。そのため、装着後も定期的なチェックとメンテナンスが重要です。具体的には、半年に1回のペースでの定期検診を推奨しています。検診では、接着状態や歯周組織の確認、咬合調整、小さな欠けの早期発見が可能です。また、セラミック周囲にプラークが蓄積すると、二次虫歯や歯周炎の原因にもなります。定期的なクリーニングにより、衛生面と機能面の両方を良好に保つことができ、結果としてセラミックの長期使用につながります。日々のセルフケアに加え、プロのケアを定期的に受けることが最善の予防策です。
自分の歯をどれくらい削るの?

ラミネートベニアとクラウンで異なる削除量
セラミック治療において、歯をどれくらい削るのかは患者様にとって最も気になるポイントのひとつです。中でも、ラミネートベニアとセラミッククラウンでは削除量が大きく異なります。
ラミネートベニアは歯の表面をわずか0.3〜0.7mm程度だけ削り、その上に薄いセラミックシェルを貼り付ける治療法です。歯の神経や内部構造には触れずに処置できるため、低侵襲(なるべく削らない)な選択肢として前歯のすきっ歯改善にも人気があります。一方で、歯の傾きや隙間の幅が大きい場合には、ベニアだけでの対応が難しいこともあります。
セラミッククラウンの場合は、歯全体を1〜1.5mmほど削って全周を覆う構造のため、補綴物としての安定性は高まりますが、削除量はやや多くなります。治療法の選択は、「削る量」だけでなく、審美性・咬合状態・歯の健康状態などを踏まえて、歯科医師と相談しながら決めることが大切です。
歯の健康と削ることのリスク
歯は一度削ってしまうと元には戻せないため、削ることには慎重であるべき理由があります。
特に天然歯のエナメル質は非常に硬く、外部刺激から歯を守る役割を担っています。これを削ると、象牙質が露出しやすくなり、刺激に敏感になったり、虫歯のリスクが高まったりする可能性があります。また、削る量が多すぎると、神経(歯髄)に近づきすぎて痛みが出ることがあり、神経を取る処置(抜髄)が必要になるリスクもゼロではありません。
一方で、最新のセラミック治療では、なるべく歯を削らずに済むよう、最小限の形成で最大限の審美性と機能性を得られる設計が可能になっています。歯を削る際には、表面麻酔や電動麻酔などを活用して痛みを抑える配慮もされているため、過剰な心配は不要ですが、「必要最小限に削る」という原則は、どの治療でも重視されています。
「削らない治療」は可能なのか
最近では、「できるだけ歯を削らない治療」を希望される方も多く、そうしたニーズに応える選択肢も少しずつ増えてきています。たとえば、ダイレクトボンディング法と呼ばれる方法では、歯をほとんど削らず、コンポジットレジンという樹脂材料を直接盛り付けて、すきっ歯を目立たなくさせることが可能です。
しかし、これはあくまで小さなすきっ歯や軽度の歯並び不整に限定される方法であり、広範囲の審美改善や長期的な耐久性を求める場合には、セラミック治療が優位です。
ラミネートベニアでも、歯の状態によっては「無形成」あるいは「ごく浅く削るだけ」で対応可能なケースもあり、完全に“削らない”わけではなくとも、削る量を最小限にとどめた治療が現実的な選択肢となります。
患者様のご希望と実際の口腔内状況を正しく照らし合わせることが、「削らずに治す」という考えをうまく実現させる鍵となります。
治療中に見た目はどうなる?仮歯は目立つ?

仮歯の審美性と違和感の有無
セラミック治療では、歯を削った後から最終的な補綴物(セラミッククラウンやベニア)を装着するまでに一定の期間が必要です。この間に使用されるのが「仮歯(テンポラリークラウン・プロビジョナルレストレーション)」です。仮歯の主な目的は、削った歯の保護、歯の移動防止、噛み合わせの維持、そして審美性の確保です。
治療期間中の会話・接客への配慮
前歯の治療を行う方の多くが気にするのが、「治療期間中の見た目や発音に支障は出ないか?」という点です。とくに接客業や営業職など、人と接する機会が多い方にとっては切実な問題です。仮歯は基本的に日常会話に支障が出ないように設計されており、特定の発音(サ行・タ行)で滑舌が悪くなるといったケースは稀です。ただし、削った直後や仮歯がまだ馴染んでいない数日は、少し発音しにくさを感じる方もいます。
また、仮歯の素材はセラミックよりもやや柔らかいため、硬い食べ物や粘着質のあるもの(キャラメル・ガムなど)は避ける必要があります。治療中の制約がゼロとは言えませんが、患者様のライフスタイルや職業に合わせた治療計画の提案も可能ですので、不安な点は事前に歯科医院に相談することが安心に繋がります。
カラーや形状の調整は可能か?
仮歯は「最終的なセラミック補綴物の前段階」としての役割もあり、カラーや形状の調整も可能です。実際、仮歯を装着した状態で数日〜数週間過ごしてみて、「色味」「大きさ」「厚み」「歯の長さ」などの細かい感覚を確認することができるため、理想の仕上がりに向けた微調整のための“試着”のような役割も果たします。
仮歯の色調は限られた範囲内での調整にはなりますが、周囲の歯に馴染む色を選ぶことは可能です。また、実際に口元での見え方や笑ったときの印象を確認しながら、最終的なセラミック作製時にはその情報を反映させることができます。つまり、仮歯を装着している期間は、単なる「つなぎの時間」ではなく、最終的な仕上がりの質を高めるための大切なプロセスでもあります。細かな要望は遠慮せずに伝えることで、満足度の高い審美治療へとつながります。
セラミック治療後に後戻りすることはある?

再びすき間ができる原因とは
セラミックで前歯のすきっ歯を改善したあと、まれに「また隙間が開いてきた気がする」と感じる方がいます。この“後戻り”のような現象は、セラミック自体が動くわけではなく、周囲の口腔環境の変化によって生じることがほとんどです。たとえば、噛み合わせのバランスが崩れて他の歯が動いたり、歯周病によって歯ぐきが下がり隙間が目立つようになったり、舌や唇の癖によって微細な力が持続的に加わることで、前歯の位置に影響が出ることもあります。また、セラミックの接着が不十分だった場合や、咬合力の過剰な集中によって接着剤が緩んでしまうケースもゼロではありません。こうした事態を未然に防ぐためにも、治療後の咬合調整や定期メンテナンスが非常に重要になります。
噛み合わせと舌癖の影響
意外に見落とされがちなのが、「舌の癖(舌突出癖)」や「唇の圧力」といった無意識の習慣が歯並びや補綴物に影響を及ぼすケースです。とくに、舌で前歯を押す癖があると、少しずつ前歯が前方に押し出されて隙間ができてしまうことがあります。また、上下の歯の接触が偏っている場合、特定の歯に負担が集中し、セラミックが微妙にズレる・浮き上がるといった現象につながることも。
こうしたリスクを抑えるために、治療前に咬合の診断をしっかり行い、力のバランスを調整することが必須です。舌癖が疑われる場合には、口腔筋機能療法(MFT)と呼ばれる訓練を併用したり、マウスピースを使って力の影響をコントロールしたりする選択肢もあります。審美補綴は見た目だけでなく、機能性を安定させる環境づくりが結果として後戻りの予防につながります。
定着性の高い処置を選ぶ重要性
セラミック治療における“後戻り”を防ぐためには、使用する接着材(セメント)や処置の精度、そして歯の状態に合った材料選択が大切です。最近では、歯質と化学的に強固に結びつく接着性レジンセメントが主流となっており、従来よりも脱離しにくくなっています。とはいえ、セラミックの装着は「はめるだけ」ではなく、歯と補綴物の形状の適合性、接着面の処理、乾燥状態などの細部まで丁寧に管理する必要があります。
また、材質選びも重要で、たとえば薄くて軽いラミネートベニアは審美性に優れますが、すき間の幅が大きい場合には耐久性や接着安定性の観点からクラウンが適していることもあります。治療を長持ちさせるためには、素材や設計だけでなく、技術と診断の正確さが不可欠です。これらの要素が揃ってこそ、後戻りの少ない美しい仕上がりが実現します。
セラミックはどれくらい自然に見える?

天然歯との色調の再現性
セラミックの最大の魅力のひとつが、天然歯に極めて近い色合いと透明感を再現できる点です。市販の歯科用セラミック材料には複数の色調が用意されており、歯の白さや黄色み、赤みなど、個々人の歯の色にきめ細かく合わせることができます。治療の際には、シェードガイドと呼ばれる色見本を使って、患者様自身の歯と最も近い色を選定し、それをもとに技工士が一点一点手作業で作り上げていきます。
とくにe.maxやジルコニアに代表される最新のセラミック素材は、自然な光の透過性と反射を持っているため、周囲の歯に溶け込むような仕上がりが可能です。加えて、色ムラや微妙な透明感まで再現できるため、「どこを治療したかわからない」と感じられるほどの自然な見た目を実現できます。審美治療の仕上がりは“色”が印象を大きく左右するため、色調選びは非常に重要な工程です。
表面の質感・透過性の精度
自然な歯に見せるためには、「色」だけでなく表面の質感と光の透過性が非常に重要です。天然歯の表面には、肉眼では見えにくい繊細な凹凸やツヤがあります。これにより、光が当たったときに複雑な反射や屈折が生まれ、深みのある自然な印象が演出されるのです。
セラミック治療においては、技工士がセラミックの表面に細かなテクスチャーを施し、艶消しのマット感や自然な光沢をコントロールすることで、こうした質感を忠実に再現します。また、厚みの違いによって透過率が変わるため、光をどのように通すかを設計段階で緻密に調整することが求められます。こうした加工は既製品ではなく、すべてオーダーメイドで一人ひとりに合わせて設計・焼成されるため、画一的な見た目ではなく、個性にフィットした自然な口元を作り出すことができるのです。
技工士の技術力による違い
セラミック治療の仕上がりは、材料の質や歯科医師の設計だけでなく、最終的な「見た目」を左右するのは技工士の腕にかかっています。セラミックの形成は、数十層にわたる細かな色の重ねや質感づくりを行う、まさに“職人技”です。経験豊富な技工士は、患者様の年齢・性別・顔の印象・口元のバランスなどを加味して、「自然に見える歯」を感性と技術で仕上げます。
また、医院によっては歯科技工所と連携して、色合わせのための立ち会い(シェードテイキング)を行う場合もあり、より高い再現性を追求する体制が整っています。セラミック治療は単なる“白い歯”を作るのではなく、「周囲と調和する美しさ」をいかに実現できるかが満足度を左右します。自然な見た目にこだわる方は、どの技工所と連携しているか、どのような制作体制かを事前に確認しておくこともおすすめです。
保険診療ではできないの?費用は?

自費治療の理由と制度的背景
セラミックによる前歯のすきっ歯治療は、原則として健康保険の適用外(自費診療)になります。これは、日本の医療保険制度における「機能回復を目的とする最低限の治療のみが保険対象」というルールに基づいています。つまり、噛む・食べるという機能に加え、「見た目を美しく整えたい」という審美性の追求が加わる場合には保険ではカバーされないのです。
また、セラミックは審美性・強度・耐久性ともに非常に優れた素材ですが、保険診療ではこれに相当する材料や技術の使用が制限されており、精密な設計やオーダーメイドの制作工程を含む治療は必然的に自費扱いとなります。
ただし、保険診療でも条件付きで白い被せ物(硬質レジン前装冠など)が使用できることもありますが、変色や割れやすさ、見た目の限界から、審美性を重視するケースではセラミックが優先される傾向にあります。
費用相場と内容の内訳(本数・材料・技工費など)
セラミック治療の費用は、使用する素材や補綴の種類、本数、医院の方針によって大きく変動します。
一般的な相場としては、
ラミネートベニア:1本あたり8〜15万円前後
セラミッククラウン:1本あたり10〜18万円前後
が目安となります(税別)。
この費用には、診査診断料、仮歯、型取り、技工所でのオーダーメイド製作、装着後の調整などが含まれるのが一般的です。
また、ジルコニアやe.maxなど、素材によっても価格差が生じるほか、症例が難しい場合には特別設計料が加算されることもあります。技工士が立ち会うシェードテイキング(色合わせ)を行う場合には、別途費用がかかるケースもあります。
さらに、複数本の同時治療で割引がある医院もあれば、1本ずつ完全に独立した設計を行うことで費用が高くなることもあるため、事前の見積もり確認はとても大切です。
医院による料金の差と見積もりの比較ポイント
同じセラミック治療でも、医院によって費用が大きく異なることがあります。
この差は単に「価格が安い・高い」という問題ではなく、提供される治療の中身や保証内容、製作に関わる技工士のレベル、素材の品質などに起因します。たとえば、同じe.maxクラウンでも、海外製の量産品を使うのか、国内の精密技工所で職人が手作りするのかで、費用にも品質にも大きな違いが生じます。
また、料金の中にどこまで含まれているかも要チェックです。仮歯の費用、調整料、再診料、保証期間などが別料金になっている医院もあります。
費用面だけで比較するのではなく、どのような治療が受けられるか、どのレベルの仕上がりが保証されるかという“質”の部分に注目することが重要です。不明点は遠慮なく質問し、納得できるまで説明を受けることが、信頼できる医院選びの第一歩となります。
セラミック治療後に必要なメンテナンスとは?

メンテナンスの頻度と内容
セラミック治療は一度装着すれば終わり、というものではありません。美しい状態と機能を長期間維持するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。一般的に、治療後は3ヶ月〜6ヶ月ごとの定期検診を推奨しています。
この定期検診では、咬み合わせのチェック、セラミックと歯の境目の確認、歯ぐきの状態の確認、必要に応じたクリーニングなどが行われます。特に咬合は時間の経過とともに微妙に変化することがあり、負担のかかる位置を調整することで破損のリスクを防ぐことができます。
また、セラミックは虫歯にはなりませんが、接着面からの二次虫歯や歯周病は十分に起こり得るため、専門的な清掃やフッ素塗布も有効です。治療後こそが本当のスタートと考え、口腔内の健康管理に取り組むことが、セラミックを長持ちさせる最大の秘訣です。
自宅でのケア方法と避けるべき習慣
日々のセルフケアも、セラミック治療の寿命を左右する大切な要素です。まず、歯ブラシはやわらかめのものを使い、補綴物と歯ぐきの境目に優しく当てて磨くことが基本です。ゴシゴシと強くこすると、セラミックに細かい傷がついたり、歯ぐきが退縮するリスクがあります。また、歯間ブラシやデンタルフロスも積極的に取り入れ、補綴物の両サイドや隙間の汚れを確実に除去する習慣をつけましょう。
加えて、セラミックを破損させやすい習慣、たとえば硬いものを前歯で噛む、氷を噛む、ペンを咥える、歯ぎしりを放置するといった癖は避ける必要があります。こうした習慣を見直すことで、見た目の美しさだけでなく、機能性の維持にもつながります。
「見た目が綺麗だから大丈夫」と油断せず、日々の積み重ねが治療結果を左右することを意識することが大切です。
セラミック特有の注意点と定期検診の重要性
セラミックは変色しにくく、非常に耐久性のある素材ですが、天然歯とは性質が異なるため特有の注意点も存在します。たとえば、セラミックは強い力に対して一気に破折する性質があり、見た目に問題がなくても、小さなヒビや亀裂が入っていることがあるのです。これを見逃すと、突然破損して再治療が必要になる場合もあります。
また、歯ぐきとの境目にプラークが蓄積すると、見た目の変化(ブラックマージン)や歯周病が進行してしまうこともあります。これを防ぐためには、定期検診で早期発見・早期対応をすることが非常に重要です。
さらに、セラミックの装着後にかみ合わせの変化が生じた場合、微細な不調でも早めに調整することでトラブルを未然に防ぐことができます。医師と患者の“二人三脚”での継続的なケアが、セラミック治療の価値を最大限に高めるのです。
セラミック治療で失敗しないために知っておきたいこと

・カウンセリング時に確認すべき3つのこと
セラミック治療を成功させるためには、治療開始前のカウンセリングが極めて重要です。特に初診の段階では、仕上がりだけでなく、治療内容・治療方針・素材の選択肢などを十分に理解することが不可欠です。確認すべきポイントは主に3つあります。1つ目は、「どのような治療法を提案されているのか」。ラミネートベニアかクラウンか、その理由とリスクを丁寧に説明してもらえるか確認しましょう。2つ目は、「治療のゴール(見た目・機能)の共有ができているか」。理想の色味や形状、仕上がりの雰囲気など、自分のイメージが伝わっているかが重要です。そして3つ目は、「治療後のメンテナンス計画があるか」。美しい状態を長く保つためには、装着後のサポート体制が不可欠です。これらの確認を怠ると、「思っていた仕上がりと違った」「すぐにトラブルが起きた」といった不満につながりかねません。納得した上で治療に進める医院を選ぶことが、失敗しないための第一歩です。
・医院選びで注目すべきポイント
セラミック治療は自由診療であり、医院によって治療方針や技術力、設備の質に大きな差があります。だからこそ、医院選びは非常に重要な判断材料です。まず注目すべきは、審美補綴に力を入れているかどうか。ホームページやパンフレットに、セラミックや前歯の治療例、取り扱い素材が明記されている医院は、審美治療に精通している可能性が高いと言えます。
次に、歯科技工士との連携体制も重要です。技工士との距離が近い医院では、色合わせや形状の微調整がスムーズに進みやすく、患者様の希望にきめ細かく対応できます。また、カウンセリングの時間をしっかり取ってくれるか、質問に対して誠実に答えてくれるかも信頼性の指標になります。
価格だけで判断するのではなく、「自分に合った治療が受けられる環境かどうか」を基準に、信頼できる医院を選ぶことが、後悔しない治療につながります。
・長く快適に使い続けるための心構え
セラミック治療を成功させるうえで、医院選びや治療内容だけでなく、患者様自身の「心構え」も大切な要素です。まず理解しておきたいのは、どんなに優れた素材であっても、「永久にトラブルがない」わけではないということ。過度な力、歯ぎしり、清掃不足などによってセラミックに影響が出ることはあります。
したがって、治療を“ゴール”ではなく“スタート”と捉え、継続的なセルフケアと定期検診を欠かさない意識が大切です。また、見た目だけでなく、噛み合わせや歯ぐきの状態など、トータルでの口腔環境維持にも目を向けることが求められます。
さらに、生活習慣の見直しも重要です。前歯で硬いものを噛まない、舌癖を改善する、ナイトガードを活用するなど、自分の口元に責任を持つ姿勢が、美しい状態を10年、20年と保つ鍵になります。
「きれいな歯であり続けたい」という気持ちを行動で支えること。それが、満足度の高いセラミック治療の本当の価値を引き出すポイントです。
埼玉県大宮の再治療0%を追求した
審美歯科セラミック治療ガイド
監修:関口デンタルオフィス大宮
電話番号:048-652-1182
*監修者
関口デンタルオフィス大宮
*経歴
・2008年 日本大学歯学部卒業
日本大学歯学部臨床研修部入局
・2009年 日本大学歯学部補綴学第一講座入局
専修医
顎関節症科兼任
・2014年 同医局退局
関口デンタルオフィス開院
*所属学会
*スタディークラブ
・CIDアクティブメンバー(Center of Implant Dentistry)