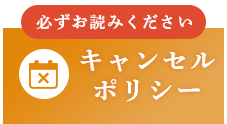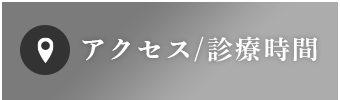差し歯の色が合わないのはなぜ?“浮いて見える口元”を自然に整えるセラミック治療
- 2025年10月15日
- 審美歯科
目次
差し歯の色だけが「浮いて見える」…口元の悩みを抱えていませんか?

写真を見返すと、1本だけ色が白すぎる(または黄色い)
ご友人との楽しい食事会や記念撮影。あとで写真を見返した時、ご自身の笑顔の中で、特定の差し歯1本だけが、周りの歯と色が合わないで不自然に目立っていることに気づき、愕然とした経験はありませんか。その差し歯は、治療した当時は周囲の歯と色合わせをして馴染んでいたはずなのに、数年経つうちに、まるでそこだけが「浮いて」見えるようになってしまったのです。これは、周囲の自然な歯(天然歯)が加齢や食生活によって徐々に色調が変化する一方で、差し歯(特に保険適用のレジン=プラスチック素材)は色が変わらない、あるいは逆に変色して黄ばんでしまうことで起こる「色の不一致」です。この「白すぎる」または「暗すぎる」という色のギャップは、セラミック治療(審美治療)によるやりかえで、現在の周囲の歯の色に自然に調和させることが期待できます。
周囲の天然歯と比べて、透明感がなく「のっぺり」している
差し歯の色が合わないと感じる原因は、色合い(黄み・赤み)だけではありません。自然な歯の美しさを決定づける最も重要な要素の一つが「透明感」です。天然の歯は、光を適度に透過する半透明な構造(エナメル質)を持っていますが、古いタイプの差し歯や、保険適用のレジン(プラスチック)で作られた差し歯は、光を透過しない「不透明」な材質であることが多いです。そのため、光が当たった時に、周囲の歯は自然に輝くのに対し、差し歯だけが光を反射せず、「のっぺり」とした絵の具を塗ったような、人工的な見た目になってしまいます。この「透明感の欠如」こそが、色合わせをしたはずの差し歯が浮いて見える最大の原因です。セラミック治療(特にオールセラミック)は、この天然歯に近い透明感を再現することを得意としており、周囲の歯列に溶け込むような自然な仕上がりが期待できます。
差し歯の根元や、歯ぐきの境目が黒ずんできた
差し歯自体の色だけでなく、その「根元」や「歯ぐきとの境目」が黒ずんできた、というお悩みも非常に多く寄せられます。この黒ずみには、主に3つの原因が考えられます。1つ目は、差し歯の内部に金属の土台(メタルコア)やフレームが使われている場合、その金属イオンが唾液によって溶け出し、歯ぐきに沈着してしまう「メタルタトゥー(金属刺青)」です。2つ目は、加齢や歯周病によって歯ぐきが痩せて(歯肉退縮)、差し歯の縁や内部の金属部分が露出して見えている状態です。3つ目は、差し歯と歯ぐきの隙間から虫歯が再発し、それが黒く透けて見えている可能性です。いずれの場合も、色が合わないだけでなく、不健康な印象を与えてしまいます。この問題は、金属を一切使用しないセラミッククラウンや、土台を金属以外のもの(ファイバーコアなど)にやりかえる審美治療で、根本的な改善が期待できます。
なぜ古い差し歯は「色が合わない」と感じるのか

「差し歯」とは?(被せ物・クラウンの仕組み)
一般的に「差し歯」と呼ばれるものは、歯科の専門用語では「クラウン(被せ物)」の一種を指すことが多く、特に神経(歯髄)の治療(根管治療)を終えた歯に、土台(コア)を立て、その上から全体を覆うように装着する人工の歯冠(しんかん)を指します。この差し歯は、失われた歯の機能と見た目を回復させる治療法です。治療当時は、周囲の歯と色合わせを行い、自然に見えるように作製されます。しかし、時間が経過するにつれて、差し歯の材質そのものの問題や、土台に使われている金属の影響、あるいは周囲の自然な歯の色が変化することなど、様々な原因で「色が合わない」「浮いて見える」といった審美的な問題が生じてくることがあります。セラミック治療は、この不自然な見た目を改善する選択肢の一つです。
原因①:材質の限界(保険適用のレジン=プラスチック)
昔に治療した差し歯の色が合わないと感じる大きな原因の一つに、保険診療で使用される材料の「材質的な限界」があります。保険適用の前歯の差し歯(例:硬質レジン前装冠)は、中身が金属で、表面に「レジン」という歯科用プラスチックを盛り付けて白さを表現しています。レジンは、セラミック(陶器)とは異なり、自然な歯が本来持っている「透明感(光の透過性)」を再現することが非常に困難です。そのため、治療直後に色合わせをしても、光が当たるとセラミックのような自然な深みがなく、「のっぺり」とした人工的な白さに見えがちです。この「透明感のなさ」が、周囲の自然な歯から浮いて見える根本的な原因となります。
原因②:経年劣化による水分や色素の吸収(変色)
保険適用の差し歯に使用される「レジン(プラスチック)」は、自然な歯の表面(エナメル質)やセラミックとは異なり、「吸水性(きゅうすいせい)」があるという材質的な特徴を持っています。お口の中は常に水分や飲食物にさらされているため、長期間使用するうちに、このレジンが水分や色素(コーヒー、お茶、ワイン、カレーなど)を徐々に吸収してしまいます。その結果、差し歯そのものが「変色」し、だんだんと黄ばんだり、くすんだりしてきます。これが、治療から数年経って「色が合わない」と感じるようになる「経年劣化」です。治療時には完璧な色合わせをしても、差し歯だけが変色してしまうため、周囲の歯との色のギャップが生まれてしまうのです。セラミックは色素を吸収しにくいため、このような変色リスクが低い材質です。
差し歯が「不自然」に見える、材質以外の要因

要因①:歯ぐきの退縮(加齢・歯周病)
差し歯を装着した当初は、歯ぐきのラインと差し歯の縁(マージン)がぴったり合っていても、加齢や歯周病の進行によって歯ぐきが痩せて下がってくる(歯肉退縮)ことがあります。歯ぐきが下がると、これまで隠れていた差し歯の根元の部分や、ご自身の歯の根(象牙質)が露出してしまいます。歯の根(象牙質)は、もともと歯冠部(白い部分)よりも色が黄色っぽいため、差し歯との色のギャップが生まれ、「色が合わない」「境目が目立つ」といった不自然さの原因となります。セラミック治療でやりかえる際は、この現在の歯ぐきのラインに合わせて、より自然に見えるよう色合わせを行います。
要因②:内部の金属の土台(メタルコア)の露出
古い差し歯(特に保険適用のもの)では、歯の土台(コア)として金属(メタルコア)が使用されていることが一般的です。この金属の色が、被せ物(差し歯)の材質(特にレジンや透明感の低いセラミック)を透過して、歯全体が自然な歯と比べて暗く、浮いて見えることがあります。これが「色が合わない」と感じる原因の一つです。さらに、加齢や歯周病で歯ぐきが下がると、この金属の土台の縁(黒い線)が直接露出してしまい、審美性を大きく損ねます。セラミック治療でやりかえる際は、この土台(コア)も金属を使用しない白いファイバーコアなどに変更することで、セラミック本来の透明感を引き出し、より自然な色合わせが可能になります。
要因③:周囲の天然歯の色の変化(加齢・黄ばみ)
差し歯が不自然に見える原因が、差し歯側ではなく、周囲のご自身の歯(天然歯)側にあるケースも少なくありません。天然歯は、加齢やコーヒー、お茶、ワイン、タバコのヤニなどの色素沈着(ステイン)によって、治療した数年前よりも徐々に色が濃く、黄ばんでいきます。一方で、差し歯、特にセラミックやレジン(プラスチック)は人工物であるため、その色はほとんど変化しません。治療当時は完璧に色合わせができていても、周囲の自然な歯の色が変化した結果、相対的に差し歯だけが「白く浮いて見える」ようになり、「色が合わない」と感じるようになるのです。この場合、現在の周囲の歯の色に合わせてセラミックでやりかえる、あるいは周囲の歯をホワイトニングで白くするといった審美的な改善策が考えられます。
「色が合わない」悩みに。「セラミック治療」という選択肢

セラミックとは?(金属を使わない審美修復材料)
セラミックとは、歯科の審美治療で用いられる「陶材(とうざい)」を主成分とした修復材料のことです。色が合わない差し歯の原因となりやすい金属(メタル)や、保険適用で使われるレジン(プラスチック)とは根本的に材質が異なります。セラミックの大きな利点は、金属を一切使用しない「メタルフリー」での治療が可能な点です(種類によります)。金属を使用しないため、古い差し歯に見られるような歯ぐきの黒ずみ(メタルタトゥー)や、金属アレルギーのリスクを回避できます。また、材質自体が自然な歯の色調や透明感に非常に近いため、周囲の歯と色合わせをした際に、差し歯とは分かりにくい自然な仕上がりを追求できます。保険の差し歯(レジン)のように水分や色素を吸収して変色することもほとんどないため、長期的に審美性を維持しやすいのが特徴です。
なぜセラミックは「自然」な色調を再現できるのか
差し歯の色が合わないと感じる最大の原因は、周囲の自然な歯が持つ「透明感」が、人工の差し歯にないことです。天然の歯は、単一の色ではなく、表面のエナメル質は透明に近く、内部の象牙質は少し黄みがかっている…といった複雑な層構造をしています。セラミック(特にオールセラミック)は、この自然な歯が持つ光の透過性や、歯の先端から根元にかけての微妙な色の変化(グラデーション)を、高いレベルで再現できる材質です。保険適用のレジン(プラスチック)や、内部に金属を使用した差し歯のように光を遮断せず、自然光の下でも周囲の歯に溶け込むように見えます。この「透明感の再現」こそが、セラミック治療での色合わせが自然な仕上がりを実現できる最大の理由です。
差し歯をセラミックにやり替えるメリット
古い差し歯をセラミックにやり替えるメリットは、色が合わないという審美的な問題を解決するだけではありません。第一に、自然な「見た目の美しさ」です。セラミックは変色しにくいため、色合わせした自然な白さが長持ちします。また、金属を使用しないため、差し歯の根元の歯ぐきが黒ずむ(メタルタトゥー)原因を取り除くことができます。第二に、「体への優しさ」です。セラミックは生体親和性が高い(体に馴染みやすい)材料であり、金属を用いないため、金属によるアレルギーの心配を回避しやすい材料です。第三に、「虫歯の再発リスクの低減」です。セラミックの表面は非常に滑らかで、レジン(プラスチック)に比べて虫歯の原因となるプラーク(歯垢)が付着しにくいという特徴があります。また、精密な接着技術により、歯とセラミックの隙間を少なくできるため、二次虫歯の予防にもつながります。
なぜセラミックは「自然」なのか?材質の種類と特徴

最も美しい透明感「オールセラミック(e.maxなど)」
古い差し歯が不自然に見える最大の原因は、「透明感」の欠如です。保険適用の差し歯や内部に金属を使用したものは光を透過しないため、自然な歯と並ぶと「のっぺり」と浮いて見え、色が合わないと感じさせます。これに対し、「オールセラミック」は、金属を一切使用せず、100%セラミック(陶材)のみで作られた審美修復物です。その最大のメリットは、自然な歯が持つ光の透過性と、複雑な色合い(グラデーション)を極めて高いレベルで再現できる点にあります。代表的な素材である「e.max(イーマックス)」は、二ケイ酸リチウム(リチウムジシリケート)系ガラスセラミックという高強度なガラス系セラミックで、その透明感と美しさはセラミック材料の中でも特に優れています。光が自然に透過するため、差し歯と歯ぐきの境目が暗く見えたり、浮いて見えたりすることがありません。特に人目に触れやすい前歯や小臼歯の差し歯をやりかえる際に、周囲の歯と違和感のない自然な色合わせを追求する審美治療において、最も推奨される選択肢の一つです。
強度と美しさを両立「ジルコニアセラミック」
「奥歯の差し歯も白くしたいが、セラミックは割れそうで不安」という方には、強度と審美性を両立した「ジルコニアセラミック」が適しています。ジルコニアは「人工ダイヤモンド」とも呼ばれるほど非常に高い強度と耐久性を誇るセラミック材料です。歯科材料の中でも特に頑丈なため、噛む力が強くかかる奥歯の差し歯(クラウン)や、複数の歯を連結するブリッジ治療にも使用することが可能です。以前のジルコニアは、強度が高い反面、色が均一で透明感に乏しく、審美的な面では自然さに欠けるという側面がありました。しかし、材料開発が進んだ現在では、自然な歯に近い透明感や色のグラデーションを持つ「高透光性ジルコニア」も登場し、奥歯でも審美的な色合わせが可能になっています。ジルコニアも金属を一切使用しないため、保険の差し歯のように金属イオンが溶け出して歯ぐきを黒ずませる(メタルタトゥー)心配がなく、色が合わないといった審美的な問題を防ぎます。差し歯のやりかえにおいて、機能的な「強度」と「美しさ」の両方を妥協したくない場合の有力な選択肢です。
保険の差し歯(CAD/CAM冠)との審美性の違い
近年、保険診療でも一定の条件(主に小臼歯や一部の大臼歯)を満たせば、「CAD/CAM冠(キャドキャムかん)」という白い差し歯を選択できるようになりました。しかし、これは審美治療で用いられる自費の「オールセラミック」とは、材質と審美性において明確な違いがあります。CAD/CAM冠の材質は、セラミックの微粒子とレジン(歯科用プラスチック)を混ぜ合わせた「ハイブリッドレジン」です。一方、オールセラミックは100%陶材です。この材質の違いが、見た目の自然さに大きく影響します。
透明感と色合わせ:セラミックは自然な歯の透明感を再現できますが、CAD/CAM冠はプラスチックを含むため光の透過性が低く、「のっぺり」とした人工的な白さになりがちです。これが色が合わない、浮いて見える原因となります。
変色:セラミックは色素を吸収しにくく、変色しにくいため長期的に色調を保ちやすいのが特長です。一方、CAD/CAM冠はプラスチックの性質上、数年経つと水分や色素を吸収し、黄ばんだり変色したりする可能性があり、将来的に「色が合わない」状態になるリスクがあります。審美性を最優先し、長期的に自然な美しさを維持したい場合は、セラミック治療が推奨されることが多いです。
自然な「色合わせ(シェードテイキング)」を実現する精密な技術

歯の色は「真っ白」ではない(複雑な色調の分析)
差し歯が浮いて見える(色が合わない)原因として、その色を「白すぎる」単一の色で作ってしまうことが挙げられます。実は、自然な天然歯は「真っ白」ではありません。わずかな黄みや赤み、グレーがかった色合い(色相)、色の濃さ(彩度)、明るさ(明度)、そして透明感といった、非常に多くの要素が複雑に組み合わさって、その人固有の色を形成しています。審美治療における精密な「色合わせ(シェードテイキング)」では、歯科医師が専用の色見本(シェードガイド)や撮影機器を用い、こうした複雑な色の情報を詳細に分析・記録します。セラミック治療で自然な差し歯を実現するには、この「色の解像度」を高める分析作業が不可欠です。
周囲の歯と調和させる「グラデーション」の再現
自然な歯をよく見ると、1本の歯の中でも色が均一ではないことがわかります。歯の根元(歯ぐきに近い部分)は、内部の象牙質の色が濃く反映されるため、少し黄み(色)が濃くなっています。そして、歯の先端(切端)に向かうにつれてエナメル質の透明感が増し、わずかに青みがかって見えることもあります。古い差し歯が「色が合わない」「不自然」に見える原因の多くは、この自然な色の変化(グラデーション)が再現されておらず、根元から先端までのっぺりとした単一色で作られているためです。セラミック治療での精密な色合わせでは、このグラデーションをセラミックの粉末を何層にも分けて盛り付けたり、色付けしたりすることで忠実に再現し、周囲の歯と調和する差し歯を目指します。
歯科技工士との連携が「自然な仕上がり」を生む
歯科医師が分析した複雑な色の情報を、最終的にセラミックという「形」に仕上げるのが、審美修復物を専門に作製する「歯科技工士」です。差し歯が色が合わないという問題を解決し、自然な審美治療を実現するためには、歯科医師と歯科技工士との密接な連携が欠かせません。歯科医師は、色合わせで得た情報(どの部分にどのような透明感や色合いがあるか)を、口腔内写真や指示書を用いて歯科技工士に正確に伝達します。そして、高度な技術を持つ歯科技工士は、その情報を基に、隣の歯の表面に見られるわずかな縞模様や、個体差のある透明感までをもセラミックで再現していきます。この歯科医師の「分析力」と歯科技工士の「再現力」の連携こそが、自然な差し歯を生み出す鍵となります。
差し歯を「やり替える」治療の基本的な流れ

STEP1:カウンセリングと精密検査(土台・根の状態確認)
差し歯の「色が合わない」というお悩みを解決するための第一歩は、患者さんのお気持ちを伺うカウンセリングから始まります。どの差し歯が、どのように不自然に見えるのか、最終的にどのような口元を希望されるのかを詳しくヒアリングします。その上で、セラミック治療などの選択肢や、それぞれのメリット・デメリット、治療期間や費用の目安についてご説明します。次に、審美治療であっても不可欠なのが「精密検査」です。特に差し歯のやりかえでは、見えない部分の状態確認が極めて重要です。レントゲン撮影(デンタルX線写真)や、必要に応じて歯科用CTを用い、差し歯の土台(コア)の状態や、そのさらに下にある歯の根(根管)が適切に治療されているか、感染(根尖病巣)を起こしていないかを徹底的に確認します。この検査結果が、すぐにやりかえが可能か、あるいは色合わせの前に土台や根の再治療が必要かを判断する重要な基準となります。
STEP2:古い差し歯の除去と土台(コア)の処置
精密検査とカウンセリングに基づいた治療計画にご同意いただけたら、実際の処置に入ります。まず、色が不自然になっている古い差し歯(クラウン)を、周囲の歯ぐきを傷つけないよう慎重に削りながら除去します。この処置は、必要に応じて局所麻酔を使用しますので、痛みを感じることはほとんどありません。差し歯を外すと、その下にある土台(コア)の状態が明らかになります。古い差し歯の色が合わない原因の一つとして、この土台に金属(メタルコア)が使われていることが挙げられます。金属の色が歯ぐきを黒ずませたり、セラミックを被せても内部から透けて見えたりするためです。セラミック本来の透明感を引き出し、より自然な色合わせを実現するために、この金属の土台を、色が白く自然な歯に近い「ファイバーコア」などにやりかえる処置を行うことが多くあります。また、もし土台の周囲に虫歯が再発していた場合は、この段階で丁寧に取り除きます。
STEP3:精密な型取りと「仮歯」の装着
土台(コア)の処置が完了し、セラミックを被せるための健康な土台が整ったら、自然な差し歯を作製するための「精密な型取り(印象採得)」を行います。審美治療の仕上がりは、この型取りの精度に大きく左右されます。セラミックとご自身の歯との間にミクロン単位の隙間も作らないよう、シリコンなどの精密な材料や、光学スキャナ(口腔内スキャナ)を用いて歯の形態を正確に記録します。同時に、セラミックの色を決める最も重要な工程「色合わせ(シェードテイキング)」を行います。周囲の自然な歯の色合い、透明感、グラデーションなどを、専用の色見本や写真撮影(シェードテイキング用カメラ)で詳細に記録します。型取りが完了したら、最終的なセラミック歯が完成するまでの間、日常生活に支障がないよう、その場でプラスチック製の「仮歯(かりば)」を作製・装着します。仮歯で見た目や発音、食事などの機能を一時的に回復させます。
STEP4:セラミック歯の装着と噛み合わせ調整
精密な型取りと色合わせの情報に基づき、歯科技工士がオーダーメイドのセラミック歯を作製します。約1〜2週間後、完成したセラミックの差し歯を歯科医院にお持ちします。まず、装着していた「仮歯」を外し、お口の中を清掃します。次に、完成したセラミック歯を実際にお口の中に入れ、適合性を確認します。歯科医師が、色合いや形が周囲の歯と自然に調和しているか、セラミックと歯の「境目」に段差や隙間がないかを厳密にチェックします。この際、患者さんご自身にも鏡でご確認いただき、色が合わないといった違和感がないか、審美的にご満足いただけるかを確認します。問題がなければ、セラミック専用の強力な接着剤(レジンセメントなど)を用い、歯とセラミックを化学的に一体化させます。最後に、上下の歯が自然に噛み合うよう、全体の噛み合わせ(咬合)を精密に調整して、やりかえ治療は完了となります。
差し歯の「やり替え」で注意すべき点

歯ぐきの黒ずみ(メタルタトゥー)は改善できるか
差し歯の色が合わないというお悩みと同時に、「歯ぐきの境目が黒ずんでいる」ことも不自然に見える大きな原因です。この黒ずみが、差し歯の内部に使用された金属の土台(メタルコア)などから溶け出した金属イオンが、歯ぐきに沈着してしまった「メタルタトゥー(金属刺青)」である場合、注意が必要です。差し歯を金属不使用のオールセラミックにやりかえることは、これから先に金属イオンがさらに溶け出すのを防ぎ、黒ずみが悪化するのを予防する原因療法となります。しかし、「すでに沈着してしまった黒ずみ」は、差し歯をやりかえただけでは消えずに残ってしまうケースが少なくありません。この場合、セラミック治療による自然な色合わせと併せて、歯ぐきの黒ずみを除去するための別途処置(レーザー治療や薬剤を用いたピーリングなど)を検討する必要があります。審美治療としてどこまでの改善を希望されるか、歯科医師に相談し、処置の可能性と限界について理解しておくことが大切です。
内部の土台(コア)のやり替えが必要なケース
差し歯の色が合わないという審美的な問題を解決するためにセラミック治療を行う際、その仕上がりを大きく左右するのが、差し歯の「内部の土台(コア)」です。古い差し歯では、この土台に金属(メタルコア)が使われていることが一般的です。金属の土台は、セラミック本来のメリットである「透明感」を内部から遮断してしまいます。特に透明度の高いオールセラミックを被せた場合、内部の金属の色が透けてしまい、差し歯全体が自然な歯よりも暗く浮いて見え、色が合わない原因となります。この問題を根本から解決し、セラミックの透明感を最大限に引き出すためには、差し歯のやりかえと同時に、この金属の土台(メタルコア)も、色が白く自然な歯に近い「ファイバーコア」などにやりかえることが推奨されます。また、土台自体が虫歯になっていたり、適合が悪くなっていたりする場合も、審美治療の前に土台をやりかえる必要があります。
歯の根(根管)の再治療が優先される場合
差し歯の色が合わないという審美的な理由でやりかえを希望された場合でも、歯科医師がセラミック治療(色合わせ)の前に、まず歯の「根(根管)」の状態を優先的に確認します。差し歯は、神経の治療(根管治療)を終えた歯に装着されています。やりかえ時の精密検査(レントゲンなど)で、この歯の根の先端に炎症や感染の疑い(根尖病巣=膿の袋など)が見つかることは少なくありません。もし、この感染(原因)を放置したまま、上から高額なセラミックの差し歯を被せてしまうと、数年後に再び痛みや腫れを引き起こし、せっかく装着したセラミックをすべて外して「根の再治療」が必要になるリスクがあります。そのため、色が合わないという審美治療を開始する前に、まずこの根管治療の再治療を優先し、歯の基礎(土台)を徹底的に健康な状態に戻すことが、自然な差し歯を長持ちさせるための大前提となります。
差し歯のやり替え・セラミック治療のよくある疑問

Q.やり替え治療は痛いですか?
A.差し歯のやりかえ治療では、「古い差し歯を外す(削る)」「土台を整える」といった処置が必要になるため、痛みをご不安に思われるのは当然です。ご安心ください。これらの処置は、局所麻酔をしっかり効かせた状態で行います。そのため、治療中に痛みを感じることはほとんどありません。これは、通常の虫歯治療で麻酔をするのと同じ感覚です。差し歯を外した際、もし内部で虫歯が再発していたり、土台(コア)のやりかえが必要になったりした場合も、麻酔が効いたまま処置を進めます。新しいセラミックを装着する(接着する)ステップでは、痛みはありません。まれに、虫歯が神経に近かった場合など、再治療後に一時的にしみたり、軽い痛みが出たりする可能性(術後疼痛)はゼロではありませんが、通常は時間の経過とともに落ち着いていきます。審美治療であっても、痛みや不安を最小限に抑えるよう配慮しますので、気になることは遠慮なく歯科医師にお伝えください。
Q.セラミックは割れたり、欠けたりしませんか?
A.セラミックと聞くと「陶器」のイメージから、「差し歯にしても割れやすいのでは?」とご心配されるお気持ちはよくわかります。確かに、金属のような粘り強さ(靭性)はありませんが、近年の歯科用セラミック材料(特にジルコニアなど)は、お口の中で使用するために開発されており、自然な歯と同等か、それ以上の十分な強度と耐久性を備えています。奥歯のやりかえにも問題なく使用できる素材が主流です。ただし、セラミックが長期的に機能するかどうかは、材質の強度だけでは決まりません。セラミックが割れたり欠けたりする原因の多くは、噛み合わせのバランスが悪いことや、ご自身ではコントロールが難しい夜間の「歯ぎしり」や「食いしばり」です。これらがセラミック歯に過度な負担をかけ続けます。そのため、色が合わないといった審美的な問題を解決する審美治療であっても、やりかえの最後に行う「噛み合わせの精密な調整」が非常に重要です。また、歯ぎしりの癖がある方には、大切なセラミック歯を守るために、就寝時に装着する「ナイトガード(マウスピース)」の使用をご提案する場合があります。
Q.治療期間と費用はどれくらいですか?
A.差し歯のやりかえにかかる治療期間と費用は、色が合わないという審美的な問題だけでなく、古い差し歯を外した「内部の状態」によって大きく異なります。治療期間:もし、差し歯を外した内部の土台(コア)や歯の根(根管)に問題がなければ、治療は比較的短期間で完了します。[1回目]に差し歯の除去と精密な型取り、色合わせを行い「仮歯」を装着、[2回目](約1〜2週間後)に完成したセラミック歯を装着、という流れで、通院回数は2〜3回程度が目安です。しかし、内部で虫歯が再発していたり、土台(コア)のやりかえが必要だったり、さらに歯の根の先に感染(根尖病巣)が見つかり「根管治療の再治療」が優先される場合は、まずその基礎治療が完了するまでに別途数回〜数ヶ月の期間が必要となります。費用:セラミックを用いた審美治療は、原則として保険適用外(自費診療)となります。費用は、使用するセラミックの種類(例:オールセラミック、ジルコニアセラミックなど)によって変動します。また、差し歯本体の費用とは別に、土台(ファイバーコアなど)をやりかえる費用や、根管治療の再治療費用が別途必要になる場合があります。カウンセリングと精密検査の際に、ご自身のケースでの総額のお見積もりを歯科医師に確認しましょう。
Q.やり替えた差し歯は、また色が合わなくなりますか?
A.「せっかくやりかえても、数年後にまた色が合わない状態に戻るのでは?」というご不安は、過去に保険の差し歯(レジン=プラスチック製)で経験されたからかもしれません。保険のレジンは、吸水性があるため、コーヒーやお茶、ワインなどの色素を徐々に吸収し、数年で黄ばんだり変色したりしてしまいます。これが色が合わない大きな原因でした。一方、セラミックは「陶器」です。陶器のお皿に色が染み込まないのと同様に、セラミックは色素や水分の吸収がほとんどありません。そのため、経年劣化による「変色」がほぼないのが最大のメリットです。セラミック治療で精密な色合わせを行えば、その色合いや透明感は長期的に維持されます。ただし、注意点が一つあります。セラミックの色は変わりませんが、周囲のご自身の歯(天然歯)は、加齢や食生活によって少しずつ黄ばんでいく可能性があります。その結果、将来的にセラミックの白さが際立ち、相対的に「色が合わない」と感じることはあり得ます。この場合は、定期的なクリーニングで周囲の歯の着色を落としたり、ホワイトニングで自然な色の調和を再び図ったりすることが可能です。
「色が合わない」ストレスから解放され、自然な笑顔へ

差し歯の色の悩みは「治療」で改善が期待できる
差し歯の色が周囲の自然な歯と合わない、浮いて見えるというお悩みは、決して珍しいことではありません。「治療した歯だから仕方ない」と、口元を手で隠したり、思い切り笑うことをためらったりして、長年ストレスを感じている方もいらっしゃるでしょう。しかし、そのお悩みは現代の歯科治療、特に審美治療によって改善が期待できます。古い差し歯の原因が、材質の経年劣化(変色)や、保険適用のプラスチック(レジン)の透明感のなさ、あるいは内部の金属による歯ぐきの黒ずみなどであっても、それらを解決する選択肢があります。金属を一切使用しないオールセラミック治療などへやりかえることで、現在の周囲の歯と調和した自然な色合わせを行い、審美的なコンプレックスを解消することが可能です。色が合わないというストレスは、我慢するものではなく、「治療」によって前向きに解決を目指せる問題なのです。
機能性と審美性を両立させる歯科治療
差し歯のやりかえというと、「見た目をきれいにするためだけ」の審美治療だと思われるかもしれません。しかし、歯科治療において審美性(美しさ)と機能性(よく噛めること)は切り離せない関係にあります。色が合わない古い差し歯は、自然に見えないだけでなく、多くの場合、機能的な問題を抱えています。例えば、差し歯と歯の間に隙間ができて虫歯が再発していたり、内部の金属の土台が歯の根を傷める原因になっていたりすることがあります。セラミック治療は、色合わせが自然であると同時に、材質的にも優れています。セラミックの表面は滑らかでプラーク(歯垢)が付着しにくく、虫歯の再発リスクを低減できると期待されています。また、精密な接着技術により、歯と差し歯の一体性を高め、隙間からの細菌侵入を防ぎます。色が合わないという問題を解決することは、審美性だけでなく、歯の健康を長期的に守るための「機能的なやりかえ」でもあるのです。
まずは専門家に「やり替えが可能か」を相談することから
「差し歯の色が合わないから、すぐにセラミックにやりかえたい」とお考えになった場合でも、まずは歯科医師による精密な診断が必要です。なぜなら、審美治療を開始する前に、土台となるご自身の歯(歯の根)の状態を確認することが最優先だからです。古い差し歯を外した際、内部で虫歯が大きく再発していたり、歯の根の先端に感染(根尖病巣)が見つかったりすることも少なくありません。この場合、色合わせ(セラミック治療)の前に、まずその原因である感染を取り除く「根管治療の再治療」が優先されます。審美的な悩みを解決し、自然な口元を取り戻すための第一歩は、「私のこの差し歯は、やりかえが可能か?」「もしやりかえるなら、どのような手順が必要か?」を専門家である歯科医師に相談し、ご自身の「現在地」を正確に知ることです。色が合わないというお悩みを、ぜひお気軽にご相談ください。
埼玉県大宮の再治療0%を追求した
審美歯科セラミック治療ガイド
監修:関口デンタルオフィス大宮
電話番号:048-652-1182
*監修者
関口デンタルオフィス大宮
*経歴
・2008年 日本大学歯学部卒業
日本大学歯学部臨床研修部入局
・2009年 日本大学歯学部補綴学第一講座入局
専修医
顎関節症科兼任
・2014年 同医局退局
関口デンタルオフィス開院
*所属学会
*スタディークラブ
・CIDアクティブメンバー(Center of Implant Dentistry)