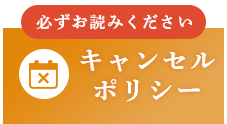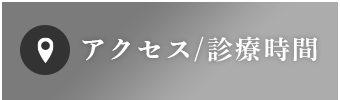「まだ早い」と思っていませんか?インプラントを後回しにするリスクとタイミングの見極め方
- 2025年10月10日
- インプラント
目次
「まだ早い」とインプラントを後回しにしていませんか?

「今はまだ、不便を感じていないから」
歯を1本失っても、特に奥歯で見えにくい場所だったり、抜歯後の痛みが治まったりすると、「食事も反対側で噛めるし、日常生活でそれほど不便を感じない」と、治療を後回しにしてしまう方は少なくありません。人間の適応能力は高く、インプラントなどの治療を受けなくても、後回しにしているうちに、その「不便さ」になんとなく慣れてしまいます。しかし、痛みや不便さを感じていない「今」このタイミングにも、お口の中では目に見えないリスクが静かに進行しています。歯が抜けた空間に向かって隣の歯が倒れ込んだり、顎の骨が痩せ始めたりしています。その小さな変化が、将来的にインプラント治療を複雑化させる原因となることを知っておく必要があります。
「手術や費用が不安で、決断のタイミングが掴めない」
インプラント治療と聞くと、「外科手術が怖い」「痛そう」「治療期間が長くて費用も高額」といったネガティブなイメージが先行し、なかなか決断に至らないというお気持ちは、非常によくわかります。こうした不安が、「本当に今がそのタイミングなのか」という迷いを生み、治療を後回しにする大きな原因となっているケースは少なくありません。しかし、知っておいていただきたいのは、その後回しにしている期間にも、お口の状態は刻々と変化しているという事実です。インプラントを埋め込むために不可欠な「顎の骨」は、歯を失った時期から痩せ始めます。いざ決断したタイミングで骨が不足していると、インプラントを埋め込むために「骨を増やす追加の手術(骨造成)」が必要となり、結果として手術のリスクやご負担(期間・費用)が、後回しにしなかった場合よりも大きくなってしまう可能性があるのです。
「もっと先の将来で考える治療だと思っている」
インプラント治療を、「入れ歯が合わなくなったご高齢の方が、最終手段として選ぶ治療」といったイメージでお持ちではないでしょうか。「自分はまだ若いから」「体力があるうちはブリッジで十分」と、インプラント治療をご自身の時期としては「まだ早い」と考え、後回しにしている方もいらっしゃいます。しかし、インプラント治療の成功において、年齢そのものよりもはるかに重要なのが「顎の骨の健康状態(骨の質と量)」です。歯を失った時期から骨は痩せ始めるため、インプラント治療の最適なタイミングは、実は「骨がまだ十分に存在する、歯を失ってから早い時期」であるとも言えます。「まだ早い」という自己判断で後回しにすることが、ご自身の顎の骨という最大の「資産」を減らしてしまうリスクにつながるかもしれません。
そもそもインプラント治療とは?(時期が関係する理由)

インプラントの基本的な仕組み(人工歯根)
インプラント治療は、歯を失った部分の顎の骨に、「人工歯根(インプラント体)」と呼ばれるチタン製のネジのようなものを外科的に埋め込む治療法です。チタンは骨と非常に親和性が高く、一定の治癒期間(時期)を経ることで、顎の骨と強固に結合します(オッセオインテグレーション)。この結合した人工歯根を土台として、その上に人工の歯(被せ物)を装着します。つまり、インプラントは「歯の根」から再現する治療法です。この「骨との結合」が治療の基盤となるため、土台である骨の状態(質と量)が治療の成否を大きく左右します。治療を後回しにすると、この土台(骨)の状態が変化してしまうリスクがあるため、治療のタイミングが重要視されるのです。
なぜ「顎の骨」に埋め込む必要があるのか
インプラント治療が他の治療法と根本的に異なるのは、失った歯の「根」の代わりを「顎の骨」に求める点です。なぜなら、自然な歯が顎の骨にしっかり支えられていたように、人工の歯も強固な土台がなければ、自然な歯に近い「噛む力」を回復させることができないからです。インプラント体を顎の骨に埋め込み、骨と結合させることで、インプラントは独立した一本の歯として機能します。この「骨に埋め込む」という仕組みこそが、インプラント治療が成功するための大前提です。したがって、治療を後回しにするリスクとして、この土台となる顎の骨が痩せてしまい(骨吸収)、いざ治療したい時期(タイミング)になった時に、インプラントを埋め込むための骨が不足している、という事態が懸念されます。
他の治療法(ブリッジ・義歯)との根本的な違い
歯を失った際の他の選択肢として「ブリッジ」と「義歯(入れ歯)」があります。これらの治療法とインプラントの根本的な違いは、「支えをどこに求めるか」です。ブリッジは、失った歯の両隣の健康な歯を削って土台にします。義歯は、残った歯にバネをかけたり、歯ぐき(粘膜)で支えたりします。どちらも「残った歯」や「歯ぐき」に負担をかけます。一方、インプラントは顎の骨に人工歯根を埋め込むため、独立しており、他の歯を削ったり負担をかけたりしません。しかし、この「骨」という土台は、歯を失った時期から痩せ始めるリスクがあります。ブリッジや義歯を選んで長期間が経過し、いざインプラントにしようと後回しにしていた場合、そのタイミングでは骨が足りなくなっている可能性があり、これがインプラント治療の時期が重要視される理由です。
インプラントを「後回し」にする最大のリスク:顎の骨が痩せていく

歯を失った瞬間から始まる「骨の吸収(廃用性萎縮)」
インプラント治療のタイミングを検討する上で、避けて通れない最大のリスクが、歯を失った部分の「顎の骨(歯槽骨)が痩せていく」ことです。歯が抜けた瞬間から、その部分の骨は「使われなくなった」と体から判断され、少しずつ吸収(後退)が始まります。これは、骨折後にギプスをしていた足の筋肉が痩せてしまうのと同じ「廃用性萎縮(はいようせいいしゅく)」と呼ばれる現象です。この骨の吸収は、歯を失った直後の時期(特に最初の1年間)に最も大きく進行すると言われています。インプラント治療を「まだ早い」と後回しにすることは、この骨の吸収を許容し、ご自身の「土台」という大切な資産を失い続ける時期を過ごすことと同義なのです。
なぜ刺激がないと骨は痩せてしまうのか
私たちの顎の骨は、自然な歯がある時期、食事などで「噛む」という刺激が歯の根(歯根)を通じて骨に伝わることで、その密度と量を維持しています。骨は、刺激(負荷)がかかることで、骨を作る細胞(骨芽細胞)と骨を溶かす細胞(破骨細胞)のバランスが保たれ、新陳代謝を繰り返しています。しかし、歯を失うと、その部分の骨には「噛む」という大切な刺激が一切伝わらなくなります。すると、体は「この骨はもう必要ない」と判断し、骨を溶かす細胞の働きが優位になります。その結果、骨は内側や高さが徐々に失われ、痩せていってしまうのです。インプラント治療を後回しにすると、この「刺激のない時期」が長引き、骨が痩せるリスクが進行してしまいます。
骨が痩せると、将来の治療がどう難しくなるのか
インプラント治療は、人工歯根(インプラント体)を、十分な「量(高さと幅)」と「質」を持つ顎の骨に埋め込むことが、長期安定の大前提です。治療を後回しにした結果、いざ「インプラントにしよう」と決断したタイミングで、この土台となる骨が痩せてしまっていると、そのままではインプラントを埋め込むことができません。この場合、インプラント手術に先立って、痩せた骨を再生させるための「骨造成(こつぞうせい)」と呼ばれる追加の外科処置(GBR法やサイナスリフトなど)が必要となります。これは、インプラントを埋め込む手術とは別に、新たな手術、治療期間の延長、そして追加の費用という、患者さんにとっての大きなリスク(負担)が増えることを意味します。後回しにしなかった早い時期であれば、この処置は不要だった可能性もあるのです。
骨だけではない。「後回し」が招くお口全体のドミノ倒し

支えを失った両隣の歯が倒れ込んでくる
インプラント治療を後回しにするリスクは、歯が抜けた場所の骨が痩せることだけではありません。歯は、お互いが隣り合うことで支え合い、現在の歯並びを維持しています。しかし、1本でも歯を失ったまま後回しにすると、その空間(スペース)に向かって、支えを失った両隣の歯が徐々に倒れ込んできます(傾斜)。後回しにしている時期が長ければ長いほど、この傾斜は顕著になります。歯が倒れ込むと、見た目の歯並びが乱れるだけでなく、傾いた歯と隣の歯との間に複雑な段差が生まれ、清掃性が著しく悪化します。その結果、プラーク(歯垢)が溜まりやすくなり、それまで健康だった歯が新たに虫歯や歯周病になるリスクが高まります。さらに、いざインプラント治療を受けようと決断したタイミングでは、この倒れ込んだ歯が邪魔になり、インプラントを入れるための十分なスペースが失われていることがあります。その場合、インプラント治療の前に、まずこの倒れた歯を矯正治療(部分矯正)で元の位置に戻す処置が必要となり、治療期間や費用のご負担が増える可能性があります。
噛み合う相手を失った歯が伸びてくる(対合歯挺出)
歯は、隣同士だけでなく、上下の歯が「噛み合う」ことでも、互いの位置を保っています。インプラント治療を後回しにする時期が長引くと、噛み合う相手の歯(対合歯)が、その空間に向かって伸びてくる(挺出)というリスクが発生します。これを専門的に「対合歯挺出(たいごうしていしゅつ)」と呼びます。例えば、下の奥歯を失ったまま後回しにしていると、上の奥歯がだんだんと下の空間に向かって下がってくるのです。歯が伸びてくると、まず歯の根(歯根)の部分が歯ぐきから露出するため、知覚過敏(冷たいものがしみる)や、酸に弱い根の部分の虫歯(根面カリエス)のリスクが高まります。さらに深刻な問題は、いざインプラント治療を受けようと決めたタイミングで、この伸びてきた対合歯が邪魔になり、インプラントの上部構造(人工の歯)を入れるための高さ(スペース)が失われてしまっていることです。その場合、インプラント治療と併せて、この伸びてしまった歯を削って高さを調整したり、場合によっては矯正治療や神経の治療が必要になったりするなど、治療が複雑化するリスクを伴います。
お口全体の噛み合わせ(咬合)のズレと負担増
歯を1本失ったまま後回しにすると、隣の歯が倒れ込み(傾斜)、向かいの歯が伸びてくる(挺出)ことは、お口全体の「噛み合わせ(咬合)」のバランスをドミノ倒しのように崩していく最大の原因となります。たった1本歯がないだけでも、私たちは無意識のうちにそこを避け、インプラントなどの治療がされていない時期は、反対側の歯でばかり噛む「片側噛み」の癖がつきやすくなります。この「後回し」の期間が長引くほど、よく使う側の健康な歯には過剰な負担が集中し続け、その歯が過度にすり減ったり、欠けたり、歯周病が悪化したりするリスクが高まります。また、全体の噛み合わせのズレが、顎の関節に不自然な負担をかけ、顎関節症(口が開けにくい、顎が痛むなど)を引き起こすリスクも否定できません。いざインプラント治療を受けようと決断したタイミングでは、この崩れてしまった全体の噛み合わせを再構築することから始めなければならず、治療が大掛かりになる可能性もあります。
インプラント治療の「タイミング」の見極め方

治療の選択肢が最も多い「抜歯後の早い時期」
インプラント治療を検討する上で、最も治療計画が立てやすく、選択肢が広がるタイミングは、「抜歯後の早い時期」であると言えます。歯が抜けた直後は、まだ顎の骨が痩せておらず(骨吸収が進行しておらず)、両隣の歯も移動を開始していないため、インプラントを埋入するための理想的な環境が残されていることが多いからです。この時期を後回しにすると、骨が痩せてしまい、いざインプラントを希望されたタイミングで骨造成(骨を増やす処置)という追加の手術リスクが必要になることがあります。また、抜歯と同時にインプラントを埋入する「抜歯即時埋入」という選択肢も、この時期ならではのものです。「まだ早い」と後回しにすることが、ご自身にとって最もシンプルだったはずの治療の選択肢を狭めてしまう可能性があるのです。
「まだ早い」は本当か?年齢との関係性
インプラント治療のタイミングについて、「まだ早い」(若すぎる)と後回しにする方もいらっしゃいます。確かに、顎の骨の成長が完了していない未成年の方(一般的に18〜20歳未満)の場合は、成長が止まるのを待つ必要があり、インプラント治療には「早すぎる時期」と言えます。しかし、顎の骨の成長が完了した成人の方であれば、「早すぎる」ということはありません。むしろ、インプラント治療のリスクは「年齢」そのものよりも、「歯を失ったまま後回しにした期間」と、それによる「骨の吸収の程度」に大きく左右されます。骨の状態が良ければ、若いうちにインプラント治療を行う方が、残存する他の歯への負担を早期に軽減できるというメリットもあります。年齢を理由に「まだ早い」と後回しにするのではなく、骨の状態が良いタイミングを逃さないことが重要です。
健康状態(持病など)がタイミングに与える影響
インプラント治療は外科手術を伴うため、お口の中の状態だけでなく、患者さんの全身の健康状態が治療のタイミングや可否に大きく影響します。例えば、糖尿病(特に血糖コントロールが不良な場合)や、重度の骨粗しょう症、血液疾患、リウマチなどの持病(全身疾患)がある場合、手術による感染リスクや、インプラントと骨との結合(オッセオインテグレーション)が妨げられる可能性があります。また、喫煙習慣は成功率を下げる大きなリスク因子です。こうした持病があるからといってインプラントが不可能とは限りませんが、まずはかかりつけの内科医と歯科医師が連携し、病状が安定している時期を見極めることが不可欠です。「まだ早い」と後回しにしているうちに、将来的に全身の健康状態が悪化し、手術のリスクが高まる可能性も考慮し、健康状態が良好なタイミングで相談することが望まれます。
「後回し」にしてしまった…もうインプラントは無理?

痩せてしまった骨を補う「骨造成(GBR・サイナスリフトなど)」とは
インプラント治療を長期間後回しにした結果、顎の骨が痩せてしまっている(骨吸収が進んでいる)場合でも、インプラント治療を諦める必要はありません。不足した骨の量を補うための「骨造成(こつぞうせい)」という処置があります。これは、インプラントを埋め込むのに必要な骨の高さや幅が足りない場合に、ご自身の骨や骨補填材を用いて骨を再生させる方法です。代表的な方法に、骨が不足している部分に膜を覆って骨の再生を促す「GBR法」や、上顎の奥歯の上にある空洞(上顎洞)に骨補填材を入れる「サイナスリフト」「ソケットリフト」などがあります。これらの骨造成を併用することで、後回しにした時期が長く骨量が減っていても、インプラント治療が可能になるケースは多くあります。ただし、これは追加の外科処置となるため、治療期間の延長や費用、手術リスクが増える可能性はあります。最適なタイミングを逃したリスクとも言えます。
倒れた歯を戻す「部分矯正」が必要なケース
歯を失ったまま後回しにしている時期が長引くと、抜けたスペースに向かって両隣の歯が倒れ込んでくる(傾斜する)ことがあります。いざインプラント治療をしようと決断したタイミングで、この傾斜が大きく進行していると、インプラント本体は埋め込めても、その上に装着する人工の歯(被せ物)を作るための十分なスペースが失われていることがあります。このような場合、インプラント治療を開始する前に、まず倒れ込んだ歯を元の位置に起こすための「部分矯正」が必要となることがあります。これは、数本の歯に限定して矯正装置(ブラケットやワイヤー、マウスピースなど)を一定期間装着し、インプラントのためのスペースを確保する治療です。後回しにした結果、本来は不要だったはずの矯正治療というステップが増え、全体の治療時期が延長し、費用も別途かかるリスクが生じます。
「後回し」にした分、治療が複雑化する可能性
結論として、インプラント治療を「まだ早い」と後回しにすることは、多くの場合、治療の選択肢を狭め、プロセスを複雑化させるリスクを高めます。後回しにした時期が長ければ長いほど、(1)顎の骨が痩せてしまい「骨造成」が必要になるリスク、(2)隣の歯が倒れ込み「部分矯正」が必要になるリスク、(3)噛み合う相手の歯が伸びてきて、その歯の調整が必要になるリスクなどが考えられます。これらは、インプラント治療そのものが不可能になるわけではなくても、追加の手術、治療期間の延長、費用の増加といった形で、患者さんのご負担が増えることを意味します。最適なタイミング(例えば抜歯後早い時期など)で治療を開始していれば、よりシンプルに進められた可能性があったのです。まずは現在の状況を知るためにも、早めに専門家にご相談いただくことが、これらのリスクを最小限に抑える鍵となります。
インプラント治療の医院選びで考慮すべき点

精密診断を支える設備(CTなど)の重要性
インプラント治療の成功は、手術前の「精密な診断」に基づいた「正確な治療計画」にかかっています。特に、人工歯根(インプラント体)を埋め込む顎の骨の状態(量や質、神経や血管の位置)を三次元的に把握することは、安全な手術のために不可欠です。従来の二次元レントゲンだけでは得られる情報に限界があり、インプラント治療においては「歯科用CT」による撮影が重要な役割を果たします。歯科用CTは、顎の骨の厚みや高さ、神経管までの距離などをミリ単位で正確に計測できるため、インプラントを埋め込む最適な位置や角度、サイズを決定する上で極めて有効です。インプラント治療を後回しにした時期が長い場合、骨が痩せているリスクが高いため、CTによる骨の状態の正確な評価はさらに重要となります。CT設備を備え、精密診断に力を入れている医院を選ぶことは、手術のリスクを低減し、より適切な治療タイミングを見極める上で考慮すべき点です。
術者の経験と治療実績
インプラント治療は、外科手術を伴う専門性の高い治療分野です。歯科医師であれば誰でも同じレベルで行えるわけではなく、術者の知識、技術、そして経験が治療結果に大きく影響します。医院を選ぶ際には、担当する歯科医師がインプラント治療に関する十分な研修を受け、豊富な経験と実績を有しているかを確認することも大切です。例えば、所属する学会(日本口腔インプラント学会など)の専門医・指導医などの資格は、一つの目安となるでしょう。また、これまでにどれくらいの症例を手がけてきたか、特に後回しにした結果、骨造成などの難易度の高い処置が必要になったケースへの対応経験なども参考になります。経験豊富な術者は、さまざまな状況に応じた適切な治療計画を立案し、手術中の偶発症への対応や、術後の管理においても的確な判断が期待できます。リスクを抑え、安心して治療を任せられるタイミングを見極めるためにも、術者の経験は重要な要素です。
治療後の長期的なメンテナンス体制
インプラント治療は、人工の歯(被せ物)が入ったら終わりではありません。そのインプラントが長期的に安定して機能するためには、治療後の「定期的なメンテナンス」が不可欠です。インプラント自体は虫歯にはなりませんが、周囲の歯ぐきや骨は、自然な歯と同様に、あるいはそれ以上に歯周病に似た状態(インプラント周囲炎)になるリスクがあります。このインプラント周囲炎が進行すると、最悪の場合、インプラントが抜け落ちてしまう原因となります。このリスクを予防するためには、ご自宅での丁寧なセルフケアに加え、歯科医院での定期的な専門的クリーニングや、噛み合わせのチェック、レントゲンでの骨の状態の確認などが欠かせません。治療を後回しにしたかどうかに関わらず、治療後のメンテナンスプログラムがしっかり確立されており、長期的に患者さんのお口の健康をサポートしてくれる体制が整っている医院を選ぶことが、インプラントを長持ちさせる上で非常に重要です。
インプラントの「時期」と「リスク」に関するよくあるご質問

Q.やはり手術が怖いのですが、痛みは?
A.インプラント治療は外科手術ですので、「怖い」「痛そう」と感じるのは自然なことです。まず、手術中は局所麻酔を十分に行いますので、処置中に痛みを感じることはほとんどありません。麻酔の感覚は、抜歯など通常の歯科治療と同様とお考えください。手術後の痛みや腫れについては個人差がありますが、処方される鎮痛剤や抗生剤を適切に服用いただくことで、多くの場合、日常生活に大きな支障なくコントロール可能です。痛みは通常、手術当日か翌日をピークに数日で落ち着きます。手術への不安が非常に強い方には、リラックスした状態で治療を受けられる「静脈内鎮静法」などの選択肢もあります。「手術が怖い」という理由で治療を後回しにされている間に、顎の骨が痩せるなどのリスクが進行してしまう可能性も考慮しなくてはなりません。適切なタイミングで治療を受けるためにも、まずは痛みや不安について遠慮なくご相談ください。
Q.治療期間はどれくらいかかりますか?
A.インプラントの治療期間は、お口の状態や治療計画によって異なりますが、一般的には数ヶ月単位の時期が必要です。まず精密検査・診断を行い、インプラント体を顎の骨に埋め込む手術(1次手術)を行います。その後、インプラントと骨がしっかり結合するのを待つ治癒期間(オッセオインテグレーション)が、下顎で約2〜4ヶ月、上顎で約3〜6ヶ月程度かかります。骨と結合した後に、人工の歯(上部構造)を装着して治療完了となります。ただし、これは骨の状態が良い場合の目安です。歯を失ってから後回しにした時期が長く、顎の骨が痩せてしまっている場合は、「骨造成(骨を増やす処置)」が必要となることがあります。その場合、骨造成の治癒期間がさらに数ヶ月加わるため、全体の治療期間が1年近く、あるいはそれ以上になるリスク(可能性)があります。適切なタイミングで治療を開始することが、結果的に治療期間の短縮につながることもあります。
Q.高齢でもインプラントは可能ですか?年齢制限は?
A.インプラント治療に、基本的に「上限」の年齢制限はありません。ご高齢の方でも、全身の健康状態が安定していれば治療を受けていただくことは可能です。年齢そのものよりも重要なのは、「骨の状態(質と量)」と「全身疾患の有無とそのコントロール状態」です。例えば、重度の糖尿病(血糖コントロールが不良)、骨粗しょう症(特定の薬剤を使用中)、心疾患などがある場合は、手術のリスクが高まるため、かかりつけ医と歯科医師が連携し、慎重に適応を判断します。「まだ早い」と後回しにしているうちに、加齢によって全身疾患のリスクが高まったり、骨の状態が悪化したりする可能性も考慮すべきです。ご高齢の方でもインプラントによって「しっかり噛める」生活を取り戻し、QOL(生活の質)を向上させている方は多くいらっしゃいます。年齢を理由に最適なタイミングを逃すのではなく、まずは健康状態を含めてご相談ください。なお、顎の成長が完了していない若年者(一般的に18歳未満)には適用できません。
Q.治療の成功率と、失敗のリスクは?
A.適切な診断・計画のもと、経験豊富な術者が行い、患者さんご自身の健康状態やメインテナンス状況が良好であれば、インプラント治療の成功率は長期的に見て非常に高い(一般的に10年生存率で90%以上)と報告されています。しかし、外科手術である以上、リスクが全くゼロではありません。考えられるリスク・偶発症としては、手術に伴う神経・血管の損傷(まれですが、下唇の麻痺など)、術後の感染、インプラントと骨が結合しない(オッセオインテグレーション不全)、長期的な問題としてインプラント周囲炎(インプラントの歯周病)などが挙げられます。これらのリスクを最小限に抑えるためには、(1)CTなどを用いた精密な術前診断、(2)適切な手術手技、そして(3)治療後の定期的なメンテナンスが不可欠です。治療を後回しにした時期が長く、骨の状態が悪化していると、手術の難易度が上がり、リスクが高まる可能性も否定できません。適切なタイミングでの治療開始と、治療後の継続的なケアが、長期的な成功の鍵となります。
「まだ早い」から「今が最適」へ。決断のための第一歩

「後回し」のリスクと「早期決断」のメリットの比較
インプラント治療を「まだ早い」と後回しにすることで生じる主なリスクは、(1)顎の骨が痩せてしまい、骨造成が必要になる可能性、(2)隣の歯が倒れ込み、部分矯正が必要になる可能性、(3)全体の噛み合わせが崩れ、治療が複雑化する可能性です。これらは、結果的に治療期間の延長や費用負担の増加につながります。一方、「早期決断」のメリットは、これらのリスクを最小限に抑えられる点にあります。抜歯後など、骨や周囲の歯の状態が良い時期(タイミング)であれば、インプラント治療がよりシンプルに進み、体への負担も少なく済む可能性が高まります。後回しにするデメリットと、早期に相談・決断するメリットを比較衡量し、ご自身にとって最適な時期を見極めることが大切です。
選択肢が多いうちに相談する重要性
インプラント治療の決断を後回しにするということは、無意識のうちにご自身の治療の「選択肢」を狭めてしまっている可能性があります。歯を失った時期が早いほど、顎の骨は十分に残っており、周囲の歯の移動も少ないため、インプラント治療における選択肢(例えば、抜歯即時埋入や、骨造成不要なシンプルな手術など)は豊富にあります。しかし、後回しにした期間が長引けば長引くほど、骨が痩せたり歯が動いたりするリスクが進行し、選択できる治療法が限られたり、より複雑な処置(骨造成や矯正)が必要になったりします。「まだ迷っている」「決断できない」というタイミングであっても、まずは専門家である歯科医師に相談し、「現在の状態」と「今ならどのような選択肢があるのか」を知ることが重要です。選択肢が多い時期に情報を得ることで、将来後悔しないための判断が可能になります。
再びしっかり噛める未来への投資
インプラント治療は、保険適用外のため費用負担が伴います。しかし、それは単なる「出費」ではなく、失われた「噛む」という大切な機能を取り戻し、将来の健康を守るための「投資」と捉えることもできます。歯を失ったまま後回しにすると、しっかり噛めないことによる消化器への負担、栄養バランスの偏り、残った歯への過剰な負担、そして顎の骨が痩せるリスクなど、全身の健康に様々な影響が及びます。これらが将来的に、より大きな医療費につながる可能性も否定できません。インプラント治療によって、再び何でも気にせず美味しく食事ができる喜びや、自信を持って笑える日常を取り戻すことは、QOL(生活の質)を大きく向上させます。治療のタイミングを後回しにせず、適切な時期に判断することは、ご自身の未来の健康と豊かな生活への価値ある投資と言えるでしょう。
埼玉県大宮の再治療0%を追求した
審美インプラント治療ガイド
監修:関口デンタルオフィス大宮
電話番号:048-652-1182
*監修者
関口デンタルオフィス大宮
*経歴
・2008年 日本大学歯学部卒業
日本大学歯学部臨床研修部入局
・2009年 日本大学歯学部補綴学第一講座入局
専修医
顎関節症科兼任
・2014年 同医局退局
関口デンタルオフィス開院
*所属学会
*スタディークラブ
・CIDアクティブメンバー(Center of Implant Dentistry)