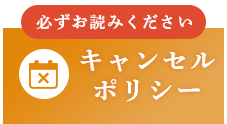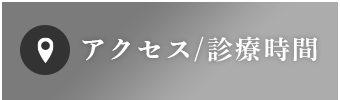即時埋入できる人・できない人|インプラント治療の適応条件とは?
- 2025年4月11日
- インプラント
目次
即時埋入インプラントとは?基本から知っておきたいこと

即時埋入と通常埋入の違いとは?
インプラント治療には大きく分けて「通常埋入(遅延埋入)」と「即時埋入」の2つのアプローチがあります。通常埋入とは、抜歯後に数か月の治癒期間を経てからインプラントを埋め込む方法。一方、即時埋入は、抜歯と同じタイミングでインプラント体(フィクスチャー)を埋め込む治療法です。
即時埋入の最大の特徴は、治療のステップが短縮されること。本来、抜歯から骨や歯ぐきが回復するまで3〜6か月の待機期間を設けるのが一般的でしたが、それを省略することで、手術回数や通院回数を減らすことが可能になります。患者様にとっては身体的・心理的な負担の軽減につながり、治療のモチベーションを保ちやすい点が魅力です。
ただし、どんなケースでも即時埋入が可能というわけではなく、骨の状態や炎症の有無など、慎重な診断が求められます。この違いを理解することが、納得のいくインプラント治療への第一歩です。
抜歯と同時にインプラントを埋め込むメリット
即時埋入の最大のメリットは、抜歯後の治癒を待たずに治療が進行するため、治療期間が短く済むことにあります。しかし、利点はそれだけではありません。特に審美領域(前歯など)の場合、抜歯直後の歯槽骨と歯肉のボリュームが十分に保たれている状態で埋入を行うことで、自然な歯ぐきのラインや歯の形を再現しやすくなるのです。
また、抜歯直後の空隙をインプラントで満たすことにより、歯槽骨の吸収を抑える効果も期待できます。通常、抜歯後は骨が時間とともに痩せていくため、骨造成や歯ぐきの整形が必要になることがありますが、即時埋入によってこれらの処置を回避または軽減できる場合があります。
加えて、手術回数が減ることで患者様の身体への負担や精神的ストレスも軽減され、結果として治療継続率の向上にも寄与しています。ただし、初期固定が十分に得られることが条件であり、治療を急ぐあまりに無理をすると、失敗のリスクが高まる点には注意が必要です。
治療期間の短縮だけではない利点
「早く終わる」だけが即時埋入のメリットではありません。特に見た目に関して敏感な方にとって、抜歯直後からの即時対応が心理的な安心感にもつながります。従来の治療法では、抜歯後に仮義歯や入れ歯で過ごす期間が生じるため、不自由さや審美的なストレスを感じることが少なくありません。
即時埋入では、適切な条件下で仮歯(プロビジョナル)を早期に装着できる場合もあり、見た目と機能の回復が同時に叶う点は大きなメリットです。特に前歯部の治療においては、周囲の歯ぐきの形態や唇との調和を自然に保つため、抜歯直後の処置が理想的なタイミングとなるケースがあります。
さらに、治療工程が簡略化されることで通院回数も少なくなり、遠方からの通院や多忙なライフスタイルの方にとっても利便性が高い治療選択肢となります。ただし、即時埋入は「適応条件」が限られるため、必ずしもすべての患者様に適用できるわけではありません。
そのため、インプラント治療をご検討の際は、まずはご自身の口腔内の状態を正確に診断し、信頼できる歯科医師と相談しながら最適な治療計画を立てることが大切です。
どんな人が即時埋入の適応になるのか?

顎の骨の厚み・高さが十分にあることが条件
即時埋入を行うには、インプラント体がしっかり固定されるだけの骨量が必要不可欠です。抜歯直後の歯槽骨(歯を支えていた骨)は、時間が経つと吸収されてしまう性質があるため、骨の幅や高さが不足していると、初期固定が得られず、インプラントが動いてしまうリスクが高まります。
とくに重要なのが、骨の「質」だけでなく「量」です。骨密度が高い(緻密で硬い)だけでなく、十分な厚みがあることで、インプラントの安定が得られやすくなります。逆に、骨が薄くて柔らかい場合は、埋入後の安定が得にくく、治療後にインプラントがぐらつく可能性もあります。
また、インプラントを埋め込む部位が上顎か下顎かでも条件は異なり、上顎は骨が柔らかくて吸収されやすいため、特に慎重な診断が求められます。CTによる骨の三次元評価が行われ、医師が「初期固定が得られる」と判断した場合に限って、即時埋入の適応となります。
歯周病や感染のない清潔な口腔環境
もうひとつの重要な条件は、抜歯部位に炎症や感染がないことです。たとえば、歯周病が進行していて歯ぐきや骨に炎症が残っている場合、そのままインプラントを埋め込むと、細菌感染によって治癒が阻害され、インプラントが脱落するリスクが非常に高くなります。
また、虫歯が進行して歯の根に膿がたまっているケースや、根尖病変(根の先にできる膿の袋)などがある場合も、即時埋入は避けるべきです。これらは、顎の骨や歯ぐきの周囲組織が健全であることが前提の治療法であるため、細菌の温床となる状態では成功率が著しく下がります。
したがって、即時埋入を検討する際は、まず歯周病や感染症の有無を徹底的にチェックし、必要に応じて事前に歯周治療や根管治療を完了させる必要があります。歯科医院では、レントゲンやCT撮影、歯周ポケット検査などを通して、口腔内の清浄度を評価し、問題がないと判断された場合にのみ適応とされます。
抜歯部位の状態が安定していることが前提
即時埋入が成功するためには、抜歯する歯の状態や抜歯後の組織の反応も大きく影響します。特に、抜歯がスムーズに行われ、周囲の歯槽骨や歯肉がほとんど損傷せずに温存できるかどうかが、適応の大きな判断基準です。
たとえば、抜歯時に骨が大きく崩れたり、歯根が割れていて骨の一部が感染していたりすると、インプラントを安定して埋め込むことは困難です。抜歯窩(ばっしか:抜いた歯の穴)の壁がすべて残っており、骨が均等に存在していることが、理想的な状態といえます。
さらに、抜歯直後は一時的に出血や炎症が生じやすいため、外科的処置に対する組織の反応も予測する必要があります。患者様が健康な免疫状態であること、そして喫煙や糖尿病などの全身的なリスク因子がないことも、治癒の質を左右します。
また、上顎洞(副鼻腔)に近い上顎の奥歯や、神経の近くにある下顎臼歯部などは、骨の位置関係から即時埋入が難しいケースもあります。こうした部位では、骨造成やサイナスリフトを含めた治療計画が必要になるため、即時埋入の適応からは外れることがあります。
そのため、即時埋入の可否は歯科医師の診断に完全に委ねられますが、患者様としても、抜歯部位の状態が良好であるかどうかを理解することが、治療選択において重要な判断材料になるといえるでしょう。
即時埋入ができないケースとは?

骨の吸収が進んでいる、骨量が不足している場合
即時埋入インプラントを成功させるには、インプラント体がしっかりと初期固定される必要があります。そのためには十分な骨の厚みと高さが必須です。しかし、抜歯予定の歯に歯周病や根の炎症などが長期間存在していた場合、すでに骨が大きく吸収されているケースが少なくありません。
特に、歯周病が重度に進行している患者様は、歯を支える骨(歯槽骨)が広範囲に失われていることが多く、インプラントの固定が困難になります。また、歯根の周囲に膿がたまっていると、その部分の骨は感染により溶けており、除去が必要になるため、さらに骨量が不足します。
このような場合は、即時埋入ではなく、まず抜歯後に骨の再生を待つ「遅延埋入」が推奨されることが多く、必要に応じてGBR(骨誘導再生)やサイナスリフトといった骨造成処置を先に行うことが前提になります。骨の状態によっては、インプラント自体が適応外となることもあり、慎重な診断が必要です。
強い炎症や膿がある抜歯部位
インプラントの即時埋入は、抜歯と同時に人工歯根を骨の中へ埋め込む外科的処置であるため、埋入部位が無菌に近い清潔な状態であることが絶対条件です。しかしながら、虫歯の悪化や根尖性歯周炎などで歯の根の先に膿がたまっていたり、歯周病が重度化して周囲に慢性的な炎症があるような場合、インプラント周囲への細菌感染のリスクが非常に高くなります。
特に、根の先端や周囲に広がった感染を完全に除去できないと、せっかく埋入したインプラントが骨と結合せず、脱落や周囲炎の原因になります。また、炎症が強い部位では血流や細胞の修復機能が損なわれており、インプラント周囲の組織再生もスムーズに進まなくなります。
このため、感染のある抜歯部位に対しては、まずは根管治療や炎症の鎮静化を図った上で抜歯を行い、その後に骨や歯ぐきの状態が落ち着いてからインプラントを検討する「ステージドアプローチ(二段階法)」が選択されます。即時埋入を優先しすぎると、結果的に治療が長引いたり、失敗のリスクが高まるため、医師の判断を重視することが大切です。
全身疾患や生活習慣が治癒を妨げる場合
即時埋入は、抜歯・埋入・治癒といった複数のプロセスが一度に進行するため、体の治癒力がしっかりと機能していることが前提になります。そのため、患者様の全身状態や生活習慣も大きく関わってきます。たとえば、糖尿病を患っている方は、血糖値のコントロール状態が悪いと、傷口の治癒が遅れたり、感染のリスクが高くなることが知られています。
また、喫煙も大きなリスク因子のひとつです。ニコチンは血流を低下させ、歯ぐきや骨の再生を妨げるため、インプラントの結合率が低下するとともに、術後の炎症や周囲炎が起こりやすくなります。そのため、禁煙ができない患者様は、即時埋入だけでなくインプラント治療そのものが適応外になるケースもあるのです。
ほかにも、骨粗しょう症治療薬(ビスホスホネート製剤)を服用している方や、重度の心疾患・肝疾患・免疫抑制状態にある方は、外科手術自体のリスクが高まるため、即時埋入には慎重な判断が必要です。
このように、口腔内の状態だけでなく、全身の健康状態や日常の習慣も含めて総合的に診断することが、即時埋入が可能かどうかを判断するカギになります。患者様自身も、持病や服用薬などを正確に申告し、医師との信頼関係を築くことが、成功の第一歩といえるでしょう。
骨の状態がカギ!CT検査でわかる適応かどうか

骨の幅・高さ・密度を正確に診断するCTの役割
インプラント治療、特に即時埋入を検討する際には、顎の骨の「幅」「高さ」「密度」を正確に把握することが非常に重要です。従来のレントゲン(パノラマ撮影)では平面的な情報しか得られませんが、三次元で立体的に構造を確認できる「CT(コンピュータ断層撮影)」では、骨の状態を詳細に診断することが可能です。
たとえば、即時埋入を成功させるためには、インプラントをしっかり支えるための骨が十分な厚み(幅)と高さを持っているかどうかが判断基準になります。CTを使えば、抜歯予定の歯の周囲の骨が均等に存在しているか、骨の内側(口蓋側)や外側(頬側)に骨欠損がないかまで、立体的に評価できます。
さらに、骨の「質」、つまり密度(硬さ)もCTデータで推測可能です。骨密度が高すぎるとドリルが通りにくく、逆に低すぎると初期固定が得られないという問題があるため、治療前に知っておくことがリスク管理につながります。CT診断は、単に可否を判断するだけでなく、どの位置・角度で埋入するかという戦略的計画を立てるための必須ツールなのです。
骨の状態によって変わる埋入角度と深さの判断
即時埋入を成功させるためには、ただ「埋める」だけでは不十分です。骨の状態に応じて、インプラントの埋入角度や深さを微調整することが、長期的な成功に大きく影響します。たとえば、骨の厚みが不足している場合は、わずかな角度の違いで骨を貫通してしまうリスクがあり、CTでの精密診断がなければ判断は難しいでしょう。
また、下顎の奥歯にある「下顎管(神経)」や、上顎の奥にある「上顎洞(副鼻腔)」など、重要な解剖学的構造を避けて埋入する必要がある部位では、CTによる三次元的な位置関係の把握が絶対に必要です。誤って神経や洞を傷つけてしまうと、麻痺や慢性副鼻腔炎などの重篤なトラブルを招く恐れがあります。
CTを使った「逆算的計画(リバースプランニング)」では、最終的に理想的な噛み合わせや見た目が得られるように、インプラントの埋入位置・角度・深さを事前に綿密にシミュレーションします。そのため、CT診断は単なる適応判断だけでなく、治療精度を高める重要な設計工程とも言えます。
シミュレーションによるリスク回避の重要性
即時埋入は、抜歯と同時にインプラントを埋め込むため、その場での判断力と手技の精度が大きく問われる治療法です。しかし、CTによる術前シミュレーションを活用することで、ほぼ全ての処置内容を事前に計画でき、偶発的なリスクを最小限に抑えることができます。
たとえば、抜歯した部位の骨に少しでも薄い部分があれば、どの方向に角度を調整すればより安定性が増すのか、インプラントの長さや太さはどのサイズが適切か、他の歯との距離はどれくらいあるかなど、数値的根拠に基づいて決定できるのがシミュレーションの最大の強みです。
また、シミュレーションデータを元に「サージカルガイド」と呼ばれる埋入位置を誘導するテンプレートを作製することもできます。これを使えば、埋入時のズレや誤差がほぼゼロになり、術者の経験に頼りすぎない、安全で再現性の高い手術が可能になります。
特に、即時埋入は骨へのダメージを最小限にしながら行う必要があるため、骨の形態を事前に把握しておくことで不要な切開や掘削を避け、治癒期間や腫れ・痛みの軽減にもつながります。このように、CT診断と術前シミュレーションの活用は、即時埋入の成功率を高めるうえで不可欠なプロセスとなっています。
即時埋入を成功させるには?外科的技術と治療計画

埋入ポジションと初期固定の確保が成否を分ける
即時埋入インプラントの成功には、「どこに、どの角度で、どれだけの深さで埋めるか」という埋入ポジションの正確さが極めて重要です。通常の遅延埋入では、抜歯後の骨が治癒した状態での埋入になるため比較的自由度がありますが、即時埋入では抜歯直後の骨の形態に合わせて埋入を行う必要があるため、難易度が高くなります。
最大のポイントは「初期固定の確保」です。これは、インプラントが骨と結合するまでの間にぐらついたり動いたりしないよう、一定以上の締結力(トルク)で骨に固定されているかどうかを指します。十分な初期固定が得られないと、骨との結合(オッセオインテグレーション)がうまく進まず、最終的にインプラントが脱落してしまうリスクが高くなります。
抜歯直後の歯槽骨はまだ柔らかいことも多く、スクリューのようにねじ込むインプラントが滑らずに安定するには、適切なドリリング(穴あけ)と挿入角度、圧力の調整が必要不可欠です。この微細な調整は術者の経験と手技に依存する部分も大きく、熟練した歯科医師による手術であることが、即時埋入を安全に行う最低条件といえるでしょう。
サージカルガイドの活用と手術精度の向上
現在のインプラント治療では、デジタル技術の活用によって手術の精度を高める取り組みが進んでおり、その代表的なものが「サージカルガイド」です。これは、CT撮影で得た患者様の顎のデータをもとに、埋入位置・角度・深さをシミュレーションし、その情報を反映させた「埋入テンプレート」を作製して、実際の手術時に使用するものです。
サージカルガイドを使うことで、歯科医師の手の感覚だけに頼らず、事前に計画した通りの精密な位置にインプラントを正確に埋入することができます。これにより、神経や上顎洞などのリスク部位を避けながら、安全で短時間の手術が可能となり、患者様への身体的負担も最小限に抑えられます。
とくに即時埋入のように、骨の条件や時間制限が厳しい症例では、1ミリ単位の誤差が初期固定の成否に直結するため、サージカルガイドの活用は治療の質を大きく左右します。また、術者の技量だけでなく、デジタル機器やシステムの導入状況も医院選びのひとつの指標になるでしょう。
なお、サージカルガイドの精度を最大限に活かすためには、術前のCT診断と診査、模型や口腔内スキャンによる正確な情報収集が前提となります。こうした工程をしっかりと踏んだ治療計画が、安心・安全な即時埋入インプラントの土台を支えています。
担当医の経験と技術レベルが結果を左右する
即時埋入は、インプラント治療の中でも特に高度な技術と経験が求められる治療法です。抜歯と同時にインプラントを入れるという一見シンプルな手順ですが、その裏では骨や歯肉の状況を瞬時に把握し、術中に柔軟な判断を行う必要があります。
たとえば、手術中に予期せぬ骨の欠損が見つかった場合、インプラントの埋入位置を変えるか、骨造成に切り替えるかの判断を瞬時に下さなければなりません。また、初期固定が十分に得られないと判断した場合は、即時埋入から遅延埋入へ計画を変更するという冷静な決断も求められます。
これらは、シミュレーションや準備だけではカバーしきれない「現場対応力」であり、歯科医師の知識・経験・技術力が問われる場面です。そのため、即時埋入を希望される場合は、インプラント症例の豊富な実績を持つ歯科医院を選ぶことが極めて重要です。
また、患者様にとっても、事前の説明や術後のフォローを含めたトータルでの信頼関係が構築できる歯科医師に相談することが、安心して治療を進める大きな鍵となるでしょう。
審美性重視の場合に適応になるケースとは?

前歯部での抜歯即時埋入の目的と難易度
即時埋入インプラントのなかでも、とくに審美性が求められる「前歯部」での治療は、目的が明確である一方、技術的に非常に高度な領域です。前歯は日常生活において常に人目に触れる部位であり、「見た目」に対する患者様の期待が高く、歯の形や位置、歯ぐきとの境目の自然さなど、細部にわたって仕上がりの美しさが求められます。
このような美しさを実現するために、抜歯と同時にインプラントを埋入し、歯ぐきの形やボリュームを保ちながら治療を進める“即時埋入”が有効な選択肢となることがあります。なぜなら、抜歯後に時間をおくと、歯ぐきや骨が痩せてしまい、最終的な見た目に影響するからです。
ただし、見た目を保ちたいからといって、誰にでも適応できるわけではありません。骨と歯ぐきの条件が揃い、外科的な難易度を正確に見極められる術者のもとで行われる必要があります。見た目を重視するからこそ、安全性と予後の安定性を両立させるための綿密なプランニングが欠かせないのです。
歯ぐきのボリュームを保つタイミングの重要性
審美性に直結するもう一つの要素が、「歯ぐきのボリューム(厚みと高さ)」です。抜歯後、歯を支えていた骨とそれを覆う歯肉は、何もしなければ自然と吸収されていきます。とくに前歯部では、頬側の骨が非常に薄く、早い段階で形が崩れてしまうことが多いため、歯ぐきの形態が維持できる“抜歯直後”が非常に重要なタイミングになります。
即時埋入は、抜歯と同時にインプラントを骨に埋め込むことで、骨と歯肉の崩壊を最小限にとどめ、自然な輪郭を保つことができるという利点があります。さらに、ヒーリングアバットメントやプロビジョナルレストレーションを併用することで、歯ぐきを希望する形に誘導しながら治療を進めることも可能です。
とくに笑ったときに歯ぐきが見える「ガミースマイル」の傾向がある方では、歯ぐきの形状が与える印象は極めて大きく、慎重なデザインが求められます。したがって、審美性を最優先する場合、歯科医師が“歯と歯ぐきの調和”をいかに理解し、術前・術中・術後にわたってコントロールできるかが鍵となるのです。
見た目と機能の両立には術前準備が不可欠
審美性を確保するためには、ただインプラントを埋め込むだけでは不十分です。「どこに、どう見せるか」を考え抜いた術前準備と、機能面を妥協しないバランス感覚が必要不可欠です。インプラントは見た目を再現するだけでなく、長く噛む力を支える存在であるため、強度や清掃性、周囲の組織との調和も同時に考慮しなければなりません。
具体的には、CTや口腔内スキャンなどを用いたシミュレーションによって、最終的な歯の位置や形をあらかじめ設計し、その位置にインプラントを正確に配置できるよう手術計画を立てる「リバースプランニング」が基本となります。これにより、審美的かつ機能的に優れた仕上がりが実現します。
また、歯ぐきの厚みが足りない場合は、歯肉移植や結合組織移植といった補助手術を併用することで、自然なボリュームを回復することも可能です。インプラント治療においては、天然歯のような仕上がりを追求するために、多角的なアプローチが必要です。
さらに、患者様とのコミュニケーションも極めて重要です。色調・形態・微妙な印象に関する希望を十分にヒアリングした上で、医師側が「再現可能な範囲」を明確に説明し、共通認識を持って治療を進めることが、満足度を高めるカギとなります。
治療後の注意点とメンテナンスの必要性

埋入直後の負担を避けるための生活指導
即時埋入インプラントの手術直後は、骨とインプラントがしっかりと結合(オッセオインテグレーション)するまでの非常に大切な期間です。この期間中にインプラントに過剰な負担がかかると、固定が不安定になり、結合がうまくいかない原因になります。とくに初期の数日〜数週間は、「静かに治癒させること」が最も重要なポイントです。
術後すぐは、硬いものや粘着性のある食べ物を避け、反対側で噛むように意識しましょう。また、傷口を触ったり、舌でインプラント部分を押したりするのも避ける必要があります。治療直後に仮歯を装着した場合、その仮歯がしっかり固定されていないと、知らぬ間にインプラント体に力が加わってしまう可能性があるため注意が必要です。
加えて、術後の入浴や運動は一時的に控えたほうが無難です。血流の急激な上昇により出血が再開する可能性があるため、少なくとも手術当日は安静に過ごすことを推奨します。アルコールや喫煙も血流や治癒能力に悪影響を与えるため、術後1週間は避けるよう指導されることが一般的です。
仮歯使用中のケアと定期チェックの重要性
即時埋入の多くでは、治癒期間中に「仮歯(プロビジョナルレストレーション)」を使用して審美性や噛み合わせを一時的に回復することがあります。この仮歯の役割は単に見た目を保つだけでなく、歯ぐきの形を整える、咬合圧(噛む力)を調整するなど多岐にわたります。だからこそ、仮歯の管理はとても重要です。
まず、仮歯は強度や安定性が本物の歯や最終的な被せ物ほど高くないため、無理な力をかけないことが前提です。固い食材を噛む、前歯で袋を開けるといった行為は避けましょう。また、仮歯の表面は細菌が付着しやすいため、柔らかめの歯ブラシで優しく磨く、デンタルフロスや歯間ブラシでの清掃を欠かさないといったケアを毎日継続することが必要です。
仮歯の使用期間中は、歯科医院での定期的なチェックが不可欠です。噛み合わせに問題が出ていないか、歯ぐきの状態に炎症がないか、インプラントに過負荷がかかっていないかを細かく確認します。とくに即時埋入では、初期固定が重要な鍵を握るため、一見問題なく見えても数週間ごとの診察が推奨されます。
このように、仮歯の期間も「治療の一部」としてしっかり管理することで、最終補綴物(セラミックなど)の装着後も良好な状態が長続きしやすくなります。
インプラント周囲炎を防ぐための予防管理
インプラントは人工物であるため虫歯にはなりませんが、周囲の歯ぐきや骨に炎症が起きる「インプラント周囲炎」というトラブルには常に注意が必要です。これは天然歯の歯周病に似ていますが、進行が早く、自覚症状が乏しいまま骨の吸収が進むことが多いため、発見が遅れるとインプラントの脱落に至るリスクがあります。
インプラント周囲炎の予防には、毎日のセルフケアと歯科医院での定期メンテナンスが両輪となって機能することが不可欠です。まず、セルフケアとしては歯ブラシだけでなく、インプラント専用のフロスや歯間ブラシ、洗口液の活用が効果的です。インプラントの周囲は天然歯と比べて歯ぐきとの結合が弱いため、プラーク(細菌のかたまり)が入り込みやすく、注意が必要です。
また、3〜6ヶ月ごとの定期検診では、歯周ポケットの深さ、出血の有無、プラークの付着状況、咬合の確認などが行われます。必要に応じて、PMTCやインプラント周囲の超音波洗浄、レーザー治療などを受けることで、炎症の芽を早めに摘み取ることができます。
とくに即時埋入は、周囲の骨や歯ぐきの変化がダイレクトに影響するため、日常的な予防意識と医師との連携がそのまま治療の成否に直結します。美しく快適な口元を長く保つためにも、「埋入後が本当のスタート」と捉え、継続的なケアを欠かさないことが最も重要です。
他の治療法との違いと比較

通常の二段階埋入法との主な違い
インプラント治療には大きく分けて「即時埋入」と「二段階埋入(遅延埋入)」の2種類があります。通常の二段階埋入法では、抜歯を行った後に数ヶ月の治癒期間を設け、その後にインプラントを埋入するというステップを踏みます。この治癒期間中に歯槽骨や歯肉が回復し、炎症がない状態で埋入手術を行えることが特徴です。
一方で、即時埋入は抜歯と同時にインプラント体を埋入する手法であり、二段階埋入と比べて治療回数や通院期間を大きく短縮できるというメリットがあります。特に前歯部では、骨や歯ぐきのボリュームが失われる前に埋入することで、審美性の維持にもつながるため、患者様からのニーズも高まっています。
ただし、即時埋入は高度な診断と外科的技術が求められ、誰にでも適応できる治療法ではないという点に注意が必要です。骨の状態や感染リスク、初期固定の確保が難しいと判断されるケースでは、安全性を重視し、あえて二段階埋入を選択することが望ましい場面もあります。即時性と確実性、双方のバランスを見極めることが治療成功の鍵となります。
即時負荷との違いと混同しないための注意点
「即時埋入」と似た言葉に「即時負荷」という用語がありますが、これはまったく別の概念です。即時埋入は、抜歯と同時にインプラント体を埋入するタイミングの話であるのに対し、即時負荷はインプラント埋入直後に仮歯や仮の上部構造を装着し、咀嚼機能を早期に回復させる治療法のことです。
即時埋入=必ずしも即時負荷ができるというわけではなく、両方を同時に適用するには、非常に厳密な条件が必要となります。たとえば、骨の密度が高く、インプラントがしっかりと初期固定されていること、噛み合わせの力が適切に分散されていること、そして患者様自身が術後の注意事項をしっかりと守れることなどが条件となります。
したがって、即時埋入が可能でも、即時負荷は見送って「治癒を優先する」選択をすることは非常に多いのです。特に前歯部の審美領域では、仮歯を装着したいという希望が強くなる一方で、過度な力が加わることで結合が不安定になるリスクもあるため、慎重な判断が求められます。
混同を避けるためには、患者様自身がそれぞれの治療ステップの意味を理解しておくことが大切です。また、歯科医師との十分なカウンセリングを通じて、何が「即時埋入」であり、何が「即時負荷」なのかを明確に説明してもらうことが、安全で納得のいく治療に繋がる第一歩となります。
抜歯後温存療法との選択肢の違い
抜歯後のインプラント治療には、即時埋入・二段階埋入のほかにも、「抜歯後温存療法(ソケットプリザベーション)」というアプローチがあります。これは、抜歯後に人工骨や再生膜などを使って、骨の吸収を最小限に抑えながら将来のインプラント治療に備える処置のことです。
抜歯後温存療法は、即時埋入が難しいけれど、将来的にインプラントを希望している方に適した選択肢です。骨量や歯肉の厚みが回復してからインプラントを計画できるため、より確実な治療が可能となります。ただし、治療期間は長くなり、複数回の手術が必要になる点はデメリットとも言えます。
また、抜歯後温存療法は、審美性の確保にも有効です。とくに前歯部では、歯ぐきや骨の形態が時間の経過とともに崩れてしまうことがあるため、抜歯後にすぐインプラントを行わない場合は、この温存処置を施すことで、将来的な審美性の回復に役立ちます。
結果として、即時埋入・即時負荷・二段階埋入・温存療法のいずれを選択するかは、「今の状態」と「将来の希望」の両方を踏まえて検討するべき問題です。治療を急ぐか、確実性を取るか、あるいは審美性を重視するか。選択肢を比較したうえで、最も納得できる方法を、信頼できる歯科医師とともに選ぶことが大切です。
患者側が意識したい「できる・できない」の判断材料

自己判断ではなく、精密検査と診断が必須
「インプラントの即時埋入ができるかどうか」は、見た目や感覚では決して判断できません。たとえば、「抜歯予定の歯の周りに痛みがない」「歯ぐきが腫れていない」など、外見上のトラブルが少ない場合でも、骨の状態や感染の有無、細菌の潜在的な存在など、目に見えないリスクが隠れていることは少なくありません。
このため、即時埋入の適応を正確に判断するためには、歯科医院での精密な検査と診断が絶対条件となります。とくに重要なのがCT(コンピューター断層撮影)による骨の三次元的な評価です。これにより、骨の厚み・高さ・密度・形態、さらには神経や上顎洞などの重要な構造との距離を正確に把握することができます。
また、歯ぐきの厚みや位置、歯の傾きや咬み合わせの状態など、細かな要素もインプラント成功の可否に関わってきます。これらすべてを総合的に見極め、「今即時埋入が可能か」「何かしらの処置を先に行うべきか」を判断するのが歯科医師の役割です。
患者様側でできることは、インプラントを希望する意思を伝えることと、事前の検査・診断を信頼して受けること。自己判断で「たぶんできるだろう」「できないならインプラントは無理」と考える前に、まずは専門家の見解をもとに判断を仰ぐことが、納得のいく治療への第一歩です。
医師との十分なカウンセリングで適応を確認
インプラント治療を進めるうえで、患者様と歯科医師との間に十分なコミュニケーションが取れているかどうかは非常に重要です。とくに即時埋入のような高度な治療では、患者様自身が「何のために、どんな治療が、どのように行われるのか」を理解していなければ、途中での不安や誤解がトラブルにつながることもあります。
そのため、治療前のカウンセリングでは、歯科医師からの一方的な説明ではなく、患者様の疑問や希望に対してしっかりと向き合ってくれる医院を選ぶことが大切です。インプラントの仕組みや治療の流れ、適応条件、手術の内容、リスク、費用、治療期間、代替案など、わかりやすく、かつ丁寧に説明されるかどうかが一つの判断基準になります。
また、カウンセリングの中で「即時埋入ができるかどうか」の条件を明確に伝えてくれるかどうかもポイントです。できる場合の理由、できない場合の理由、それに対する別の選択肢の提示がある医院は、信頼性が高いといえます。
さらに、患者様の口腔内環境や健康状態、生活習慣などを考慮し、無理のない計画を提案してくれる歯科医師かどうかも確認しておきたいところです。カウンセリングは「説明を受ける場」ではなく、「治療の方向性を一緒に考える場」だと考えると、納得感のあるインプラント治療に繋がります。
治療を受ける前に整えておきたい健康習慣
即時埋入インプラントの適応条件には、口腔内だけでなく、全身の健康状態や生活習慣も深く関係してきます。とくに問題になりやすいのが、喫煙習慣・糖尿病・睡眠不足・ストレス・栄養バランスの乱れなど、治癒力や免疫力に悪影響を与える要因です。
たとえば喫煙は、血管を収縮させて血流を悪化させ、インプラント埋入後の骨結合を妨げるだけでなく、インプラント周囲炎のリスクも高めます。即時埋入を希望する場合は、少なくとも術前術後の一定期間は禁煙が求められることを理解しておく必要があります。
また、糖尿病はコントロールされていれば問題ありませんが、血糖値が不安定な状態では、治癒が遅れたり感染のリスクが高まったりするため、主治医との連携が必須となります。歯周病や虫歯の有無、歯みがき習慣、食生活も含めて、治療前に可能な限り健康な口腔環境を整えておくことが成功の鍵です。
加えて、口呼吸や歯ぎしり、舌癖などの口腔習癖もインプラントに影響を与えることがあるため、事前に歯科医師に相談しておくことが望ましいです。これらは日常的な癖として軽視されがちですが、長期的にインプラントへ過剰な負荷を与える可能性があるため、必要に応じてナイトガードの使用や口腔筋機能療法(MFT)を行うケースもあります。
インプラント治療は一度きりの処置で終わりではなく、「一生付き合っていく人工歯」です。だからこそ、治療前から自分の体や生活を見つめ直し、インプラントを長持ちさせるための準備をすることが、結果的に満足度の高い治療につながります。
即時埋入を検討するなら、まずは専門の歯科へ相談を

即時埋入の経験豊富な医院を選ぶポイント
即時埋入インプラントは高度な技術と診断力が求められる治療法です。そのため、実際に治療を受ける際には、「即時埋入に対応しているか」だけでなく、「経験と実績があるかどうか」まで確認することが重要です。即時埋入は治療の手順が短縮される一方で、骨の条件や感染リスクなどの繊細な要素を見極めなければならず、術者の技量が成否を大きく左右します。
医院の選定時には、CT設備やシミュレーションソフト、サージカルガイドの導入など、精密な診断と治療を支える設備が整っているかどうかも判断材料になります。これらは、より安全性の高い治療計画の立案と、実際の手術の精度を高めるうえで非常に有効です。
また、症例の提示や写真での比較、術後の説明が丁寧かどうかなど、患者への情報提供の姿勢も医院選びでは重要なポイントです。信頼できる医院であれば、治療の利点だけでなく、リスクや起こりうる合併症、代替案まできちんと伝えてくれるはずです。「ただインプラントができる歯科医院」ではなく、「一人ひとりに合った治療を提案できる医院」を選ぶことが、納得のいく治療への第一歩です。
納得して治療を受けるための情報収集
インプラント治療、特に即時埋入は患者様にとって多くの決断を伴う治療法です。だからこそ、事前の情報収集はとても大切です。「この治療法は自分に合っているのか?」「ほかの選択肢は?」「どんなリスクがあるのか?」といった疑問を解消することが、納得して治療を受けるための土台となります。
情報収集の方法としては、まず歯科医院の公式サイトで診療内容を確認することが基本です。その際、即時埋入についての詳細な説明があるか、設備や治療の流れが明記されているか、院長やスタッフの専門性が伝わってくるかなどをチェックしましょう。また、インプラント専門医や口腔外科の資格を持つ歯科医師が在籍しているかどうかも安心材料になります。
次に、実際のカウンセリングを受けることが何よりの情報収集になります。診察を通して、自身の状態に即時埋入が適しているかどうか、手術の流れや費用、アフターケアの体制まで詳しく知ることができます。聞きづらいと感じることも含めて、率直に質問できる環境を整えてくれる医院は信頼性が高いと言えるでしょう。
さらに、セカンドオピニオンの活用も視野に入れてみてください。異なる視点からの診断や提案を受けることで、より客観的な判断が可能になります。後悔しない選択のためには、「情報の多さ」よりも「質の高い情報」と「対話のしやすさ」がカギとなります。
適応かどうかを知ることが「最善の選択」につながる
即時埋入ができるかどうかという問いに対して、「できるかもしれない」と思うことと、「医師の診断により適応とされた」という確かな根拠には大きな違いがあります。治療の成功率や術後の安定性は、適応条件の正確な見極めにかかっていると言っても過言ではありません。
実際に、骨の状態や歯ぐきの厚み、全身の健康状態などを含めた総合的な判断によって、即時埋入の適応か否かが決まります。たとえ希望していても、感染リスクや骨の量が足りなければ、別の治療法の方がより安全で確実な結果をもたらす可能性もあるのです。
ですから、「即時埋入にこだわること」よりも、「自分にとって最適な治療は何かを知ること」のほうが重要です。そうした視点で診療に臨むことで、結果として納得度の高い、長持ちするインプラント治療へとつながります。
最後に、即時埋入を含むインプラント治療は、「急ぐ」ことが目的ではなく、「正しく判断し、適切なタイミングで行う」ことが成功の鍵です。まずは信頼できる歯科医院で、じっくりと診断を受け、丁寧に相談することから始めましょう。それが、あなたの将来の笑顔と健康を守る「最善の選択」になるはずです。
埼玉県大宮の再治療0%を追求した
審美インプラント治療ガイド
監修:関口デンタルオフィス大宮
電話番号:048-652-1182
*監修者
関口デンタルオフィス大宮
*経歴
・2008年 日本大学歯学部卒業
日本大学歯学部臨床研修部入局
・2009年 日本大学歯学部補綴学第一講座入局
専修医
顎関節症科兼任
・2014年 同医局退局
関口デンタルオフィス開院
*所属学会
*スタディークラブ
・CIDアクティブメンバー(Center of Implant Dentistry)