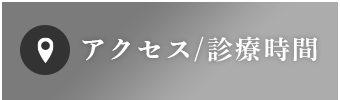歯ぐきが下がって歯が長く見える… 歯周病の進行を止める方法とは?
- 2025年3月18日
- 未分類
目次
はじめに:歯ぐきが下がるのはなぜ?

歯ぐきが下がると見た目や健康にどんな影響がある?
鏡を見たときに「歯が長くなった気がする」と感じたことはありませんか?それは、実際に歯の長さが変わったわけではなく、歯ぐきが下がったこと によって、歯の根元が露出している状態です。歯ぐきが下がると見た目の印象が大きく変わり、口元が老けた印象になることがあります。
しかし、歯ぐきの後退は見た目だけの問題ではありません。口腔内の健康に深刻な影響 を与える可能性があります。
- 知覚過敏が悪化しやすくなる
歯ぐきが下がると、歯の根元にある象牙質が露出します。この部分は神経に近く、冷たい飲み物や熱い食べ物に敏感になり、しみる症状(知覚過敏)が起こりやすくなります。 - 虫歯や歯周病のリスクが増加する
露出した歯の根元はエナメル質に覆われていないため、虫歯になりやすい部位です。また、歯ぐきが下がることで歯と歯ぐきの間に歯周ポケットが深くなり、細菌が繁殖しやすくなります。 - 歯の寿命が縮まる
歯ぐきの後退が進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)にも影響を及ぼし、歯がぐらついて抜けるリスクが高まります。歯を失うと、食事や会話に支障をきたすだけでなく、全身の健康にも悪影響を与える可能性があります。
このように、歯ぐきの健康は見た目だけでなく、歯の寿命や口腔内の健康を維持するために重要な要素なのです。
歯ぐきが下がる原因は歯周病だけじゃない?
歯ぐきの後退と聞くと、まず「歯周病」を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、実際には歯周病以外にも、さまざまな要因が歯ぐきの後退を引き起こします。
- 歯周病(歯槽膿漏)
歯周病は、歯ぐきの炎症が進行し、歯を支える骨(歯槽骨)が溶けてしまう病気です。初期段階では歯ぐきの腫れや出血が見られますが、進行すると歯ぐきが下がり、歯が長く見えるようになります。 - 過度なブラッシング
「歯をしっかり磨かないと」と思うあまり、力を入れすぎた歯磨きが原因で歯ぐきを傷つけてしまうことがあります。特に、硬い歯ブラシを使って強く磨くと、歯ぐきが傷つき、少しずつ後退してしまいます。 - 加齢による影響
年齢を重ねると、歯ぐきの弾力が失われ、少しずつ後退していく傾向があります。特に、長年にわたる歯ぎしりや食いしばりの習慣があると、歯ぐきに負担がかかり、より進行しやすくなります。 - 歯ぎしり・食いしばり
強い力が歯や歯ぐきにかかると、歯ぐきがダメージを受け、歯の根元の部分から歯ぐきが下がってしまうことがあります。歯ぎしりをしている自覚がない場合でも、寝ている間に食いしばる習慣があると、歯ぐきに大きな負担がかかります。 - 不適切な歯並びや噛み合わせ
歯並びが悪いと、特定の歯に過度な力がかかり、その部分の歯ぐきが下がることがあります。また、噛み合わせが悪いと、歯ぐきの負担が増え、後退が進みやすくなります。
このように、歯ぐきの後退にはさまざまな原因があり、適切な対策をとることで進行を防ぐことができます。
早めの対策が重要!放置するとどうなる?
「少し歯ぐきが下がってきたかも…」と感じても、痛みがないために放置してしまう方も少なくありません。しかし、歯ぐきの後退は自然に回復することはなく、進行していくリスク があります。
放置するとどうなる?
- 歯周病の進行
歯ぐきが下がることで、歯と歯ぐきの間に深い隙間(歯周ポケット)ができ、そこに細菌が入り込みやすくなります。結果として、歯周病が進行し、歯を支える骨が溶けるリスクが高まります。 - 歯のぐらつきや抜歯のリスク増加
歯周病が進行すると、歯を支える組織が破壊され、最終的には歯がぐらつき、抜歯を余儀なくされることもあります。 - 口臭の悪化
歯周病が進行すると、口臭の原因となる細菌が繁殖しやすくなります。特に、歯周ポケットに溜まった細菌は、強い口臭を引き起こすことがあり、対人関係にも影響を与える可能性があります。 - 食事や発音への影響
歯がぐらつくと、噛む力が低下し、食事が楽しめなくなることがあります。また、前歯の歯ぐきが下がると、発音がしづらくなることもあります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに進行してしまう のが、歯ぐきの後退の怖いところです。症状が軽いうちに適切なケアを行うことで、歯ぐきの健康を守ることができます。
歯ぐきが下がる主な原因とは?

歯周病による歯ぐきの後退
歯ぐきが下がる原因の中でも、最も多いのが歯周病です。歯周病は、歯と歯ぐきの間に細菌が繁殖し、炎症を引き起こす病気です。進行すると、歯ぐきが腫れたり出血したりするだけでなく、歯を支える骨(歯槽骨)が破壊され、歯ぐきが徐々に後退していきます。
歯周病の進行による歯ぐきの変化
- 歯垢(プラーク)の蓄積
歯磨きが不十分な状態が続くと、歯の表面や歯ぐきの隙間に細菌が付着し、歯垢(プラーク)が形成されます。放置すると、歯垢は24時間以内に歯石へと変化し、歯ブラシでは除去できなくなります。 - 歯肉炎の発症
歯垢や歯石の中に含まれる細菌が歯ぐきを刺激し、炎症が発生します。初期段階では、歯ぐきの腫れや歯磨き時の出血が主な症状となります。 - 歯周ポケットの拡大と歯槽骨の破壊
炎症が進むと、歯と歯ぐきの間の隙間(歯周ポケット)が深くなり、細菌がさらに奥へと侵入します。これにより、歯を支える骨が溶け、歯ぐきが後退してしまいます。 - 歯のぐらつきと抜歯のリスク
歯槽骨が減少すると、歯を支える力が弱まり、歯がぐらつくようになります。最終的には、歯を抜かざるを得ないケースもあります。
歯周病が原因で歯ぐきが下がることを防ぐためには、日頃から正しいブラッシングを心がけ、定期的に歯科医院で歯石を除去することが大切です。
強すぎる歯磨きが歯ぐきを傷つける
歯磨きは、歯の健康を守るために欠かせない習慣ですが、間違った磨き方をしていると歯ぐきを傷つける原因になります。特に、強すぎるブラッシングや誤った歯磨き方法は、歯ぐきの後退を引き起こす要因の一つです。
強すぎる歯磨きによる影響
- 歯ぐきが傷つき、炎症が起きやすくなります。歯ブラシの圧が強すぎると、歯ぐきにダメージを与え、徐々に後退してしまうことも。
- 歯の表面のエナメル質が削れ、知覚過敏を引き起こす可能性がある。特に硬めの歯ブラシを使用し、ゴシゴシと力強く磨く習慣があると、歯の保護機能が低下します。
- 歯ぐきのマッサージ効果が低下し、健康な状態を維持しにくくなる。適度な圧でブラッシングすることは歯ぐきの血流を促進しますが、強すぎる力で磨くと逆にダメージとなります。
適切な歯磨きの方法
- 歯ブラシは「鉛筆を持つように軽く握る」ことで、必要以上の力をかけないようにする。
- 毛先を歯と歯ぐきの境目に当て、優しく小刻みに動かして磨くことを意識する。
- 硬めの歯ブラシではなく、柔らかめまたは普通の硬さの歯ブラシを選ぶことで、歯ぐきへの負担を軽減する。
- 電動歯ブラシを活用することで、適度な圧力で磨きやすくなり、歯ぐきを傷つけにくくなる。
「歯をしっかり磨かなければ」と思うあまり、力を入れすぎることが多いですが、強く磨けば磨くほど歯ぐきに負担をかけることになります。適切なブラッシングを意識し、歯ぐきの健康を守ることが大切です。
加齢や生活習慣が歯ぐきの健康に与える影響
歯ぐきの後退は、加齢による自然な変化としても起こることがあります。年齢を重ねることで、歯ぐきの弾力や再生力が低下し、少しずつ後退する傾向があります。
加齢による歯ぐきの変化
- コラーゲンの減少によって歯ぐきが薄くなり、下がりやすくなる。
- 加齢とともに血流が悪くなり、歯ぐきの再生能力が低下する。
- 骨密度が減少し、歯を支える力が弱まり、歯ぐきが下がる要因となる。
また、生活習慣も歯ぐきの健康に大きく影響を与えます。特に、喫煙やストレス、栄養不足は歯ぐきの後退を進行させる原因となります。
歯ぐきの健康を損なう生活習慣
- 喫煙は血流を悪化させ、歯ぐきの再生能力を低下させる。タバコに含まれるニコチンや有害物質が血管を収縮させ、歯ぐきの細胞に十分な栄養が届きにくくなる。
- ストレスがたまると免疫力が低下し、歯ぐきの炎症が進行しやすくなる。歯ぎしりや食いしばりの原因にもなり、歯ぐきに負担がかかることがある。
- 栄養バランスの乱れにより、歯ぐきの組織が弱くなり、後退しやすくなる。特に、ビタミンCやカルシウムが不足すると、歯ぐきの健康が損なわれやすくなる。
歯ぐきを健康に保つためにできること
- 栄養バランスの良い食事を心がけることで、歯ぐきの再生を促す。ビタミンC、カルシウム、たんぱく質を意識的に摂取することが重要。
- 禁煙をすることで、歯ぐきの血流が改善し、健康な歯ぐきを維持しやすくなる。
- ストレス管理を行い、免疫力を高めることで歯ぐきの炎症を抑える。
歯ぐきの後退は年齢による影響もありますが、生活習慣を改善することで進行を遅らせることが可能になります。
歯ぐきが下がるとどうなる?

歯が長く見えて老けた印象になる
歯ぐきが下がると、まず見た目の変化に気づく人が多いです。通常、歯ぐきは歯の根元を覆っていますが、歯ぐきが後退すると根元が露出し、歯が長く見えるようになります。この状態は「ロングトゥース(long tooth)」とも呼ばれ、見た目の印象に大きな影響を与えます。
特に、前歯の歯ぐきが下がると、口元のバランスが崩れ、実際の年齢よりも老けた印象を与えることがあります。また、歯ぐきの色が不均一になったり、境目がギザギザに見えたりすることで、より目立ちやすくなります。
歯ぐきの後退による影響
- 自分の笑顔に自信が持てなくなる
笑ったときに歯ぐきの後退が目立ち、口元を隠してしまう人も少なくありません。 - 会話や写真撮影を避けるようになる
歯ぐきの後退が気になり、人と話すことや写真に写ることに抵抗を感じることがあります。 - 口元のコンプレックスがストレスにつながる
見た目の変化を気にしすぎることで、自信を失い、精神的な負担になることがあります。
このように、歯ぐきの後退は見た目だけでなく、心理的な影響も大きいです。歯ぐきを健康に保つことは、単に口腔内の健康維持だけでなく、自分に自信を持つためにも重要なポイントです。
知覚過敏が悪化しやすくなる
歯ぐきが下がることで、歯の根元(象牙質)が露出し、知覚過敏が起こりやすくなります。象牙質はエナメル質に比べて柔らかく、神経に近いため、外部からの刺激に敏感に反応します。
知覚過敏が起こる原因
- 冷たい飲み物や食べ物がしみる
歯の根元がむき出しになると、冷たい水やアイスクリームを食べたときに強い痛みを感じることがあります。 - 温かい食べ物でも違和感を感じる
知覚過敏が進行すると、温かいスープやお茶などの熱いものにも反応するようになります。 - 歯ブラシの毛先が当たるだけで痛い
露出した象牙質は刺激に敏感なため、通常の歯磨きでも痛みを感じることがあります。 - 酸性の飲食物が歯の表面を溶かし、さらに悪化
柑橘類や炭酸飲料、酢を使った料理などを頻繁に摂取すると、歯の表面がさらに傷つき、知覚過敏がひどくなる可能性があります。
知覚過敏を防ぐための対策
- 知覚過敏用の歯磨き粉を使用する
フッ素や硝酸カリウムが配合された歯磨き粉を使うことで、痛みを軽減できます。 - 歯のエナメル質を守る
強すぎるブラッシングを避け、歯にやさしいケアを心がけることが重要です。 - 歯科医院でのコーティング治療を受ける
フッ素塗布や歯のコーティング治療を受けることで、歯の表面を保護し、知覚過敏の症状を緩和できます。
歯ぐきの後退による知覚過敏は、放置すると食事のたびに痛みを感じるようになり、生活の質が低下する可能性があります。違和感を覚えたら、早めに歯科医院で相談することが大切です。
歯の寿命が縮まり、最悪の場合は抜歯に至ることも
歯ぐきが下がると、単に見た目が変わるだけでなく、歯を支える組織(歯周組織)が弱くなり、歯の寿命が縮まるリスクがあります。特に、歯周病が進行すると、最終的に歯が抜け落ちてしまう可能性があります。
歯ぐきの後退が進行すると起こる問題
- 歯のぐらつきがひどくなる
歯を支える骨(歯槽骨)が減少すると、歯の固定力が弱まり、歯がグラグラと揺れるようになります。 - 歯を支えられなくなり、抜歯が必要になる
歯槽骨が大きく減ると、歯ぐきだけでは歯を支えきれなくなり、自然に抜けてしまうこともあります。 - 歯がなくなることで噛み合わせが乱れる
一本の歯が抜けるだけでも、隣の歯や噛み合わせのバランスが崩れ、さらに他の歯に負担がかかるようになります。
抜歯後の影響
- 隣の歯が倒れ込んできて、歯並びが悪くなる
- 噛み合わせが悪くなり、顎関節症のリスクが高まる
- 発音や食事に影響が出て、日常生活の質が低下する
抜歯を避けるためにできること
- 歯ぐきの後退が気になったら、早めに歯科医院を受診し、状態をチェックしてもらう。
- 歯周病が進行する前に、定期的なクリーニングで歯石を除去する。
- 適切な歯磨き方法を実践し、歯ぐきを守る習慣を身につける。
歯ぐきの後退は進行性の問題であり、放置すると歯を失うリスクが高まります。最悪のケースを避けるためにも、日常的なケアと専門的な治療を組み合わせることが重要です。
歯ぐきの後退を防ぐためのセルフケア

正しい歯磨きの方法を見直す
歯ぐきの後退を防ぐために最も重要なのが、正しい歯磨き習慣を身につけることです。歯磨きは毎日の習慣であり、適切に行うことで歯ぐきへのダメージを防ぐことができます。しかし、間違った方法で磨いていると、歯ぐきを傷つけ、逆に後退を加速させる可能性があるため、注意が必要です。
間違った歯磨きの例
- 力を入れてゴシゴシと磨く
- 硬めの歯ブラシを使っている
- 長時間磨いてしまい、歯ぐきに過度な負担をかける
- 歯ぐきの境目を意識せずに磨く
このような磨き方を続けていると、歯ぐきを傷つけるだけでなく、エナメル質の摩耗や知覚過敏を引き起こす原因にもなります。
正しい歯磨きのポイント
- 歯ブラシの持ち方を工夫する
歯ブラシは「鉛筆を持つように軽く握る」と、力を入れすぎずに磨くことができます。力が強すぎると歯ぐきを傷つけるため、優しく磨くことを意識しましょう。 - 適切な歯ブラシを選ぶ
硬めの歯ブラシは歯ぐきを傷つける原因になるため、「やわらかめ」または「普通」の硬さの歯ブラシを使用しましょう。歯ぐきにやさしい設計の歯ブラシを選ぶのも効果的です。 - 歯ぐきの境目にブラシを当てる
歯と歯ぐきの境目に毛先を45度の角度で当て、細かく優しく動かします。これにより、歯周ポケット内の汚れをしっかり取り除きながら、歯ぐきへの負担を最小限に抑えることができます。 - 電動歯ブラシを活用する
電動歯ブラシは適度な圧で磨けるため、強く磨きすぎることを防ぐのに役立ちます。手動の歯ブラシよりも歯垢除去率が高く、歯ぐきにやさしいモデルも多いです。
正しい歯磨きを習慣化することで、歯ぐきの健康を守ることができます。毎日のケアを見直し、歯ぐきに負担をかけないよう心がけましょう。
デンタルフロス・歯間ブラシの活用で歯ぐきを守る
歯磨きだけでは取り切れない汚れが、歯と歯の間や歯周ポケットに溜まることがあります。歯ぐきの後退を防ぐためには、デンタルフロスや歯間ブラシを併用し、歯周病の原因となる細菌の繁殖を防ぐことが重要です。
デンタルフロスの役割と使い方
デンタルフロスは、歯と歯の間の細かい汚れやプラークを取り除くための必須アイテムです。特に、歯ぐきの後退が進行すると、歯と歯の隙間が広がり、食べかすや細菌が溜まりやすくなるため、フロスの使用がより重要になります。
- フロスを適切な長さ(約40cm)にカットし、両手で持つ
- 歯と歯の間にゆっくりと挿入し、こするように動かして汚れを除去する
- 強く押し込みすぎないように注意しながら、歯ぐきを傷つけないように使用する
歯間ブラシの活用
歯間ブラシは、特に歯と歯の隙間が広がった部分の汚れを効果的に除去できます。
- サイズの合った歯間ブラシを選び、無理なく挿入できるものを使用する
- 力を入れずに前後に優しく動かして、歯ぐきを傷つけないようにする
- フロスと併用することで、より効果的に歯垢を除去できる
毎日のブラッシングにフロスや歯間ブラシを取り入れることで、歯ぐきの健康を維持し、歯周病の進行を防ぐことができます。
歯ぐきマッサージで血行を促進する
歯ぐきを健康に保つためには、歯ぐきの血流を良くすることも大切です。血流が悪くなると、歯ぐきの細胞に十分な栄養が行き渡らず、歯ぐきの後退が進みやすくなります。
歯ぐきマッサージの効果
- 血行が促進され、歯ぐきの細胞が活性化する
- 歯ぐきの腫れや炎症を和らげる
- 歯周病の予防に役立つ
簡単にできる歯ぐきマッサージの方法
- 指の腹を使って、歯ぐきを優しくマッサージする
親指と人差し指で歯ぐきを軽く押しながら、円を描くようにマッサージすると、血行が良くなります。 - 歯ブラシを使ってマッサージする
柔らかめの歯ブラシを使い、歯ぐきの表面を軽くなでるようにブラッシングすることで、血流が促進されます。 - 歯ぐきに良い成分が配合されたジェルを使用する
歯ぐきの血行を良くする成分が含まれたジェルを使用すると、マッサージの効果が高まります。
歯ぐきマッサージを毎日の習慣にすることで、歯ぐきの健康を維持し、後退を予防することができます。
歯周病による歯ぐき下がりを防ぐプロのケア

定期的な歯科検診で早期発見・早期治療
歯ぐきが下がる原因の多くは歯周病によるものであり、進行すればするほど治療が困難になります。歯周病は初期の段階では自覚症状が少ないため、歯ぐきの後退に気づいたときにはすでに進行していることが多いです。そのため、定期的に歯科検診を受けることが重要です。
歯科検診でチェックするポイント
- 歯ぐきの腫れや炎症の有無
- 歯周ポケットの深さ(歯と歯ぐきの間の隙間)
- 歯のぐらつきがないか
- 歯垢や歯石の付着状況
歯科検診の頻度
歯周病予防のためには、3〜6ヶ月に1回の定期検診を受けることが推奨されています。歯ぐきの状態をチェックし、歯周病の初期兆候が見られた場合は、すぐに適切な処置を行うことで進行を防ぐことができます。
歯科検診を受けるメリット
- 歯周病の早期発見・早期治療ができる
- 歯ぐきの健康状態を維持しやすくなる
- 口腔内の清潔を保つことで、歯ぐきの後退を防げる
歯ぐきの後退が進行してしまうと、元の状態に戻すことは難しくなるため、定期的な検診を受け、早い段階で適切なケアを行うことが大切です。
スケーリング・ルートプレーニングで歯周病を防ぐ
歯周病が進行すると、歯と歯ぐきの間に歯石が蓄積し、細菌の温床となります。これを放置すると炎症が悪化し、歯ぐきがどんどん後退してしまいます。そのため、定期的に歯科医院で歯石を除去する「スケーリング」や「ルートプレーニング」が必要になります。
スケーリングとは?
スケーリングとは、歯の表面や歯周ポケット内に付着した歯石を除去する処置のことを指します。歯石は歯ブラシでは除去できず、歯科医院で専用の器具を使用して取り除く必要があります。
ルートプレーニングとは?
ルートプレーニングは、スケーリングでは取りきれない歯根の部分に付着した歯石や細菌を徹底的に除去する治療です。歯根の表面を滑らかにすることで、歯垢や歯石の再付着を防ぎ、歯周病の進行を抑えます。
スケーリングとルートプレーニングの効果
- 歯ぐきの炎症を抑え、腫れや出血を改善する
- 歯周ポケットの深さを減少させ、歯ぐきの健康を維持する
- 歯周病菌の繁殖を抑え、口臭の予防につながる
施術の頻度
歯周病が軽度の場合は、半年に1回程度のスケーリングで十分な場合が多いです。しかし、すでに歯ぐきの後退が進んでいる場合や歯周ポケットが深くなっている場合は、3〜4ヶ月に1回の頻度で施術を受けることが推奨されます。
スケーリングやルートプレーニングを定期的に行うことで、歯ぐきの健康を維持し、歯周病の進行を防ぐことができます。
生活習慣の改善で歯ぐきの健康を維持
歯ぐきの健康を守るためには、歯科医院での専門的なケアだけでなく、日々の生活習慣の見直しも重要となります。歯周病を予防し、歯ぐきの後退を防ぐために、以下の点に注意する必要があります。
栄養バランスのとれた食生活を心がける
歯ぐきの健康には、ビタミンやミネラルが重要な役割を果たします。特に、以下の栄養素を積極的に摂取することで、歯ぐきの健康を維持しやすくなります。
- ビタミンC(歯ぐきの炎症を抑え、コラーゲンの生成を促進)
摂取源:レモン、オレンジ、いちご、ピーマン - カルシウム(歯や骨の健康を維持)
摂取源:牛乳、チーズ、ヨーグルト、豆腐 - ビタミンD(カルシウムの吸収を助け、骨密度を向上)
摂取源:魚(サーモン、サバ)、きのこ類 - たんぱく質(歯ぐきの細胞を修復し、強化する)
摂取源:肉類、卵、大豆製品
喫煙を控える
喫煙は歯周病の最大のリスク要因の一つであり、タバコを吸うことで血流が悪くなり、歯ぐきの再生能力が低下します。また、喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病の進行が早く、治療の効果が出にくいことが分かっています。
禁煙することで、歯ぐきの血流が改善され、歯周病のリスクを大幅に下げることができます。
ストレス管理を行う
ストレスが溜まると、免疫力が低下し、歯ぐきの炎症が進行しやすくなります。また、ストレスが原因で歯ぎしりや食いしばりが増えると、歯ぐきに過度な負担がかかり、後退が進行することがあります。
ストレスを軽減するために、適度な運動、十分な睡眠、リラックスできる時間を確保することが大切です。
歯周病の予防には、日々のセルフケアとプロフェッショナルケアの両方をバランスよく取り入れることが重要です。早めの対策を心がけ、健康な歯ぐきを維持しましょう。
進行した歯ぐきの下がりは治療できる?

歯周組織再生療法(エムドゲイン・リグロス)とは?
歯ぐきが下がると、見た目の変化だけでなく、知覚過敏や歯のぐらつきなどの問題が発生します。進行してしまった歯ぐきの後退は自然に元に戻ることはないため、専門的な治療を受けることで歯周組織の再生を促す必要があります。近年では、歯周組織再生療法と呼ばれる治療法が注目されており、特に「エムドゲイン」や「リグロス」といった薬剤を使用した治療が効果的とされています。
エムドゲインとは?
エムドゲイン(Emdogain)は、スウェーデンで開発された歯周組織再生薬であり、歯ぐきや歯槽骨、歯根膜などの組織を再生させる働きがあります。子どもの歯が生える際に分泌される「エナメルマトリックスデリバティブ」というタンパク質を主成分とし、歯周病で破壊された歯ぐきや骨の再生を促進します。
エムドゲインの治療の流れ
- 歯周病によって損傷した歯ぐきや骨をきれいに掃除する。
- エムドゲインを適用し、組織の再生を促す。
- 数ヶ月かけて歯周組織が再生し、歯ぐきが健康な状態に戻る。
リグロスとは?
リグロス(Regroth)は、日本で開発された歯周組織再生薬で、厚生労働省に認可された歯周病治療薬です。リグロスには「FGF-2(線維芽細胞増殖因子)」が含まれており、骨や歯ぐきを再生する効果が期待されています。
リグロスの特徴
- 保険適用されるため、エムドゲインよりも費用を抑えられる。
- FGF-2の働きで、骨の再生力が高まる。
- 手術後のダウンタイムが比較的短い。
どちらの治療法が適しているのか?
エムドゲインは、歯周病によって歯槽骨が軽度に失われたケースに適しており、リグロスは、骨の再生が求められる症例に効果的とされています。歯ぐきの状態によって最適な治療法が異なるため、歯科医師と相談しながら適切な方法を選択することが大切です。
歯肉移植術で失った歯ぐきを取り戻す方法
歯ぐきが大きく下がってしまった場合、「歯肉移植術(FGG・CTG)」と呼ばれる治療法で歯ぐきを補うことができます。
歯肉移植術の種類
遊離歯肉移植術(FGG: Free Gingival Graft)
- 上顎の口蓋(こうがい)から歯ぐきを採取し、下がった部分に移植する方法。
- 硬く厚みのある歯ぐきを再生できるが、見た目の自然さがやや劣る。
結合組織移植術(CTG: Connective Tissue Graft)
- 口蓋の内部から結合組織のみを採取し、歯ぐきに移植する方法。
- 自然な見た目になりやすく、審美的に優れた仕上がりになる。
歯肉移植の手順
- 口蓋から歯ぐきの一部を採取する。
- 歯ぐきが下がった部分に移植し、縫合する。
- 約2週間で傷口が治癒し、新しい歯ぐきが定着する。
歯肉移植のメリット
- 歯ぐきの厚みが増し、歯の保護力が向上する。
- 知覚過敏の改善につながる。
- 見た目が自然になり、審美性が向上する。
歯肉移植のデメリット
- 移植した部分と元の歯ぐきに若干の色の違いが生じることがある。
- 口蓋の採取部位に痛みを伴うことがある。
- 術後のダウンタイムが必要。
歯ぐきの後退が進行している場合は、歯肉移植術によって歯ぐきを補強することで、歯の健康と見た目の両方を改善できます。
知覚過敏の治療と合わせて行う対策
歯ぐきの後退によって知覚過敏が悪化した場合、以下のような治療法を併用することで症状を緩和することができます。
知覚過敏の治療法
フッ素塗布
- フッ素を歯の表面に塗ることで、象牙質を保護し、刺激から歯を守る。
レーザー治療
- 低出力レーザーを照射することで、神経の反応を抑え、知覚過敏の症状を和らげる。
レジンコーティング
- 露出した象牙質にレジン(歯科用樹脂)を塗布し、刺激から保護する。
日常生活での対策
- 知覚過敏用の歯磨き粉を使用し、歯の神経を保護する。
- 強すぎるブラッシングを避け、優しく磨くことを意識する。
- 酸性の食品(柑橘類、炭酸飲料、酢を多く含む料理)を控えめにする。
知覚過敏の治療と歯ぐきの再生治療を組み合わせることで、歯ぐきの健康を回復させながら、痛みやしみる症状を軽減することが可能となります。
歯ぐきを健康に保つための生活習慣とは?

栄養バランスの良い食事で歯ぐきを強くする
歯ぐきを健康に保つためには、日々の食生活が重要な役割を果たします。特に、歯ぐきの組織を強くし、炎症を防ぐ栄養素を積極的に摂取することで、歯周病の進行を抑え、歯ぐきの後退を防ぐことができます。
歯ぐきの健康を守るために必要な栄養素と食品
ビタミンC(抗酸化作用・コラーゲン生成)
- 歯ぐきを構成するコラーゲンの生成を促し、歯ぐきを強くする。
- 炎症を抑える働きがあり、歯周病の進行を防ぐ効果も期待できる。
- オレンジ、レモン、いちご、ピーマン、ブロッコリーなどに多く含まれる。
カルシウム(歯や骨を強化)
- 歯槽骨を強くし、歯をしっかり支えることで、歯ぐきの健康を維持する。
- 牛乳、チーズ、ヨーグルト、小魚、豆腐、ひじきなどの食品から摂取できる。
ビタミンD(カルシウムの吸収を促進)
- カルシウムの吸収を助け、骨や歯の健康を支える。
- 鮭、サバ、卵、きのこ類、日光浴(紫外線を浴びることで体内で生成)によって補える。
たんぱく質(歯ぐきの組織を修復・強化)
- 歯ぐきの細胞や血管を健康に保ち、傷ついた組織の回復を助ける。
- 肉、魚、大豆製品、卵、ナッツ類に豊富に含まれる。
ポリフェノール(抗菌・抗炎症作用)
- 口内の細菌の増殖を抑え、歯周病のリスクを低減する。
- 緑茶、カカオ(ダークチョコレート)、赤ワイン、ブルーベリーなどから摂取可能。
食生活を改善することで、歯ぐきの健康を守るだけでなく、全身の健康も向上させることができます。日頃から栄養バランスを意識し、歯ぐきの強化に役立つ食品を積極的に取り入れることが大切です。
喫煙が歯ぐきに与える悪影響と禁煙のススメ
タバコは歯ぐきの健康にとって非常に有害な習慣であり、喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病のリスクが2〜6倍高いといわれています。タバコの成分が歯ぐきに与える悪影響について理解し、禁煙を検討することが、歯ぐきの健康を維持するための重要なポイントとなります。
タバコが歯ぐきに与える影響
血流の低下による歯ぐきの弱体化
- ニコチンは血管を収縮させ、歯ぐきへの血流を低下させる。
- 血液の循環が悪くなることで、歯ぐきの再生能力が低下し、後退が進行しやすくなる。
歯周病の進行を加速
- 喫煙者は免疫力が低下しているため、細菌感染に対する抵抗力が落ち、歯周病が悪化しやすい。
- 歯ぐきの腫れや出血が起こりにくくなるため、歯周病に気づかないまま進行してしまうことが多い。
歯ぐきの黒ずみ(メラニン色素の沈着)
- タバコの影響で歯ぐきにメラニン色素が沈着し、黒ずみが目立つようになる。
- 一度黒くなった歯ぐきは自然には戻らず、治療が必要になることもある。
インプラントや歯周組織再生治療の成功率低下
- 喫煙者はインプラントや歯肉移植の成功率が低く、治療後の回復も遅くなる。
禁煙のメリット
- 血流が改善され、歯ぐきが健康を取り戻しやすくなる。
- 免疫力が向上し、歯周病の進行を防げる。
- 口臭が軽減し、歯の黄ばみや歯ぐきの黒ずみも改善される。
禁煙することで、歯ぐきの健康だけでなく、全身の健康も向上します。歯科医院では禁煙支援を行っていることもあるため、歯ぐきを守るためにも禁煙を検討することが望ましいです。
ストレスと歯ぎしりが歯ぐきに及ぼす影響
ストレスは、歯ぐきの健康にも大きく影響を及ぼします。ストレスが溜まると、無意識のうちに歯ぎしりや食いしばりをしてしまい、歯ぐきに過剰な負担がかかることがあります。
歯ぎしり・食いしばりが歯ぐきに与える影響
- 歯ぐきへの圧力が増し、後退を加速させる。
- 歯の表面が削れ、知覚過敏が悪化する。
- 顎関節症のリスクが高まり、顎や顔の筋肉に痛みが出ることもある。
歯ぎしりの対策
マウスピースの使用
- 夜間の歯ぎしりを防ぐために、歯科医院でマウスピース(ナイトガード)を作成する。
リラックスする習慣を取り入れる
- ストレス管理を行い、リラックスする時間を確保する。
- 深呼吸やストレッチ、軽い運動を取り入れ、ストレスを発散させる。
寝る前の生活習慣を見直す
- 就寝前のスマホやカフェインの摂取を控え、質の良い睡眠を心がける。
歯ぐきの健康を維持するためには、ストレスを溜めすぎないようにし、歯ぎしりや食いしばりの対策を行うことが大切です。
知覚過敏と歯ぐき下がりの関係とは?

知覚過敏の原因は歯ぐきの後退にある?
知覚過敏は、冷たいものや熱いものを口にしたときに「キーン」としみるような痛みを感じる症状であり、その原因の一つとして歯ぐきの後退が関係しています。通常、歯の表面はエナメル質に覆われており、外部からの刺激を遮断していますが、歯ぐきが下がることで歯の根元(象牙質)が露出し、神経に直接刺激が伝わりやすくなります。
歯ぐきの後退が知覚過敏を引き起こすメカニズム
- 歯ぐきが後退し、象牙質がむき出しになる
歯ぐきが下がることで、本来なら歯ぐきに覆われている象牙質が露出します。 - 象牙細管を通じて刺激が神経に伝わる
象牙質には象牙細管と呼ばれる微細な管が無数にあり、この管を通じて外部の刺激が歯の神経に伝わります。 - 冷たいものや熱いものがしみるようになる
飲食時の温度変化や、歯ブラシの刺激が象牙細管を介して神経に伝わり、痛みを引き起こします。
知覚過敏の主な症状
- 冷たい水やアイスを口にするとしみる
- 熱いスープやコーヒーでも痛みを感じる
- 歯ブラシの毛先が当たると不快感がある
- 酸味の強い食べ物(レモンや酢)で痛みが走る
歯ぐきが下がる原因が知覚過敏を引き起こすため、根本的な対策としては歯ぐきの健康を守ることが重要となります。
知覚過敏を和らげる歯磨き粉の選び方
知覚過敏を軽減するためには、専用の歯磨き粉を使用することで症状を和らげることができます。知覚過敏用の歯磨き粉には、象牙質の神経への刺激を遮断する成分が含まれており、継続的に使用することで症状が改善するケースが多いです。
知覚過敏に効果的な成分
- 硝酸カリウム – 象牙細管の神経を落ち着かせ、痛みを和らげる効果がある。
- フッ素(フッ化ナトリウム) – エナメル質を強化し、酸によるダメージを防ぐ。再石灰化を促し、歯を健康に保つ働きがある。
- 酢酸ストロンチウム – 象牙細管を封鎖し、刺激が神経に届かないようにする。
- ヒドロキシアパタイト – 歯の表面をコーティングし、外部刺激を遮断する。
知覚過敏用歯磨き粉の使用方法
- 1日2回以上使用し、継続的にケアすることが大切(即効性はなく、継続することで徐々に効果が現れる)。
- 歯ブラシの毛先を優しく当て、力を入れずに磨く(強く磨くと逆に象牙質が傷つき、知覚過敏が悪化することがある)。
- 歯磨き後に歯磨き粉をしばらく口に残す(すぐにうがいをすると成分が流れてしまうため、少量の水で軽くすすぐ程度が良い)。
知覚過敏用の歯磨き粉を適切に使用することで、症状を軽減し、歯ぐきの健康を守ることが可能となります。
しみる症状を緩和する歯科での治療法
知覚過敏がひどくなると、日常生活に支障をきたすことがあります。その場合、歯科医院での治療を受けることで、痛みを和らげることができます。
歯科医院で行われる知覚過敏の治療法
フッ素塗布
- フッ素を歯の表面に塗布することで、象牙細管を封鎖し、刺激を遮断する。
- 定期的に施術を受けることで、知覚過敏の進行を抑えることができる。
レーザー治療
- 低出力のレーザーを照射し、象牙細管を封鎖することで知覚過敏を改善する。
- 治療時間が短く、痛みもほとんどないため、手軽に受けられる治療法の一つ。
レジンコーティング(象牙質の保護)
- 露出した象牙質にレジン(歯科用樹脂)を塗布し、物理的に保護する。
- 長期間効果が持続し、しみる症状を防ぐことができる。
歯肉移植術(歯ぐきが極端に下がった場合)
- 歯ぐきの後退がひどい場合、口蓋から歯ぐきを移植することで、露出した象牙質をカバーする。
- 美しい見た目を取り戻しながら、知覚過敏の症状も改善できる。
知覚過敏が気になる場合は、セルフケアに加えて歯科医院での専門的な治療を受けることで、より確実に症状を緩和できるでしょう。
歯周病が全身の健康に及ぼす影響

歯周病が糖尿病や心疾患のリスクを高める?
歯周病は単なる口腔内の病気ではなく、全身の健康にも大きな影響を及ぼすことが分かっています。特に、糖尿病や心疾患との関連性が強く、多くの研究によって証明されています。
歯周病と糖尿病の関係
- 炎症が血糖値を悪化させる
- 歯周病が進行すると、歯ぐきに慢性的な炎症が発生する。
- その炎症が体内のインスリンの働きを阻害し、血糖値が上昇しやすくなる。
- その結果、糖尿病の症状が悪化しやすくなる。
- 糖尿病患者は歯周病になりやすい
- 糖尿病の人は免疫力が低下しており、歯周病菌が繁殖しやすい環境になる。
- 高血糖状態が続くと、歯ぐきの血流が悪くなり、感染しやすくなる。
- 歯周病治療が血糖コントロールを改善する
- ある研究では、歯周病を治療することで血糖値(HbA1c)が0.4%〜0.6%改善するという結果が出ている。
- そのため、糖尿病のコントロールをする上で、歯周病治療は非常に重要な役割を果たす。
歯周病と心疾患の関係
- 歯周病菌が血管に入り、動脈硬化を引き起こす
- 歯周病菌が血流に入り込むことで、血管の内側に炎症を引き起こす。
- これが原因で血管が硬くなり、動脈硬化を引き起こしやすくなる。
- 血栓ができやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まる
- 炎症が進行すると、血液がドロドロになり、血栓ができやすくなる。
- これが原因で、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まる。
- 歯周病がある人は心疾患リスクが1.5倍
- 歯周病患者は、健康な人に比べて心疾患のリスクが約1.5倍高いとされている。
免疫力の低下と歯ぐきの炎症の関係
免疫力が低下すると、体が細菌やウイルスに対する抵抗力を失い、感染症にかかりやすくなります。歯周病も細菌感染によって引き起こされるため、免疫力の低下が直接的な悪影響を及ぼすことがあります。
免疫力低下が歯周病を悪化させるメカニズム
- 免疫力が落ちると、細菌が繁殖しやすくなる
- 体の防御機能が低下すると、歯周病菌が急激に増殖しやすくなる。
- 特に、体調を崩したときや睡眠不足が続いたときに歯ぐきが腫れることがある。
- ストレスが免疫機能を低下させる
- ストレスを感じると、体内でコルチゾールというホルモンが分泌される。
- コルチゾールの増加は、免疫力を低下させる原因となるため、歯周病が悪化しやすくなる。
- 加齢による免疫機能の低下
- 年齢を重ねると、免疫細胞の働きが弱くなり、歯周病菌に対する抵抗力が落ちる。
- 高齢者は特に歯周病が進行しやすく、歯を失うリスクが高まる。
免疫力を高めるための習慣
- 栄養バランスの良い食事を摂る(ビタミンC・D、たんぱく質を意識)
- 質の良い睡眠をとる(7〜8時間が理想)
- ストレスを溜めない(運動や趣味を楽しむ)
- 適度な運動を行う(血流を良くし、免疫力を向上させる)
健康寿命を延ばすために歯ぐきを守る重要性
近年、「健康寿命」という言葉が注目されています。これは、病気や介護に頼らず、自立した生活を送れる期間のことを指します。歯と歯ぐきの健康は、健康寿命を延ばす上で重要な要素の一つとされています。
歯ぐきの健康と健康寿命の関係
- 歯が多いほど長生きする
- 厚生労働省の調査によると、自分の歯が20本以上残っている人は、健康寿命が長くなる傾向がある。
- 歯が多く残っているほど、しっかり噛めるため、栄養を十分に摂取できる。
- 噛む力が認知症予防につながる
- しっかり噛むことで脳が刺激され、認知機能の低下を防ぐ効果が期待されている。
- 歯を失うと噛む回数が減り、脳の働きが低下するリスクが高まる。
- 歯周病を防ぐことで誤嚥性肺炎を予防できる
- 高齢者に多い誤嚥性肺炎は、口腔内の細菌が気道に入り込むことで発症する。
- 歯周病が進行すると、口腔内の細菌数が増え、誤嚥性肺炎のリスクが高まる。
健康寿命を延ばすためにできること
- 定期的な歯科検診を受け、歯周病を予防する
- しっかり噛む習慣をつけ、歯を健康に保つ
- 口腔内の清潔を維持し、全身の健康を守る
歯ぐきの健康は、単に歯を守るだけでなく、全身の健康や長寿にも関わる重要な要素となります。
まとめ:歯ぐきが下がる前にできることを始めよう!

早期発見・早期対策が歯ぐきを守るカギ
歯ぐきの後退は、ゆっくりと進行するため、気づいたときにはすでに進行しているケースが多い。しかし、早期に発見し適切な対策を取ることで、歯ぐきの後退を食い止め、健康な状態を維持することが可能である。
歯ぐきの後退を早期に発見するポイント
- 歯が長く見えるようになった:鏡を見たときに、以前より歯が長く見えると感じた場合、歯ぐきが下がり始めている可能性がある。
- 歯と歯の間にすき間ができる:歯ぐきが下がることで、歯と歯の間にすき間ができ、食べかすが詰まりやすくなる。
- 知覚過敏が気になるようになった:冷たい飲み物や食べ物を口にしたときにしみるようになったら、歯ぐきが下がって象牙質が露出している可能性がある。
- 歯磨きの際に歯ぐきから出血する:健康な歯ぐきは歯磨きで簡単に出血しないため、歯ぐきからの出血は歯周病のサインかもしれない。
- 口臭が気になる:歯周病が進行すると、口臭が強くなることがあるため、普段より口臭が気になる場合は要注意。
歯ぐきの後退が進行しないために、早期に歯科医院でチェックを受けることが大切である。
自宅ケアとプロの治療を組み合わせるのがベスト
歯ぐきの健康を守るためには、日々のセルフケアと歯科医院での専門的なケアを組み合わせることが重要である。
自宅でできる歯ぐきケアのポイント
- 適切なブラッシングを行う
- 強すぎるブラッシングを避け、歯ぐきに優しい歯磨きを心がける。
- 柔らかめの歯ブラシを使い、45度の角度で毛先を歯ぐきの境目に当てながら優しく磨く。
- デンタルフロスや歯間ブラシを活用する
- 歯と歯の間の汚れを取り除き、歯ぐきを健康に保つ。
- 歯間の広さに応じて、フロスや歯間ブラシを使い分ける。
- 栄養バランスの良い食事をとる
- ビタミンC(歯ぐきを強くする)、カルシウム(歯の健康を維持)、たんぱく質(歯ぐきの再生を助ける)などをバランスよく摂取する。
- ストレスを管理し、歯ぎしりを防ぐ
- 歯ぎしりは歯ぐきに過剰な負担をかけるため、ストレスを溜めない生活を心がける。
- 必要に応じてナイトガード(マウスピース)を使用し、歯ぐきへの負担を軽減する。
歯科医院で受けるべきプロのケア
- 定期的な歯科検診(3〜6ヶ月に1回)
- 歯周病の早期発見・早期治療のために欠かせない。
- 歯ぐきの状態や歯周ポケットの深さをチェックし、必要に応じて治療を行う。
- スケーリング・ルートプレーニング(歯石除去)
- 歯ブラシでは落とせない歯石を除去し、歯周病の進行を防ぐ。
- ルートプレーニングでは、歯周ポケット内の歯石や細菌を徹底的に取り除く。
- 歯周組織再生療法(エムドゲイン・リグロス)
- 歯周病によって失われた歯槽骨や歯ぐきを再生する治療法。
- 軽度〜中等度の歯ぐきの後退に有効。
健康な歯ぐきを維持して、美しい笑顔を手に入れよう!
歯ぐきが健康であることは、歯の寿命を延ばすだけでなく、美しい笑顔や自信につながる。健康な歯ぐきを維持することのメリットは数多くある。
健康な歯ぐきを維持するメリット
- 美しい口元をキープできる
- 歯ぐきがしっかりしていると、歯が長く見えることなく、バランスの良い口元を維持できる。
- 知覚過敏を防ぎ、快適に食事ができる
- 歯ぐきがしっかり歯を覆っていると、象牙質の露出が少なくなり、冷たいものや熱いものを食べても痛みを感じにくくなる。
- 歯の寿命を延ばし、将来的な治療費を抑えられる
- 歯ぐきを守ることで、歯のぐらつきや抜歯のリスクを減らし、長く健康な歯を保つことができる。
- 早めのケアを行うことで、将来的にインプラントや入れ歯などの高額な治療を避けられる可能性がある。
- 全身の健康につながる
- 歯周病を予防することで、糖尿病や心疾患、誤嚥性肺炎のリスクを軽減できる。
歯ぐきの健康は、一生の財産である。今からできるケアを習慣化し、将来の健康と美しい笑顔を守ることが大切だ。
再治療0%を追求した歯科治療専門クリニック
埼玉県さいたま市の歯医者・歯科
監修:関口デンタルオフィス大宮
電話番号:048-652-1182
*監修者
関口デンタルオフィス大宮
*経歴
・2008年 日本大学歯学部卒業
日本大学歯学部臨床研修部入局
・2009年 日本大学歯学部補綴学第一講座入局
専修医
顎関節症科兼任
・2014年 同医局退局
関口デンタルオフィス開院
*所属学会
*スタディークラブ
・CIDアクティブメンバー(Center of Implant Dentistry)