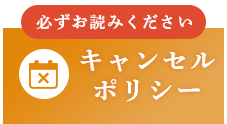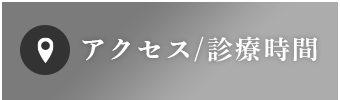「歯を抜きたくない」と悩む方へ。重度歯周病でも歯を残すための選択肢
- 2025年10月20日
- 未分類
目次
歯がグラグラ、歯茎から膿…「もう抜くしかない」と諦めていませんか?

「重度歯周病」と診断され、抜歯を勧められた不安
歯科医師から「重度歯周病のため、この歯は抜くしかないかもしれません」と告げられた時の衝撃とご不安は、計り知れないものがあるでしょう。長く使ってきたご自身の歯を失うかもしれないという事実は、すぐには受け入れがたいものです。「本当に抜かないといけないのか」「他に歯を残すための治療法はないのか」と、情報を探されているかもしれません。抜歯は最終手段であり、ご自身の歯を守りたいというお気持ちは当然のことです。まずはそのお気持ちを受け止め、諦めずに歯を残す可能性を探ることが大切です。
自分の歯で、これからも食事を楽しみたいという願い
おせんべいをバリバリと食べたり、お肉をしっかり噛みしめたり。ご自身の歯で自由に、美味しく食事を楽しめることは、当たり前のようでいて、実はかけがえのない喜びです。重度歯周病が進行し、歯がグラグラしたり痛みが出たりすると、思うように噛めなくなり、食べる楽しみが失われがちです。だからこそ、「これ以上自分の歯を失いたくない」「できる限り自分の歯で噛み続けたい」という願いは、生活の質(QOL)を維持する上で非常に切実です。歯を残すという希望は、単に歯の本数を保つだけでなく、食べる楽しみ、話す喜びを守ることにも繋がっています。
「歯を残す」可能性を諦める前に知ってほしいこと
「重度歯周病だから、もう抜歯しかない」とすぐに諦める必要はありません。確かに重度歯周病は、歯を支える大切な骨が大きく失われた深刻な状態です。しかし、現代の歯周治療には、歯を残すことを目指す様々な選択肢があります。徹底的な歯周基本治療はもちろん、状態によっては歯周外科手術や、失われた骨などの歯周組織の再生を試みる「再生療法」といった先進的な治療法も存在します。「抜かない」で済む可能性、あるいは歯の寿命を延ばせる可能性が残されているかもしれません。まずはご自身の歯と歯周組織の状態を精密に検査し、どのような治療法が適用できるのか、専門家の意見を詳しく聞くことが重要です。
なぜ「重度歯周病」になってしまうのか?
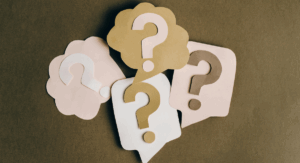
歯周病は静かに進行する「歯を支える骨の病気」
歯周病は、初期段階では痛みなどの自覚症状がほとんどなく進行するため、「静かなる病気(SilentDisease)」と呼ばれます。これは単なる歯ぐきの病気ではなく、歯周病菌という細菌によって引き起こされ、歯を支える土台である「歯槽骨(しそうこつ)」が破壊されていく感染症です。この骨の喪失こそが、最終的に歯がグラグラになり、抜歯に至る主な原因です。重度歯周病の治療法の目的は、この骨の破壊を食い止め、可能な限り歯を残す(抜かない)ことです。自覚症状がなくても進行している可能性があるため、早期発見と適切な対処が重要になります。
「重度」とはどのような状態?(歯周ポケット・骨吸収)
歯周病が「重度」と診断されるのは、歯を支える組織に深刻なダメージが及んでいる状態です。主な指標は、「歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)」の深さと、レントゲンで確認される「歯槽骨の吸収(骨が溶けること)」の程度です。健康な歯周ポケットの深さは通常1〜3mmですが、重度歯周病では6mm以上に達することが多く、歯ぐきの下で骨が広範囲に破壊されていることを示します。これにより歯は支えを失い、グラグラと動き始めます。重度歯周病の治療法は、ポケットを浅くし、これ以上の骨吸収を食い止めることを目指します。状態によっては失われた骨の再生療法も歯を残す(抜かない)選択肢となります。
歯磨きだけでは防げない?進行に関わる要因
プラーク(歯垢)の蓄積による不十分な清掃が歯周病の主な原因ですが、重度歯周病への進行には、歯磨きだけではコントロールできない他の要因も関わっています。例えば、「喫煙」は血流を悪化させ、歯周組織の修復能力を低下させます。「糖尿病(特に血糖コントロールが不良な場合)」は免疫力を低下させ、炎症を悪化させます。その他、「遺伝的な要因」「ストレス」「特定の薬剤の服用」「噛み合わせの問題(咬合性外傷)」なども進行を加速させるリスク因子です。これらの要因があると、丁寧な歯磨きだけでは進行を抑えきれない場合があります。したがって、重度歯周病で歯を残す(抜かない)ための治療法は、専門的な清掃や外科処置、場合によっては再生療法と並行して、これらのリスク因子への対策も含めた包括的なアプローチが必要となります。
重度歯周病で「歯が抜ける」メカニズム

歯周ポケットの深化と、歯石・細菌の温床
歯周病の始まりは、歯と歯ぐきの境目に蓄積したプラーク(歯垢)です。プラーク内の細菌が出す毒素によって歯ぐきに炎症が起き(歯肉炎)、進行すると歯と歯ぐきの付着が剥がれて「歯周ポケット」と呼ばれる溝が深くなります。重度歯周病では、このポケットが非常に深くなり、歯ブラシの毛先が届かない「聖域」となります。この深いポケットの中には、硬い歯石が付着し、酸素を嫌う性質を持つ悪玉の歯周病菌が大量に繁殖します。まさに細菌の温床となり、炎症を持続・悪化させる原因となります。歯を残すための治療法は、まずこのポケット内の徹底的な清掃から始まります。
歯槽骨(歯を支える骨)が溶けていく過程
深くなった歯周ポケット内の細菌が出す毒素や、それに対する体の免疫反応(炎症反応)が、歯を支える重要な土台である「歯槽骨(しそうこつ)」を破壊していきます。これは、細菌が直接骨を溶かすというよりは、慢性的な炎症の結果として、骨を溶かす細胞(破骨細胞)が活性化されることによります。重度歯周病では、この骨の吸収(破壊)が広範囲かつ深くまで進行し、歯の根(歯根)を支える骨の量が著しく減少します。レントゲン写真で見ると、歯の周りの骨のレベルが大きく下がっているのが確認できます。歯を残す(抜かない)ためには、この骨の破壊を食い止め、場合によっては失われた骨の再生療法も検討する治療法が必要となります。
最終的に歯が支えを失い、自然に抜け落ちることも
歯槽骨の破壊が進行し、歯を支える骨がほとんどなくなってしまうと、歯はグラグラと大きく動揺し始めます。食事の際に痛みを感じたり、硬いものが全く噛めなくなったりします。そして、最終的にはわずかな力でも、あるいは何もしなくても、歯が自然に抜け落ちてしまうことがあります。これが重度歯周病の末期的な状態です。「抜かない」ことを希望されても、支えとなる骨が完全に失われてしまった場合は、残念ながら歯を残すことが物理的に不可能となります。だからこそ、重度歯周病と診断された場合でも、少しでも骨が残っている段階で適切な治療法(歯周基本治療、外科治療、再生療法など)を開始することが、歯を残すための最後のチャンスとなるのです。
「歯を残す」ための第一歩:徹底的な歯周基本治療

抜かない治療の基本は「感染源の除去」
重度歯周病であっても、「歯を残す(抜かない)」ための治療の最も基本的な考え方は、「感染源である歯周病菌とその温床(プラーク・歯石)を徹底的に除去すること」に尽きます。歯周病は細菌感染症であり、歯を支える骨を溶かす根本的な原因は細菌です。したがって、どのような治療法(外科治療や再生療法を含む)を選択するにしても、まずこの感染源を取り除く「歯周基本治療」がすべての土台となります。この基本治療によって歯ぐきの炎症が改善し、進行が食い止められれば、抜歯を回避できる可能性が高まります。安易に抜歯を選択する前に、この基本に立ち返ることが重要です。
歯周ポケット内の歯石・プラークを取り除く(SRP)
歯周基本治療の中核となるのが「SRP(スケーリング・ルートプレーニング)」と呼ばれる処置です。重度歯周病では、歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)が非常に深くなっており、その内部の歯根面には、歯ブラシでは到底届かない硬い歯石や、細菌の塊であるプラーク(バイオフィルム)が付着しています。SRPは、専用の器具(スケーラーやキュレット)を用いて、このポケット深部の歯石や汚染された歯根面を丁寧に除去し、滑らかにする治療法です。これにより、歯周病菌の温床を取り除き、歯ぐきの炎症を改善させ、ポケットの深化を防ぎます。歯を残す(抜かない)ためには、この目に見えない部分の徹底的な清掃が不可欠です。麻酔下で行うこともあります。
なぜセルフケア(歯磨き)の改善が不可欠なのか
歯科医院での専門的なクリーニング(SRPなど)は非常に重要ですが、それだけで重度歯周病が治癒するわけではありません。治療の成功、そして歯を残す(抜かない)ためには、患者さんご自身の毎日の「セルフケア(歯磨き)」の質を飛躍的に向上させることが不可欠です。なぜなら、歯科医院で一時的に細菌を除去しても、日々のケアが不十分であれば、プラークはすぐに再び蓄積し、炎症が再発してしまうからです。これは、外科治療や再生療法といった高度な治療法を行ったとしても同様です。正しいブラッシング方法、デンタルフロスや歯間ブラシの適切な使用法を習得し、毎日実践していただくこと。この患者さん自身の取り組みが、重度歯周病治療の成否を左右する最も重要な鍵となります。
基本治療で改善しない場合の「歯周外科治療」

外科的に感染源を除去し、清掃しやすい環境を作る
重度歯周病において、歯周基本治療(SRPなど)だけでは深い歯周ポケットの底に付着した歯石や細菌(感染源)を完全に取り除くことが難しい場合があります。このようなケースで「歯を残す(抜かない)」可能性を高めるための次のステップが「歯周外科治療」です。この治療法の主な目的は、歯ぐきを一時的に開くことで、歯根面や骨の欠損部を直接目で確認しながら、徹底的に感染源を除去することです。さらに、病的に深くなったポケットを浅くし、患者さんご自身や歯科衛生士が清掃しやすい環境(プラークコントロールしやすい環境)を整えることも重要な目的です。これにより、重度歯周病の進行を食い止め、将来的な再生療法への道を開くこともあります。
歯周ポケット掻爬術(そうはじゅつ)とは
歯周ポケット掻爬術は、歯周外科治療の中でも比較的侵襲(体への負担)が少ないとされる治療法の一つです。局所麻酔下で、主に歯周ポケットの内壁に存在する炎症性の組織(不良肉芽組織)を掻き出す(掻爬する)処置です。歯ぐきを大きく切開・剥離することは通常ありません。この治療法の目的は、炎症を引き起こす組織を除去することで、歯ぐきの腫れを引き締め、ポケットの深さをわずかに減少させることです。ただし、歯根面に付着した歯石の除去は、器具が届く範囲に限られ、直視下での処置ではないため、深いポケットや複雑な形態を持つ重度歯周病のケースでは、感染源の完全な除去が難しい場合があります。「歯を残す(抜かない)」ためのより確実な処置として、次に述べるフラップ手術が選択されることが多いです。
フラップ手術(歯肉剥離掻爬術)の目的と効果
フラップ手術(歯肉剥離掻爬術)は、中等度から重度歯周病において、歯周基本治療で改善が見られない場合に選択される代表的な歯周外科治療法です。局所麻酔下で歯ぐきを慎重に切開・剥離し(フラップを開き)、病変部を明視野(直接目で確認できる状態)にします。目的は主に3つあります。(1)歯根面にこびりついた歯石やプラーク、炎症性組織を徹底的に除去すること。(2)必要に応じて、歯周病によって不整になった骨の形態を整え、ポケットが再発しにくい環境を作ること。(3)骨の欠損が大きい場合には、この手術と同時に「歯周組織再生療法」を行い、失われた骨や歯周組織の再生を試みることです。効果として、歯周ポケットの大幅な改善、清掃性の向上、歯ぐきの炎症の鎮静が期待でき、「歯を残す(抜かない)」ための予後を大きく改善する可能性があります。
失われた骨を再生させる?「歯周組織再生療法」という選択肢

歯周病で失われた「歯を支える組織」を再生する治療法
重度歯周病によって歯を支える骨(歯槽骨)が大きく失われると、歯はグラグラになり、通常は抜歯が検討されます。しかし、特定の条件を満たす場合には、「歯周組織再生療法」という、失われた組織の再生を試みる治療法が存在します。この治療法は、単に骨の再生を目指すだけでなく、歯根表面のセメント質や、歯と骨をつなぐ歯根膜といった、歯を支えるために不可欠な組織全体の再生を図ります。これにより、歯を残す(抜かない)可能性を高め、ご自身の歯で噛み続ける未来を取り戻すことを目的とします。再生療法は、重度歯周病に対する先進的なアプローチの一つであり、希望の持てる選択肢となり得ます。
GTR法、エムドゲイン®︎ゲルを用いた再生療法の仕組み
歯周組織再生療法には、主に「GTR(GuidedTissueRegeneration)法」と「エムドゲイン®︎ゲルを用いる方法」という2つの代表的な治療法があります。GTR法は、歯周外科手術の際に、骨が失われた部分に特殊な「膜(メンブレン)」を設置する治療法です。この膜が物理的なバリア(壁)となり、治癒の早い歯ぐきの上皮細胞が骨の欠損部に入り込むのを防ぎます。これにより、骨や歯根膜といった、再生に時間のかかる組織が回復するためのスペースと時間を確保する仕組みです。一方、エムドゲイン®︎ゲルは、豚の歯胚(歯の芽)から抽出・精製したタンパク質(エナメルマトリックスデリバティブ)を主成分とした薬剤です。これを歯周外科手術時に、清掃した歯根面と骨の欠損部に塗布します。このタンパク質が、歯が生えてくる時(歯の発生期)と同様の環境を再現し、歯周組織の再生を促すと考えられています。どちらの治療法も、重度歯周病で失われた組織を再生させ、歯を残す(抜かない)ことを目指す点で共通しています。
再生療法が適応となる条件と限界点
歯周組織再生療法は、重度歯周病で歯を残す(抜かない)ための有力な治療法ですが、残念ながらどのようなケースにも適用できる万能な方法ではありません。成功のためにはいくつかの「適応条件」があり、「限界点」も存在します。適応条件として最も重要なのは、「骨の失われ方(骨欠損の形態)」です。再生療法は、主に垂直的に深く骨が失われた「垂直性骨欠損」や、歯の根が分岐している部分(根分岐部)の骨欠損など、再生のためのスペースが確保しやすい特定の形態で効果を発揮しやすいとされています。水平的に全体が下がってしまったような骨欠損の再生は非常に困難です。また、患者さんご自身の「全身状態が良好であること」、そして何よりも「徹底したプラークコントロール(セルフケア)が術後も継続できること」が大前提となります。喫煙は再生療法の成功率を著しく下げる原因となるため、禁煙が強く推奨されます。限界点として、再生療法を行っても、必ずしも期待通りの完全な再生が得られるとは限らないこと、再生の程度には個人差があることなどが挙げられます。
歯を残すためにできる、その他の治療法アプローチ

動揺(グラつき)が大きい歯を固定する「暫間固定」
重度歯周病によって歯を支える骨が大きく失われると、歯は指で押しただけでもグラグラと動揺(どうよう)するようになります。この状態では、食事の際に痛みが出たり、さらに動揺が大きくなったりするだけでなく、歯周組織の治癒を妨げる原因にもなります。「暫間固定(ざんかんこてい)」とは、このような動揺が大きい歯を、隣接する比較的安定した歯と接着剤やワイヤーなどで一時的に連結し、固定する治療法です。これにより、歯にかかる力を分散させ、動揺を抑えることで、(1)噛む機能の回復を助ける、(2)歯周外科治療や再生療法を行う際の歯の安静を図る、(3)治療後の治癒を促進する、といった効果が期待できます。あくまで「暫間的」な処置であり、根本的な歯を残す(抜かない)ための歯周病治療と並行して行われます。
歯にかかる負担を軽減する「噛み合わせ調整」
重度歯周病で歯を支える骨が弱っている場合、正常な「噛む力(咬合力)」であっても、その歯にとっては過大な負担(咬合性外傷)となり、病状をさらに悪化させる原因となることがあります。また、歯が動揺したり移動したりすることで、特定の歯だけが強く当たるような不自然な噛み合わせが生じていることも少なくありません。「噛み合わせ調整(咬合調整)」とは、強く当たりすぎている部分の歯の表面をごくわずかに削合(研磨)することで、全体の噛み合わせのバランスを整え、特定の歯への負担を軽減させる治療法です。これにより、歯の動揺を抑え、歯周組織へのダメージを減らし、歯を残す(抜かない)ための環境を整えます。再生療法などを行う場合にも、治療部位への過度な負担を避けるために重要となる処置です。
根分岐部病変への対応など、特殊なケースの治療法
奥歯(大臼歯)のように歯の根が複数に分かれている部分を「根分岐部(こんぶんきぶ)」と呼びます。重度歯周病が進行し、この根分岐部にまで骨の破壊が及んだ状態を「根分岐部病変」と呼びます。この部位は形態が非常に複雑なため、プラークコントロールが極めて難しく、通常の治療法では改善が困難なケースが多いです。歯を残す(抜かない)ためには、特殊なアプローチが必要となることがあります。例えば、歯周外科手術(フラップ手術)の際に、分岐部の清掃性を高めるために骨や歯肉の形態を修正したり、条件が合えば「歯周組織再生療法」を試みたりします。また、分岐部病変の進行度によっては、複数の根のうち、問題のある根だけを選択的に切断・除去する「ヘミセクション」や「トライセクション」、「ルートセパレーション」といった外科的な治療法によって、歯全体を抜かないで済むように部分的に歯を残すという選択肢もあります。
「歯を残す」治療を受けるための歯科医院選び

歯周病治療・再生療法に注力している医院の見分け方
重度歯周病で「歯を残す(抜かない)」ための治療、特に歯周外科手術や再生療法は、全ての歯科医院で行っているわけではありません。医院を選ぶ際には、その医院が歯周病治療にどれだけ注力しているかを見極めることが重要です。一つの目安として、歯科医師が歯周病に関する専門的な研修を受けているか、学会(日本歯周病学会など)の認定医・専門医資格を有しているかなどが挙げられます。また、医院のウェブサイトなどで、重度歯周病に対する具体的な治療法(歯周外科手術、GTR法やエムドゲイン®︎を用いた再生療法など)について、詳細な情報提供を行っているかも判断材料になります。「抜かない」ことを第一に考え、精密な診断・治療に必要な設備(CTやマイクロスコープなど)への投資や、治療後の長期的なメンテナンス体制の重要性を強調している医院は、歯を残すことに真摯に取り組んでいる可能性が高いと言えるでしょう。
精密な診査・診断(歯周ポケット測定、レントゲン、CT)の重要性
重度歯周病で「歯を残す(抜かない)」ことが可能かどうかを判断するためには、精密な診査・診断が不可欠です。まず、歯周ポケットの深さを1歯ずつ丁寧に測定し、歯ぐきの炎症の状態(出血や排膿の有無)を確認します。次に、レントゲン写真(デンタルX線写真やパノラマX線写真)で、歯を支える骨(歯槽骨)がどの程度失われているか(骨吸収の程度やパターン)を評価します。しかし、重度歯周病や再生療法を検討するケースでは、二次元的なレントゲンだけでは情報が不十分なことが多く、「歯科用CT」による三次元的な検査が極めて重要となります。CTでは、骨が失われた部分の形態(垂直的な骨欠損の有無など、再生療法の適応判断に不可欠)や、骨の厚み、神経や血管の位置などを立体的に、より正確に把握できます。これらの精密な情報を基に、歯を残すための最適な治療法を選択し、安全な治療計画を立案します。
治療計画、期間、費用について十分な説明があるか
重度歯周病で「歯を残す(抜かない)」ための治療は、多くの場合、複数回の通院と長い期間を要します。特に歯周外科手術や再生療法などの治療法は、その後の治癒期間やメンテナンスが成功の鍵を握ります。そのため、治療を開始する前に、担当の歯科医師から具体的で分かりやすい「治療計画」の説明を受けることが非常に重要です。説明には、現在の状態の診断結果、提案される治療法(基本治療、外科治療、再生療法など)とその根拠、考えられる他の選択肢(抜歯を含む)とそれぞれのメリット・デメリット、予想される治療期間の目安、そして必要な費用の総額(保険適用・適用外の内訳)が含まれているべきです。一方的な説明ではなく、患者さんの疑問や不安に丁寧に答え、十分に納得した上で治療に臨める(インフォームドコンセント)ような、信頼関係に基づいたコミュニケーションを重視する歯科医院を選ぶことが、歯を残すための長い道のりを共に歩む上で大切です。
重度歯周病・歯を残す治療に関するよくある疑問(FAQ)
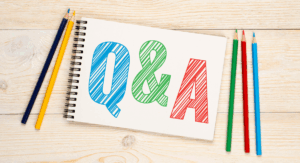
Q.重度歯周病の治療は痛みを伴いますか?
A.重度歯周病の治療、特に歯周ポケット深部の歯石除去(SRP)や歯周外科手術、再生療法などの治療法は、通常、局所麻酔を十分に行いますので、処置中に痛みを感じることはほとんどありません。ご安心ください。ただし、治療後、麻酔が切れると多少の痛みや腫れ、歯がしみる感じが出ることがあります。その場合は処方された鎮痛剤を服用していただくことで、多くは日常生活に支障なくコントロール可能です。痛みの感じ方には個人差がありますが、「歯を残す(抜かない)」ための治療ですので、痛みを最小限に抑えるよう配慮します。
Q.再生療法を行えば、必ず歯は残せますか?
A.歯周組織再生療法は、重度歯周病で失われた歯を支える骨などの組織の再生を促し、「歯を残す(抜かない)」可能性を高めるための有効な治療法の一つです。しかし、残念ながら「必ず」歯を残せると保証できるものではありません。再生療法の効果は、骨の失われ方(骨欠損の形態)、患者さんのお口の清掃状態、全身の健康状態(糖尿病や喫煙など)、そして術後のケアなど、多くの要因に左右されます。適応となるケースも限られます。再生療法はあくまで歯を残すための「可能性を高める」治療法であり、成功率を高めるためには術後の徹底したセルフケアと定期メンテナンスが不可欠です。
Q.治療期間はどのくらいかかりますか?
A.重度歯周病の治療期間は、病状の程度や選択する治療法によって大きく異なります。まず、歯周基本治療(SRPやブラッシング指導など)だけで数週間から数ヶ月かかります。基本治療で改善が見られない場合、歯周外科手術や再生療法に進むと、さらに数ヶ月の治癒期間が必要です。全体の治療期間としては、半年から1年以上かかることも珍しくありません。「歯を残す(抜かない)」ためには、焦らず根気強く治療に取り組むことが重要です。また、治療後も安定した状態を維持するための定期的なメンテナンスが長期にわたって必要になります。
Q.治療が終わった後も通院は必要ですか?
A.はい、重度歯周病の治療において、治療後の「定期的なメンテナンス(SPT:サポーティブペリオドンタルセラピー)」は極めて重要です。歯周病は、高血圧や糖尿病のように、完治するというよりは「コントロールしていく」慢性疾患に近い側面があります。たとえ歯周外科手術や再生療法などの高度な治療法によって一時的に状態が改善しても、日々のケアが不十分だったり、定期的な専門的クリーニングを怠ったりすると、容易に再発してしまいます。歯を残す(抜かない)ためには、治療後も通常3〜4ヶ月に一度(状態によってはそれ以上の頻度で)通院していただき、専門的なクリーニングや検査を受け、良好な状態を維持していくことが不可欠です。
諦めるのはまだ早い。「抜かない」ための可能性を信じて

重度歯周病でも「歯を残す」ための選択肢は存在する
重度歯周病と診断され、抜歯しかないかもしれないと告げられても、すぐに諦める必要はありません。現代の歯周治療には、「歯を残す(抜かない)」ことを目指す様々な治療法の選択肢が存在します。徹底的な歯周基本治療はもちろんのこと、歯周外科手術や、失われた骨や歯周組織の再生を試みる「再生療法」など、状態によっては適用できる可能性があります。これらの治療法によって、抜歯を回避できる、あるいは歯の寿命を延ばせる希望があります。ご自身の歯を守るための選択肢があることを、まずは知っていただきたいと思います。
治療の成功には、患者様自身の協力が不可欠
重度歯周病から「歯を残す(抜かない)」ための治療法は、歯科医師の処置だけで成功するものではありません。どんなに高度な治療(例えば再生療法)を行っても、その効果を維持し、長期的に歯を残すためには、患者さんご自身の積極的な協力、特に日々の徹底したプラークコントロール(歯磨きやフロスなど)が不可欠です。歯科医院での治療と、ご自宅でのセルフケアの両輪が揃って初めて、重度歯周病という難敵に立ち向かうことができます。治療の成功は、歯科医師と患者さんの二人三脚で勝ち取るものです。
まずは専門家に相談し、ご自身の歯の状態を知ることから
「歯を抜かないで済む方法はないだろうか」「自分の重度歯周病は、どの治療法なら歯を残す可能性があるのか」とお悩みなら、まず最初に行うべきことは、歯周病治療を専門とする、あるいは力を入れている歯科医師に相談することです。インターネットの情報だけで判断せず、精密な検査(歯周ポケット測定、レントゲン、必要であればCT検査など)を受け、ご自身の歯と歯周組織の「現在の状態」を正確に把握することが重要です。診断に基づき、歯を残すための具体的な治療法(再生療法の適応なども含め)や、その可能性、限界について、専門家から直接説明を聞くこと。それが、諦めずに前へ進むための第一歩となります。
再治療0%を追求した歯科治療専門クリニック
埼玉県さいたま市の歯医者・歯科
監修:関口デンタルオフィス大宮
電話番号:048-652-1182
*監修者
関口デンタルオフィス大宮
*経歴
・2008年 日本大学歯学部卒業
日本大学歯学部臨床研修部入局
・2009年 日本大学歯学部補綴学第一講座入局
専修医
顎関節症科兼任
・2014年 同医局退局
関口デンタルオフィス開院
*所属学会
*スタディークラブ
・CIDアクティブメンバー(Center of Implant Dentistry)