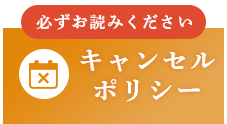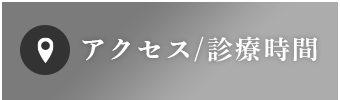噛むと痛い症状を放置するとどうなる?|リスク別に見る口腔ダメージ
- 2025年5月13日
- 未分類
目次
初期の痛み放置で進行する歯髄炎リスク

・虫歯が象牙質を越えて歯髄に到達するメカニズム
歯の表面エナメル質に始まった虫歯は、唾液中の細菌が産生する酸によって徐々に侵食が進み、やがて象牙質に到達します。象牙質には細い管状構造(象牙細管)が張り巡らされており、そこには歯髄から伸びた微細な神経線維や液体が通っています。虫歯が象牙質を越えると、細菌とその代謝産物がこれらの象牙細管を通じて歯髄内へ侵入し、歯髄を覆う結合組織や血管を直接刺激します。初期は炎症が限局的ですが、象牙質の露出が大きくなるにつれて炎症が拡大し、歯髄内に大量の炎症性サイトカインが放出されることで、強い痛みを感じるようになります。この段階を放置すると、細菌がさらに歯髄組織を破壊し、炎症は不可逆的に進行します。
・一過性の冷温痛覚が永続性疼痛に変わるプロセス
可逆性歯髄炎の段階では、冷たい水や熱い飲み物を飲んだときに一瞬だけ痛みを感じる程度ですが、治療を怠ると歯髄炎は不可逆性に移行します。炎症によって歯髄の血管透過性が亢進し、組織内に浮腫(水腫)が発生すると、内圧が高まって神経終末が圧迫されます。その結果、痛みが瞬間的なものから“ズキズキ”と持続的な拍動痛へと変化し、噛むときや歯に触れたときの痛みだけでなく、何もしなくても疼痛が続く状態になります。この拍動性の痛みは、炎症が根尖にまで波及し、根尖周囲の骨や歯根膜にダメージを与えているサインです。
・歯髄壊死から根尖病変への移行パターン
不可逆性歯髄炎を放置すると、壊死した歯髄組織は腐敗し、その排泄物が根尖孔から顎骨の中へ漏れ出します。細菌と炎症産物は、歯根膜を破壊しながら周囲の骨を溶かし“根尖病変”を形成します。初期は歯の軽い動揺や違和感だけですが、進行すると歯茎の腫れ、膿のにじみ、顔面の腫脹、さらには発熱や倦怠感など全身症状を伴うこともあります。根尖病変はレントゲンで透過像として観察でき、根管治療(神経を抜いて根管内を消毒・封鎖)を早期に行えば歯を救えますが、放置が長期化すると抜歯や外科的切開排膿が必要になるケースも増えます。したがって、冷温痛が強くなってからでは手遅れになる前に、初期の違和感段階で歯科を受診し、適切な検査と治療を受けることが歯を守る第一歩です。
歯根破折の見逃しによる抜歯リスク

・クラック発生から破折に至るストレス集中部位
日々の咀嚼や歯ぎしり、硬いものの噛みしめによって歯にかかる力は一部の部位に集中しやすく、特に奥歯の咬合面中央や歯頸部(歯と歯茎の境目)は“ストレス集中ゾーン”として知られています。これらの部位では、エナメル質の内側にある象牙質が微小亀裂(マイクロクラック)を生じやすく、亀裂は日常的な咀嚼ストレスを受けるたびに少しずつ拡大します。初期のマイクロクラックは痛みを伴わず、患者様自身も気づきにくいのが特徴ですが、クラックが象牙質を越えて歯根膜近くまで達すると、食事や歯磨きのわずかな圧力でも痛みが誘発されることがあります。この段階で適切な診断・治療を受けず放置すると、クラック線は歯根全体に広がり、最終的に歯根が完全に割れてしまう歯根破折を起こします。歯根破折は歯の支持組織を急速に失わせ、抜歯しか選択肢がなくなる深刻な状況を招きます。
・早期検知が難しい亀裂の症状サイン
歯根破折の初期症状は極めて微細で、多くの患者様がむし歯や歯周病と誤認しがちです。たとえば、冷たい飲みものを飲んだときに「キーン」と一瞬だけ痛む、歯を軽く叩いたときに部分的に鋭い痛みを感じる、あるいは硬い物を噛んだ瞬間にだけ生じる違和感や痛みなどが代表的ですが、これらは可逆性の症状と捉えられることが多く、受診を先延ばしにしてしまいます。さらに、クラックはエナメル質の下層に隠れているため、視診では発見できず、歯科医師でも症状のみでは判別が難しいことがあります。正確な診断には、マイクロスコープやルーペ下での精密探査、歯根模型や色素染色といった特殊検査が必要です。これらの検査を行わないまま進行すると、クラックは歯根部の深層へと広がり、細菌感染が根尖部に及んで痛みと支持組織破壊を急激に悪化させます。
・破折線に沿った骨吸収と支持組織崩壊
歯根破折が進行すると、破折線を通じて細菌や炎症産物が歯根膜や歯槽骨へ直接侵入し、局所的な炎症を引き起こします。X線写真では、破折線に沿って“縦走性透過像”が現れ、骨の透明度が増して見えるのが典型的な所見です。この透過像は、骨が細菌性の炎症反応で溶かされていることを示しており、支持組織の急速な崩壊を裏付けます。支持組織が失われると歯は動揺し、噛むたびに揺れと痛みが増し、最終的には咀嚼機能を維持できない状態に陥ります。さらに、骨吸収が顕著に進んだ部位では、インプラントなど将来的な修復オプションの適応範囲も狭まり、骨造成や長期的な高額治療を余儀なくされます。歯根破折による抜歯リスクを回避するためには、冷温痛や咬合時痛など初期の違和感を感じた時点で速やかに歯科医院を受診し、マイクロスコープやCT検査を含む精密な診断を受けることが重要です。早期発見・早期治療により、歯を失うリスクを大幅に減らすことができます。
歯周組織炎進行による歯槽骨吸収

・咬合時の過負荷とサイトカイン誘発作用
歯周炎が進行すると、咬合(噛み合わせ)時に歯にかかる力が炎症を起こした歯周組織へ直接伝わり、さらにダメージを悪化させます。炎症を起こした歯周ポケット内では、歯周病菌由来のリポ多糖(LPS)や毒素によってサイトカイン(IL-1β、TNF-α、IL-6など)が大量に分泌されます。これらのサイトカインは破骨細胞を活性化し、骨を溶かすプロセスを促進。噛むたびに生じる機械的刺激がサイトカイン分泌をさらに誘発するため、「咬合の過負荷 → サイトカイン増加 → 骨吸収促進」という悪循環が生まれ、歯槽骨(歯を支える顎骨)の吸収が加速します。炎症が深部へ及んだ歯周ポケットは深くなり、炎症メディエーターが骨縁下にまで影響を及ぼすことで、歯を支える土台そのものが失われつつある状態になります。
・ポケット深度増大とBOP陽性状態の持続
歯周組織炎の進行指標として歯周ポケット深度(PPD)とBOP(Bleeding on Probing:プロービング時出血)があります。健康な歯周組織ではポケット深度は1~3mm程度で出血もしませんが、炎症が中等度以上に進行するとポケット深度は4mm以上となり、プロービング時に出血や膿の排出を伴うBOP陽性状態が継続します。ポケット深度が深くなるほどプラークや歯石はさらに蓄積しやすくなり、細菌叢のアンバランスを助長して炎症が慢性化。BOP陽性率が30%を超えると炎症活動性が高いとされ、歯槽骨吸収のスピードも速まります。定期的なプロービング検査でポケット深度とBOPをモニタリングすることは、骨吸収の進行を早期に察知し、スケーリング&ルートプレーニング(SRP)など専門的クリーニング介入をタイムリーに行ううえで欠かせません。
・骨欠損が複合する多根歯周病の進行
臼歯部などで歯根が複数(多根)存在する歯では、歯根間にある溝(根分岐部)も歯周炎の影響を受けやすく、骨欠損は根分岐部から放射状に広がります。歯周ポケットが根分岐部にまで到達すると、歯根間結節や歯槽骨間の支持組織が急速に破壊され、縦走性欠損や階段状欠損など複雑な骨欠損パターンが形成されます。このような多根歯周病はSRPだけでは除去が難しく、フラップ手術やGTR(組織再生誘導法)などの再生療法を併用しないと骨縁が回復せず、歯の動揺が強まり最終的には抜歯となるケースが少なくありません。特に、第1大臼歯の根分岐部透過像は歯槽骨吸収が進んだ証拠であり、早期の外科的介入が歯の寿命を左右します。したがって、臼歯部の歯周組織炎を軽視せず、定期的なポケット測定とX線診査で根分岐部周囲の骨状態を評価し、適切なタイミングで専門的治療を受けることが歯を抜かずに守る鍵となります。
咬合バランス崩壊が招く顎関節症

・偏咀嚼による顎関節への偏荷重メカニズム
片側の歯の痛みを避けて反対側ばかりで咀嚼(偏咀嚼)を続けると、顎関節(こかくかんせつ)にかかる咬合力が一方に集中します。本来、咀嚼時の力は左右の顎関節と咀嚼筋群に均等に分散されて顎運動が円滑に行われますが、偏咀嚼では側対筋の過緊張を招き、咬合位と顎位の不一致を生じさせます。具体的には、咬合の中心位(ICP)から病的に変位した咬合位(CR)への移行が不自然になり、関節円板(ディスク)と下顎頭(マンディブラル・コンドル)の連動が乱れます。この結果、咬合力が部分的に増強された側の関節突起や関節窩にストレスが蓄積し、次第に関節包や靭帯が過伸展し、顎関節症(TMJ障害)の初期症状である関節周囲の違和感や軽度のクリック音を生じやすくなります。
・筋緊張–開口制限–クリック音連鎖の悪循環
顎関節周囲の過度なストレスは、咬筋や側頭筋、内側翼突筋といった咀嚼筋の慢性的な緊張を引き起こします。これらの筋肉は顎運動の駆動源であると同時に、顎関節の安定化にも関与していますが、緊張が高まると顎関節包内圧が上昇し、関節円板の正常なスライドが阻害されます。その結果、口を大きく開けたときに「パキッ」「ゴリゴリ」といったクリック音が発生しやすくなるとともに、開口制限(開口時の痛みや引っかかりを伴う可動域制限)が生じます。筋緊張とクリック音、開口制限は互いに悪循環を形成し、次第に痛みのネガティブ・フィードバックが中枢神経にも定着。慢性化すると頭痛や顔面痛、首肩こりなどの関連痛を引き起こし、顎関節症のQOL低下を加速します。
・慢性顎関節症が全身症状に波及する経路
顎関節症による慢性疼痛や機能障害は、局所的な問題に留まらず全身の健康にも影響を及ぼします。まず、慢性的な咀嚼筋緊張は頚椎のアライメント(配列)異常を招き、頚肩部の筋肉連鎖に緊張を波及させて肩こりや頭痛を増悪させます。また、睡眠中の歯ぎしり(ブラキシズム)が増加すると、睡眠の質が低下し、日中の疲労や集中力低下を招きます。さらに、顎関節症性疼痛は交感神経を過剰に刺激し、ストレスホルモン(コルチゾール)の慢性的な上昇を引き起こすことがわかっています。これによって免疫機能が抑制され、全身の炎症傾向が高まると、高血圧や消化器疾患、さらにはうつ状態や不安障害といった精神的健康リスクも増大します。
感染波及で生じるリンパ節腫脹・炎症

・根尖病変から周囲粘膜への膿瘍形成プロセス
歯髄壊死から根尖周囲に根尖病変が発生すると、壊死組織や細菌由来の毒素が根尖孔を介して顎骨内に漏れ出し、周囲の歯槽骨や歯根膜、粘膜組織に急性炎症を引き起こします。この炎症がさらに進行すると、歯根周囲の結合組織内に膿(膿瘍)がたまり、痛みや発赤、腫れを伴う化膿性炎症となります。患者様は歯の深部から「ずん」と鈍い痛みを感じ、患部の粘膜が盛り上がるように腫れてくることが特徴です。また、押すと圧痛を強く感じたり、膿が皮下に広がって皮膚の表面が赤紫色に変色したりする場合もあり、そのまま放置すると膿瘍が頬や顎下へ波及し、さらに深部組織へと広がる危険性があります。
・顎下リンパ節への経路と免疫反応
膿瘍内の細菌や炎症産物は、リンパ液の流れに乗って顎下リンパ節や頸部リンパ節へと運ばれます。通常はリンパ節内のマクロファージやリンパ球によって異物が捕捉・処理され、局所で免疫反応が完結しますが、急性感染が激しい場合はリンパ節自体が腫大し、触れるとゴロゴロとした硬さや圧痛を伴う「リンパ節腫脹」を引き起こします。このリンパ節腫脹は、顎下部の膨隆として自覚されやすく、首を動かすと痛むこともあります。リンパ節の腫れが長引く場合は、免疫系の過負荷を示すサインであり、全身性の抗菌治療や局所の切開排膿が必要になることもあります。
・全身発熱・倦怠感を伴う急性感染症状
歯性感染がリンパ節に波及すると、局所反応にとどまらず全身的な症状を引き起こすことがあります。炎症性サイトカイン(IL-1、TNF-αなど)は血中に放出され、視床下部の体温調節中枢を刺激して発熱を招くほか、肝臓での急性相タンパク質合成を促進し、C反応性蛋白(CRP)が上昇します。これに伴い、患者様は全身倦怠感や食欲不振、頭痛、関節痛などを感じやすくなり、重症化すると敗血症のリスクも否定できません。特に糖尿病や免疫抑制状態にある方では、局所感染が短期間で全身へ波及しやすいため、早急に歯科医院を受診して抗菌薬投与や膿瘍の切開排膿、必要に応じた入院管理を受けることが治療成功の鍵となります。
栄養吸収障害と消化器ストレスの増大

・咀嚼効率低下が食物破砕能率に与える影響
噛むと痛い状態が続くと、無意識に弱い側でのみ咀嚼する「偏咀嚼」や、咀嚼そのものを避ける「咀嚼回避」行動が増えます。本来、歯と歯がかみ合って食塊を細かく砕き、唾液と混ぜ合わせることで消化酵素(アミラーゼやリパーゼ)が食物に十分に作用できるようになります。しかし、咀嚼効率が低下すると食塊が大きいまま胃へ送られ、消化管内での分解にかかる負担が大きくなります。十分に咀嚼されない食物は、胃酸分泌を過剰に刺激することで胃粘膜を傷つけやすく、胃もたれや胸やけの原因となります。また、未処理の大きな食塊は腸管に到達した際に消化吸収率を低下させ、ビタミン、ミネラル、アミノ酸といった基本的栄養素が十分に取り込まれないことで、身体全体のエネルギー代謝や免疫機能にも悪影響を及ぼします。
・柔らかい食事偏重による栄養素偏在リスク
咀嚼痛を避けるためにおかゆ、スープ、ヨーグルトなどの柔らかい食品に偏ると、食事のバリエーションが制限され、必須アミノ酸や必須脂肪酸、食物繊維、カルシウム、鉄、ビタミンB群など多様な栄養素が不足しがちになります。特にたんぱく質不足は、抗体やホルモン、酵素の原料であるアミノ酸の供給不足を招き、免疫力低下や傷の治癒遅延、筋肉量減少などを引き起こします。さらに、食物繊維の摂取不足は腸内環境を悪化させ、有害菌優勢となることで短鎖脂肪酸の産生が低下し、腸粘膜バリア機能が弱体化します。このような腸内環境の悪化は過敏性腸症候群(IBS)や便秘、慢性的な下痢を招き、加えてビタミンKやビタミンB12の合成にも支障を来し、全身性の栄養不足と代謝異常を助長します。
・消化酵素分泌–腸内環境悪化の連鎖反応
咀嚼により十分に細かくされた食塊は、舌と咽頭の運動によってスムーズに胃へ送られ、その刺激に応じて胃腺から胃酸、ペプシノーゲン、リパーゼが適切に分泌されます。しかし、咀嚼不良により大きな食塊が胃に到達すると、機械的な分解が不十分なうえ、胃酸の分泌が過度に亢進して胃粘膜が傷つきやすくなり、慢性的な胃炎や胃潰瘍のリスクが高まります。さらに、十二指腸や小腸での消化吸収プロセスでも、膵液や胆汁分泌のシグナルが乱れ、脂質や炭水化物の分解効率が低下。未消化の栄養素が大腸へ流入すると、腸内細菌の代謝産物としてガスや有害なフェノール類、インドール類が過剰に産生され、腸管粘膜に炎症を引き起こします。この炎症が慢性化すると、リーキーガット症候群(腸漏れ)を誘発し、腸管バリアが破綻して細菌成分や毒素が血中に漏出。これが全身性の低度炎症を助長し、メタボリックシンドロームや糖尿病、自己免疫疾患の発症リスクを上昇させます。
発音・コミュニケーションへの障害

・痛み部位による舌—口蓋—歯列協調の乱れ
噛むと痛い歯を避けるために、無意識に舌を痛みのない側へ寄せて咀嚼や発音を行う「代償運動」が生じます。本来は舌先が上顎の前歯切縁や口蓋隆起に軽く触れて「サ」「タ」「ラ」行などを発音しますが、痛みを避けると舌は動線を変えてしまい、空洞的な発音になったり、舌先が正しい位置に届かずに摩擦音が不十分になったりします。さらに「ガ」「カ」「ナ」「タ」行の軟口蓋や軟組織接触も、舌の運動範囲が偏ることで不安定になり、声がこもったり息漏れが強くなったりすることがあります。このように、痛みをかばう咀嚼パターンの変化は、日常の会話中にも常に舌と歯列、口蓋の精緻な協調が必要な部位を乱し、耳にはっきり聞き取れない発音を繰り返す原因となります。
・音声明瞭度低下と心理的ストレス
発音が不明瞭になると、相手に「聞き取れない」と繰り返し問われたり、「何度も聞き返して失礼」と遠慮した言い方を強いられたりして、話すたびにストレスを感じるようになります。特にビジネスの電話や会議、プレゼンテーションの際には、自信を持って発言できず、声のトーンも小さく硬くなりがちです。これは声帯にも緊張を連鎖させ、結果として声質のこもりやかすれを招き、さらに明瞭度が落ちるという悪循環を生みます。聞き返されるたびに自己効力感が低下し、「また聞き返されるかもしれない」という予期不安から口元を隠しがちになり、顔の表情までも制限されることがあります。結果として、会話のテンポが乱れ、相手とのアイコンタクトやジェスチャーも自然さを失い、コミュニケーション全体の質が低下します。
・社会生活—対人関係への影響パターン
発音障害や口元の痛みによってコミュニケーションに支障が生じると、家族や友人、同僚との日常会話を楽しめなくなり、徐々に会話の頻度を減らすようになります。そうした「コミュニケーションの回避」は本人だけでなく、相手にも「反応が薄い」「元気がない」という誤った印象を与え、関係性にヒビを入れることがあります。また、集団での飲み会や食事会では会話の中心になりにくく、自己紹介やスモールトークにも消極的になりがちです。こうした場面で孤立感を覚えると、心理的な負担はさらに増し、引きこもり傾向や抑うつ状態へ進むリスクも高まります。特に口元は「笑顔」「表情」「声」の三要素が重なって相手に影響を与える部位であり、機能不全が長引くと「もう人前で話さない方がいいかも」という自己制限思考に陥ります。このような社会的・心理的負のスパイラルを断ち切るには、早期に痛みの原因を歯科医師に相談し、正常な噛む機能と発音機能を回復することが何よりも重要です。
審美性低下が及ぼす精神的健康リスク

・口元の痛みに伴う笑顔抑制–自尊感情低下
噛むと痛い状態が続くと、患者様は無意識に口元を手で覆ったり、大きく口を開けて笑うことを避けたりするようになります。口角を上げて自然に笑う動作は、脳へ「快適」「安心」というシグナルを伝える役割を果たしており、笑顔を作ることでセロトニンやオキシトシンといったポジティブホルモンの分泌が促進されることが知られています。しかし、痛みによって笑顔を抑制するとこのフィードバックループが断たれ、謎の不快感や孤独感から自己肯定感が徐々に低下していきます。実際に、笑顔が減ると「自分は楽しそうに見えない」「他人に良い印象を与えられない」というネガティブな自己評価が強まりやすく、対人関係の場面で自然な表情が出せなくなってしまいます。このように、口元の痛みが審美性の低下を招くことで、自尊感情の喪失と精神的ストレスの増大という二次的問題を引き起こします。
・器具・マウスガード無しでの応急避難行動
痛みを軽減しようとマウスガードや簡易的なガーゼ噛ませなど、市販の器具を自己判断で使用すると、咬合バランスをさらに乱し、歯列や顎関節への負荷を助長するケースがあります。適合していないマウスガードは歯面を均等に覆えず、かえって一部に過度の圧が集中して痛みを悪化させることも少なくありません。また、ガーゼをかませ続けると唾液分泌が阻害され口腔内乾燥を招き、二次的に口臭や粘膜トラブルを引き起こします。これらの“応急避難行動”は、患者様自身の不安を一時的に和らげるものの、根本的な解決には至らず、かえって精神的負担を増やす要因となります。専門家の診断と適切なカスタムメイドのガード装着が不可欠です。
・長期不快感と抑うつ傾向の関連性
慢性的な口腔内の痛みは、睡眠の質を悪化させ、日中の疲労感や集中力低下を招きます。持続的な痛みや違和感はコルチゾールなどのストレスホルモン分泌を増大させ、交感神経の緊張状態が続くことで全身のホメオスタシス(恒常性)が乱れ、抑うつ傾向を高めることが研究で示されています。また、慢性痛を抱えることで「もう自分の身体は信じられない」という無力感や絶望感が生まれ、社会参加意欲の低下、引きこもり傾向、さらには人間関係の断絶につながるリスクもあります。口腔の痛みは単なる局所症状ではなく、精神の健康をも蝕む重大な問題です。早期に歯科専門医のもとで原因を明確にし、適切な治療を受けることが、身体だけでなく心の健康を守るためにも不可欠です。
放置による治療難易度の飛躍的上昇

・単純処置から外科的治療へのステージシフト
噛むときの軽度の痛みを「そのうち治る」と放置すると、当初はコンポジットレジン充填や単純なスケーリングといった比較的低侵襲の処置で済んだものが、やがて根管治療や歯周外科、さらには歯根端切除術やインプラント埋入を伴う大規模な手術へと格段にステージが上がります。たとえば、象牙質まで達した虫歯であれば早期なら詰め物で修復できますが、そのまま進行して歯髄炎を発症すると、神経を抜く根管治療(3~5回の通院が必要)に移行します。さらに根尖部に膿瘍ができて根尖病変を併発すると、歯根の先端を切除し、歯槽骨を一部削る外科的歯根端切除術が必要になることがあります。これらの外科的処置は、術中の麻酔量や術後の疼痛管理、創部ケアの手間が大幅に増大し、身体的・精神的負担も飛躍的に高まります。
・治療期間延長と通院回数増加のコスト
早期であれば1~2回の通院で完了した処置が、放置の結果として各種専門治療を組み合わせた複数ステージの包括的治療へと拡張します。根管治療では感染根管内を徹底的に消毒するために毎回、薬剤充填-洗浄-再充填を繰り返し、合計で4~6回の通院が必要になることがあります。歯周外科や歯根端切除術では、術前のCT検査・血液検査、手術当日、術後の抜糸・再評価でさらに3~4回、合計で通院が8~10回に及ぶことも珍しくありません。これにより、交通費や休暇取得による機会損失、時間的コストが累積的に増加し、患者様の日常生活や仕事、家事・育児との両立が困難になります。
・併行する全身疾患管理とのスケジュール調整
高齢者や糖尿病・心疾患を抱える患者様は、抗凝固薬、抗血小板薬、降圧薬、インスリンや経口血糖降下薬などを服用しているケースが多く、歯科治療に先立って内科医との連携が不可欠です。放置により病変が深刻化すると、止血リスクの高い処置(抜歯や歯根端切除、歯周外科)を行う際に、内服薬の一時中断や用量調整が必要となり、内科受診による別途スケジュール調整が発生します。さらに、術後の抗生剤投与や痛み止め服用に関しても、腎機能や肝機能のモニタリングが必要となり、内科と歯科の受診日が重なることで日程が複雑化します。結果として、歯科治療単独で済んだ早期とは異なり、全身管理を併行するマルチタスクが患者様の心理的・時間的負担を増大させます。
Q&Aで学ぶ!放置リスクのよくある疑問

・Q1: 痛みが軽いから放置しても大丈夫?
噛むときに感じる「少しの違和感」や「軽い鈍痛」は、実は口腔内で病変が静かに進行しているサインかもしれません。初期の虫歯はエナメル質を越えて象牙質に到達すると、象牙細管を介して歯髄に炎症を引き起こしやすくなります。最初は冷たいものを飲んだときの一過性の痛み程度でも、放置すると歯髄炎が不可逆性に進行し、ズキズキと続く疼痛や拍動痛に変わります。歯周病なら歯肉の軽い腫れや出血が「歯磨きのせいかな」と見逃されがちですが、歯周ポケットの深部では細菌が繁殖し、サイトカインによる骨吸収が進むことで、知らぬ間に歯槽骨が溶かされていきます。軽度の痛みや違和感を感じた段階で受診しないと、根管治療や外科的介入が必要になるリスクが飛躍的に高まるため、「軽いから…」と後回しにせず、初期症状の段階で専門家に相談することが大切です。
・Q2: 鎮痛薬で痛みが和らいだら治ったと言える?
市販の鎮痛薬(NSAIDsなど)を用いると炎症性の痛みを一時的に抑えられますが、これはあくまで症状の“覆い隠し”に過ぎず、痛みの原因そのものを取り除く処置ではありません。鎮痛薬で痛みが引くと、「治った」と自己判断される方が多いですが、実際にはむし歯菌が歯髄や歯根膜を侵食し、根尖病変を形成している可能性があります。さらに歯根破折や歯周炎による骨吸収が進行すると、鎮痛薬への耐性ができて効果が薄れるばかりか、痛みの質が拍動痛や鋭い痛みに変わることも少なくありません。鎮痛薬で一時的に痛みを封じても、感染や組織破壊は進行し続けるため、疼痛緩和剤を併用しつつ速やかに歯科受診し、レントゲンや電気歯髄診断などの精密検査で原因を特定したうえで根本治療を行うことが必須です。
・Q3: 受診のタイミングはいつが最適?
「噛むと痛い」「冷たいものがしみる」「歯茎が腫れている」という初期症状を自覚したら、遅くとも48〜72時間以内には歯科医院に連絡しましょう。痛みを感じ始めると、細菌感染や炎症は歯髄や歯周組織の深部へと急速に拡大します。初期段階であれば、コンポジットレジンによる充填やプロフェッショナルクリーニング(PMTC)、局所的な抗菌薬塗布といった比較的短時間で終了するシンプルな処置で済みます。しかし受診が1週間以上先延ばしになると、根管治療や歯周外科手術、場合によっては歯根端切除や抜歯・インプラント治療が必要となり、通院回数や治療期間、費用が飛躍的に増大します。
なお、痛みの有無にかかわらず、以下のサインが見られたらすぐに受診してください:
・冷温痛が数秒以上続く
・噛むときに歯がグラつく感じがする
・歯茎が赤く腫れて膿がにじむ
再治療0%を追求した歯科治療専門クリニック
埼玉県さいたま市の歯医者・歯科
監修:関口デンタルオフィス大宮
電話番号:048-652-1182
*監修者
関口デンタルオフィス大宮
*経歴
・2008年 日本大学歯学部卒業
日本大学歯学部臨床研修部入局
・2009年 日本大学歯学部補綴学第一講座入局
専修医
顎関節症科兼任
・2014年 同医局退局
関口デンタルオフィス開院
*所属学会
*スタディークラブ
・CIDアクティブメンバー(Center of Implant Dentistry)